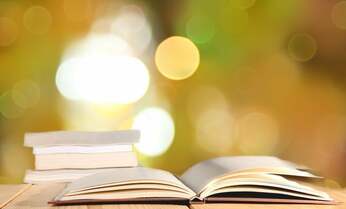
頭に花を咲かせるファッションが流行 人間が“植物化”する未来の話
※写真はイメージです (GettyImages)
文芸評論家の清水良典さんが選んだ「今週の一冊」。今回は『植物忌』(星野智幸著、朝日新聞出版 1760円・税込み)の書評を送る。
* * *
子どものころ見た映画で「マタンゴ」というSFホラーがあった。数人の男女を乗せたヨットが遭難して、巨大なキノコだらけの無人島に漂着する。空腹に耐えられずそのキノコを食べた仲間が、次々とキノコに変身していくという内容である。「総天然色」映画の毒々しい色彩のマタンゴは、しばらくの間うなされるくらい気味悪かった。それでいて、心の奥底にはちょっぴり自分もそうなってみたいという変身願望が潜んでいたような気がする。本書を読みながらこの昔の映画をふと思い出したのは、そのときに覚えた変身願望が甦ったからだろうか。
11作品を収めた本書では、さまざまな架空の植物が出てくる。そして植物にとりつかれた人間が、ついには植物化を遂げるヴィジョンが進行していくのだ。たとえば「スキン・プランツ」は、植物を頭皮に植える技術が生まれ、新しいファッションとして流行する話から始まる。ところが花が咲くと当人が死ぬことが判明する。慌てて品種改良されたものの生殖能力を失うらしい。にもかかわらず頭にいろいろな花を咲かせる人が溢れ、人間の世は花園のようになる。人類が滅んでも良いという暗黙の覚悟をしたことになる。ぞっとするホラーのようでもあり、妖しい誘惑力をも秘めている。
一方「ひとがたそう」では、植物の人類破壊計画を阻もうとする「ネオ・ガーディナー」なるチームが登場する。しかしマメ科の人形草に仲間がいつのまにか取り込まれている。どうして植物の仲間になったのかを尋ねると、「人間が生き延びるため」だと答えるのである。草になれたほうが幸せかもと思いながらも「まだ人間でいたい」と言い切る2人が残る。しかしラストの言葉は次のようだ。
「私たちはまだ若かった。」
これもショート・ホラーみたいだが、人類が全て植物になり代わったら、さぞ地球は美しい星になることだろう。私たちはその可能性にまだ気づいていないだけなのかもしれない。そんな未来の視点から本書は書かれている。
本書には「世界的な植物の殿堂」と謳われる「からしや」が共通してあちこちに出てくる。最初は大きなグリーン・ショップのようなイメージだったが、じつは先端的な研究所であり、次第に世界を変革する巨大企業に成長していく。「からしや」の名前の由来は、「あまりの種」と題した「あとがき」に書かれているが、これもまんまと作品の一部になっている。いわば本書は「からしや」サーガ(物語群)なのだ。植物への倒錯的ともいえる愛に加えて、ナンセンス・ギャグのような軽やかなノリと、とめどない奔放な想像力、そして平然とモラルの限界を超えてしまう語りの力が渾然と結集した作品群である。
私のお気に入りは「ディア・プルーデンス」。もとは「からしや」のレジ打ちのおばさんだったが、今は青虫の「ぼく」が、隣家の二階の部屋に閉じこもっている少女に懸命にコンタクトを取って外へ出てくるよう促す物語だ。タイトルはビートルズの曲名。彼らが仲間とインドに渡って瞑想にハマっていた頃に、宿舎の部屋から出てこないミア・ファーローの妹、プルーデンス嬢に呼びかけたジョン・レノンの曲である。それと「はらぺこあおむし」が合体したようなチャーミングな作品だ。
我が家のベランダにも植物が十数鉢ある。朝夕水遣りするのが私の仕事で、メンテナンスが妻の仕事である。そこに本書に出てくるミスマッチな返答をするランの新種「喋らん」なんか加えて育ててみたい。コロナ禍で屋内に閉塞する私たちに、本書は植物という未来の夢を届けてくれた。ヒトから出ていきなさいと囁いてくれた。
※週刊朝日 2021年7月9日号

























