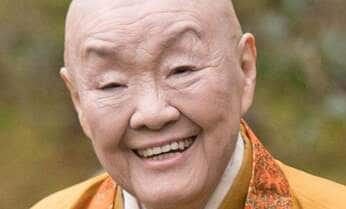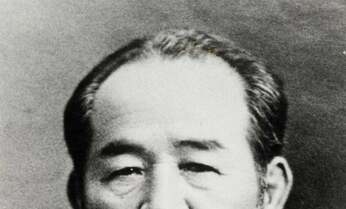
妻・千代をパンデミックで失った渋沢栄一に学ぶ逆境の心構え 玄孫が読み解く
481社の創業にたずさわったという渋沢栄一(渋沢栄一記念館提供)
渋沢健さん(提供)
「できる」「できない」「やりたい」「やりたくない」の軸(筆者提供)
NHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公で「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一。渋沢家五代目の渋沢健氏が衝撃を受けたご先祖様の言葉、代々伝わる家訓を綴ります。
* * *
人類は数多くの戦争を繰り返してきて局部的な破壊や悲劇は大きかったものの、新型コロナウイルス感染症のパンデミックほど広範的なスケールで世界の人々の日常生活を脅かした危機は前代未聞です。
その中、特に犠牲になったのは社会の高齢者や貧困弱者という傾向があり、経済界では大企業と比べると中小・零細企業の資金繰りが厳しい状況に陥りました。
先進国ではワクチン接種が広まって重傷者・死者は減少している昨今でも、途上国・新興国など世の中の多くが未だに逆境に立たされています。
およそ500社の会社を設立したと言われる渋沢栄一ですが、全てが順風の人生ではなく多くの逆風も体験しています。栄一の時代にはコレラやスペイン風邪というパンデミックが世界に広まっていて、前妻の千代をコレラで失っています。
ただ、公私の逆境に屈することなく、多くの実績を後世に残した栄一の言葉に我々は耳を傾けるべきではないでしょうか。書籍『論語と算盤』の「大丈夫の試金石」という説で栄一は「自然的逆境」に立った場合に以下の心構えが大切であると示しています。
・「足るを知る」-これは、何を失ったことにより、何が有るかに気づいて感謝することでありましょう。
・「分を守る」-やるべきことをきちんとやって身を守ることです。例えば、うがい、手洗い、マスク着用、「密閉」「密集」「密接」を避ける等です。もちろん、ワクチン接種も、この類に入ります。
・「天命であるから仕方ない」-ジタバタするより心を平静に保ち、場合によっては思い切って断念する。
つまり、自然的逆境のときには正しく恐れることが大事であるということになります。 ただ、新型コロナウイルスは自然的な存在かもしれませんが、コロナ禍は「人為的な」側面もあります。
人と人の間、あるいは人と社会の間で生じる人為的な逆境の場合、「自分からこうしたい、ああしたいと奮励さえすれば、大概はその意のごとくになるものである」という栄一は提唱しています。
一般的に我々は「できる」「できない」という軸で物事を判断する傾向があります。
「できない」あるいは「できていない」という否定を判断基準にすると幸福な生活を送ることができない、と渋沢栄一は指摘します。
「しかるに多くの人は自ら幸福なる運命を招こうとはせず、かえって手前の方からほとんど故意にねじけた人となって逆境を招くようなことをしてしまう。それでは順境に立ちたい、幸福な生活を送りたいとて、それを得られるはずがないではないか」
だから栄一は「自分からこうしたい、ああしたい」、つまり、自分が「やりたい」「やりたくない」の軸も大事であると唱えているのです。
では、横軸に「できる・できない」、縦軸に「やりたい・やりたくない」の四象限で整理してみましょう。
この場合、ベストポジションは当然ながら、右上の「やりたい」「できる」になります。
一方、「できない」ところですが、左下の「やりたくない」ポジションは順位がそれほど高いところではなく、場合によっては整理して捨てても良いところです。
問題は明らかに右下の「できる」のに「やりたくない」ポジションです。勉強ができるのにやりたくない子供。仕事ができるのにやりたくない部下、あるいは上司。これらは改善しなければ状態です。
しかし、我々はほとんどの場合、左上のポジションいるのではないでしょうか。「やりたい」ことはたくさんあります。
ただ、お金がないから「できない」。
時間がないから「できない」。
制限があるから「できない」。
経験がないから「できない」。
我々は、できないことばかりです。
このポジションにいた場合に「できる」「できない」の軸で判断すると、我々はできないところにいます。だから、元々は「やりたい」ことができないので、あきらめて「やりたくない」へと沈んでしまうかもしれません。
子供の頃、プロ野球選手や宇宙飛行士になりたいという人もいたでしょうし、歌手やケーキ屋さんという人もいたでしょう。でも、実際には子供の頃の夢を追いかけて、本当にそうなった人というのは、極めてまれです。「できる」「できない」という軸で自分の人生を考えたので、どこかで挫折してしまったからです。
しかし、同じ左上のポジションの場合、「やりたい」「やりたくない」軸で考えると我々はやりたいところにいます。栄一がいう「こうしたい、ああしたい」です。このベクトルを立てていれば、すぐに「できる」訳ではありません。前後左右するかもしれません。しかし、いずれ「できる」方へとシフトする可能性が残ります。
本当は、誰でもやりたいことがいっぱいある。けれども、いろいろな言い訳を自分たちに言い聞かせてしまいます。失敗するのが嫌だからです。
もちろん、「できる」「できない」の軸も大事なのです。でも、ここばかりを見ていると、自分が本来持っているポテンシャルを発揮できないまま、人生が過ぎてしまうことにもなりかねません。それではあまりにももったいない。
前回の本コラムでご紹介した大谷翔平選手に聞いてみたいことがあります。「論語と算盤」の「大丈夫の試金石」を読んで何を感じたかと。
恐らく、自分も渋沢栄一が提唱していたように「こうしたい、ああしたい」という人生のベクトルをずっと立てていた、と答えるのではないでしょうか。
我々はもちろん、大谷翔平のような野球はできません。渋沢栄一のように500社ぐらいの会社を設立することもできない。ただ「こうしたい、ああしたい」というベクトルを、これを立てておくことは誰でもできることであります。(渋沢健)
◆しぶさわ・けん シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、コモンズ投信株式会社取締役会長。経済同友会幹事、UNDP SDG Impact 企画運営委員会委員、東京大学総長室アドバイザー、成蹊大学客員教授、等。渋沢栄一の玄孫。幼少期から大学卒業まで米国育ち、40歳に独立したときに栄一の思想と出会う。近著は「SDGs投資」(朝日新聞出版)