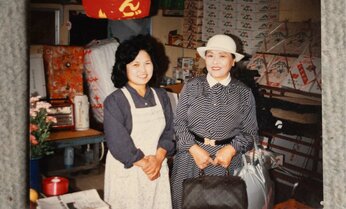進化する動物、しない動物がいるのはなぜ? 動物学者・今泉忠明先生が子どもたちに伝える「生き物のふしぎ」
(写真はイメージ/GettyImages)
進化する動物、しない動物の違いは? AERA with Kids編集部に子どもたちや保護者から集まった動物・生き物の疑問について、『ざんねんないきもの事典』(高橋書店)監修でおなじみの動物学者・今泉忠明先生に聞きました。
北極のシロクマに元気でいてもらうには?
Q.北極のシロクマが痩せている写真をお母さんに見せてもらいました。 どうしたら元気でいてもらえますか?
A.北極のホッキョクグマが痩せている理由は、主に地球温暖化による海氷の減少が影響しています。ホッキョクグマは海氷の上を歩き、アザラシを狩って食べる生活を送っていますが、海氷が減るとアザラシにそっと忍び寄ることが難しくなり、十分な食べ物を得られなくなっています。この状況を改善するためには、温暖化を防ぐための行動が必要です。ホッキョクグマや環境を守るための具体的な行動を紹介しましょう。
ホッキョクグマを守るための行動は、一つには家庭などでエネルギーを節約し、温暖化を防ぐための取り組みを行うことです。LED照明の使用やエアコンの効率的な利用などが叫ばれているのもそのためです。
それと太陽光や風力などの再生可能エネルギーを積極的に利用することです。
また環境保護活動やイベントに参加したり、ホッキョクグマやその生息地を守るための意識を高めたりすることも大切です。食料や品物を買うときは本当に必要かどうかをよく見極め廃棄物を減らすなど、日常生活で持続可能な選択を行うことが必要です。これらの行動を通じて、ホッキョクグマや地球全体の環境を守ることができます。
猛毒をもったアリ、クモが増えてきていない?
Q.ここ数年、日本にはいないはずの猛毒をもったアリ、クモなどが増えてきていると思います。 以前なら子どもたちにどんどん捕まえたり、触ったりして観察させたいと思っていましたが、知識がない為、何かあってはと心配になります。敏感になりすぎでしょうか?
A.たしかに日本では、以前は見られなかった猛毒を持つアリやクモが増えてきていることが懸念されています。ヒアリとセアカゴケグモが有名ですね。
ヒアリは中南米原産の外来アリで、日本では物流のグローバル化に伴い持ち込まれています。2017年から2019年までに15都道府県で48件の確認事例があり、特に港湾地域で多く発見されています。ヒアリは非常に攻撃的で、刺されると皮膚の炎症を引き起こします。
特に注意しなければいけないのはアレルギーをもつ子どもたちです。その場合はアナフィラキシーショックを引き起こすこともあります。
セアカゴケグモは1995年に大阪府で初めて発見され、現在は全国的に分布しています。このクモは毒を持ち、かまれると軽い痛みから始まり、腹痛や胸痛を引き起こすことがあります。セアカゴケグモは攻撃的ではなく、触ると咬まれることがあるので、素手で触らないように注意が必要です。軍手などを着用して作業することが推奨されます。
子どもたちが触れる可能性がある場合、安全を最優先することが重要で、次いで知識を深めることが大切です。安全に観察や学習ができれば恐れることも少なくなるでしょう。クモやアリなど小さなものを拡大しないとよく見えない場合が多いですが、透明なガラス瓶あるいはプラスチック容器で蓋をするようにして捕まえると手で触れないですみます。そして虫眼鏡などでじっくり観察すると良いです。
なぜ動物の心臓の速さはそれぞれ違う?
Q.なぜ、動物たちの心臓の速さは、それぞれ違うのですか?象はネズミよりも遅い?(小3、タク)
A.動物たちの心臓の速さは体の大きさによって異なります。それは主にその体のサイズや代謝速度に由来するからで、一般的に、体が小さい動物ほど心拍数が高く、代謝が速い傾向があります。例えば、ハツカネズミの心拍数は1分間に600〜700回と非常に速いです。これは、エネルギーを効率的に消費するために必要な代謝速度が高いためです。一方、体の大きな動物は代謝が低く、心拍数も遅いです。例えば、ゾウの心拍数は1分間に約20〜30回と非常に遅いです。この低代謝率により、体への負荷が少なく、細胞のダメージも少なくなるため、長寿の傾向があります。
進化する動物、しない動物の違いは
Q.進化する動物としない動物は、なんでいるのですか?
A.進化する動物としない動物がいるのは、進化の条件と環境への適応が異なるためです。進化は、生物集団の遺伝的な特徴が世代を経て変化する現象であり、一般に、集団内に特徴の異なる個体が存在し、この特徴の違いが遺伝子の違いに起因し、特徴の違いに応じて生存率や繁殖率が異なると進化が起こりやすいと考えらます。
気候変動のような急速な環境変化に対して、生物は順応、分布域の変化、進化のいずれかで対応する必要があり、これらの対応がうまくいかない場合、絶滅に至る可能性があります。
一方で、シーラカンスやカブトガニのように、何億年も姿を変えずに生き残っている「生きた化石」と呼ばれる動物もいます。これらの動物は、環境が大きく変化しなかった深海などの特定の環境に適応していたから、進化の必要性がなかったと考えられています. また、大量絶滅期を生き残った種は、その時代の環境に適応していたため、進化の速度が遅かったり、止まったりする場合があります。
生物が進化するかどうかは、遺伝的な多様性、環境の変化、自然選択の圧力が複雑に絡み合って決まります。
なぜオスは派手?
Q.どうしてオスのほうがだいたい派手なんですか?
A.オスの生物が派手な理由は、主に性淘汰(せいとうた)と呼ばれる進化が原因です。性淘汰は、異性を引き付けたり、同性を打ち負かしたりするために進化した特徴を指します。
繁殖期に少しでもほかのオスよりも派手な色彩や形状を持つオスがメスに選ばれると、これにより、オスがより派手になっていく競争が始まります。メスは自分に最適な遺伝子を持つオスを選びやすくなるから、派手さは目印としてメスには好都合です。オス同士の競争においても、目立つ特徴は重要です。シカの角やクワガタの大顎は、他のオスを打ち負かすための武器として機能するからです。
オスの派手さは主に異性を引き付けるための性淘汰によるものなのですが、例外もいろいろ存在しますから、まだ私たちにはわからない力がオスを派手にしているのでしょうね。
※1月に実施した「AERA with Kidsフェスタ2025」でお答えできなかった方の質問・回答をご紹介しました。
〇今泉忠明(いまいずみ・ただあき)/動物学者。東京水産大学(現在の東京海洋大学)卒業後、国立科学博物館で哺乳類の分類学・生態学を学ぶ。生態調査の経験が豊富。監修の『ざんねんないきもの事典』(高橋書店)はミリオンセラー。