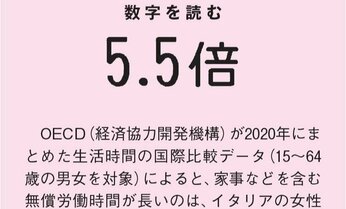TCB中園医師が”久留米市民初のエベレスト登頂成功”を橋本副市長へご報告。久留米市の子ども達にチャレンジの精神を伝えてまいります。
【進化を文化に】TCBと中園医師は世界一を目指して挑戦を続けます
- TCB東京中央美容外科
日本全国に105院(2025年7月現在)を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(理事長:寺西 宏王、以下「TCB」)の中園秀樹医師は7月10日(木)、久留米市の橋本政孝副市長へ表敬訪問し、久留米市民として初めて(※TCB調べ)エベレスト登頂に成功したことをご報告しました。
左:TCB 中園医師 右:久留米市 橋本副市長
2025年5月14日(水)6時55分エベレスト山頂(標高8848m)にて(左が中園医師)
表敬訪問では冒頭、中園医師より久留米市で生まれてからの生い立ちについて語られ、「1978年に久留米市で生まれ、父親の仕事の都合で札幌に移った後、2000年に久留米大学医学部に入学を機に久留米に戻ってきました。今は札幌よりも久留米の方が長くなりました。久留米大学ではワンダーフォーゲル部に入部し、北アルプスなどでトレーニングをしていました。そのまま久留米大学の耳鼻科で働いていたのですが、エベレストを本格的に挑戦しようと退職しようとしたところ、大学から休職を提案され「山休(さんきゅう)」と位置づけキリマンジャロに登ったりしていました。世界で8番目に高いマナスルに登った時には久留米大の旗を持って行って頂上で掲げました。」と写真パネルを用いて説明がなされました。
続いて今回のエベレスト挑戦について話が及び、「今はTCBという美容クリニックで勤務していますが、エベレスト挑戦のために退職を申し出たところ、休職を会社から提案いただきサポートも受けながらの挑戦でした。3月にネパールに向けて出発し、2週間くらい徐々に高度を上げながらベースキャンプを目指しトレッキングをして高度順応をしました。4月20日が誕生日だったので、ベースキャンプでお祝いをしてもらいました。ベースキャンプからキャンプ1~4まで徐々に登っていくのですが、ベースキャンプからキャンプ1が雪崩やクレバスがあって危険で、日中にいくと危ないので夜中にヘッドライトを付けていきました。キャンプ3からは酸素ボンベが必要で、寝る時も24時間酸素ボンベを付けて生活していました。山頂付近はもう雲の上で、空も見たことないくらいの濃い青でした。神々しい世界である一方、生き物のいないデスゾーンで少し怖い思いもしました。別の隊で同じ日に2人亡くなっていて、死が隣にある世界でした。そうしたところを経て5月14日の朝6時55分に登頂することができました。山頂から降りてくるときに指が凍傷になってしまって、ヘリで緊急搬送されました。今は母校の久留米大学病院の形成外科で治療してもらっています。指のことがあるので無事と言い切って良いのかは分かりませんが、久留米に戻ってくることができました。」と、今回の挑戦の一部始終が語られました。
橋本副市長からは、「世界最高峰のエベレスト登頂成功おめでとうございます。登る過程に大変な困難を伴いながらも、初志貫徹で達成されたことにただただ感動しております。日々すごい精進されてきたのだと思います。今回の経験を是非機会があれば久留米の子ども達に伝えて欲しいです。挑戦することの大切さと、そのための努力の大切さとか、またどこかの場面で叶えば子ども達にとって有意義なことになると思います。エベレストともなると一人では登れないでしょうから、大学や会社のバックアップがあって支えてもらいながら登ったという、チームで成し遂げたこともまたひとしおと感じます。」など労いのお言葉を頂戴しました。
・メディアでの紹介今回の表敬訪問の模様を各メディアにも取り上げていただきました。
■KBC九州朝日放送
『久留米市出身の医師がエベレスト登頂に成功 地元市役所を表敬訪問』
https://kbc.co.jp/news/article.php?id=15588357&ymd=2025-07-10
『久留米市出身のお医者さん エベレスト登頂を市に報告 「次は家族と一緒に…」』
https://kbc.co.jp/news/article.php?id=15591211&ymd=2025-07-10
■TNCテレビ西日本
『久留米市の46歳医師がエベレスト登頂に成功 市民として初 久留米市役所に報告 福岡』
https://news.tnc.co.jp/news/articles/NID2025071026292
・表敬訪問概要■日時:2025年7月10日(木) 10:00~10:20(※本イベントは終了しています)
■場所:久留米市役所 8F 市長対応室
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
■参加者:
・久留米市 橋本政孝 副市長
・TCB 中園秀樹 医師
■内容:
・中園医師よりエベレスト登頂のご報告
・橋本副市長よりご挨拶
・ご歓談
・記念撮影
・中園医師と久留米市1978年 久留米市生まれ
2006年 久留米大学医学部 卒業
2008年 久留米大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2011年 聖マリア病院 耳鼻いんこう科
2017年 久留米大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
現在はエベレスト登頂で負った凍傷の治療のため、久留米市内の自宅で療養中
詳しい経歴
母校の久留米大学 内村直尚学長へ登頂成功報告
・エベレスト挑戦概要<登頂日時>
2025年5月14日(水)6時55分(現地時間)
<スケジュール>
3月26日(水):ネパールへ向け日本を出発
3月27日(木)~3月30日(日):カトマンズで顔合わせや準備を行いルクラに移動
3月31日(月):ルクラからエベレスト街道のトレッキング開始
4月1日(火)~4月7日(月):ナムチェバザール、ペンボチェ、ディンボチェ、ゴラクシェップなどを巡りトレッキング
4月8日(火):エベレストベースキャンプ(標高5364m)に到着
4月10日(木)~4月11日(金):ロブチェピーク(標高6118m)で高度順応
4月26日(土)~4月30日(水):キャンプ2(標高6400m)で高度順応
5月9日(金):ベースキャンプを出発
5月13日(火):22時頃にキャンプ4(標高7900m)を出発、山頂アタックへ
5月14日(水):6時55分エベレスト登頂(標高8848m)
5月15日(木):キャンプ4からキャンプ2まで下山、ベースキャンプまでヘリ移動
<登頂サポート>
・渡邊直子さん(日本人女性初8000m峰14座制覇・「クレイジージャーニー」「情熱大陸」出演)
https://naoko-watanabe.jp/
左:TCB 中園医師 右:渡邊直子さん
・中園医師インタビュー帰国して間もない中園医師に話を聞きました。
Q.エベレスト登頂した時の気持ちは?
頂上では感動して泣くかなと期待していたが、実際は目の前のことに必死で、自分の体調管理や酸素ボンベの残量のことに集中していたため感動して泣くということは無かった。しかし、ここが世界で一番高いところで、ここより高いところは世界に存在しないんだ、という高揚感があった。
登っている最中から感じたが、エベレストは神々しい世界。周りに生命が全くいないデスゾーンで、人が立ち入ってはいけない場所なんじゃないかと、生き物がいてはいけないところであると思ったときに恐怖を感じ無事に帰れるか心配だった。神々しい世界に自分が入り込んでしまったな、と。
Q.困難だったこと、トラブルは?
日本人の山仲間数人と一緒に今回は登る予定だったが、ベースキャンプにたどり着く前に低酸素血症などで一人また一人とリタイアしてしまい、結局自分一人だけでの挑戦になってしまった。
アタック中は3回くらい死ぬかもしれないと思った。
一番最初は山頂で。いつも山登りの時は体力を60%残して登頂し、もう一度登れるくらいの余力をもっていくようにしているが、今回は40%くらいしか残っておらず、無事に降りられないかもしれないという不安があった。リタイアしてもバスで回収されるトレイルランニングの大会と違って、エベレストは自分でキャンプ地まで降りられないことは即ち死を意味するので、山頂で死ぬかもしれないと感じた。
下山中も2回ほど急に眠気が来て、寝てしまえば楽になれるが、それも寝る=死を意味するので、キャンプ4までたどり着いたときは心底ホッとして生きている実感が湧いた。
また、渡邊直子さんとロブチェピークでの高度順応スケジュールについて喧嘩になったが、それを乗り越えてより一層の信頼関係が出来たことでマネジメントを全面的にお任せでき、成功につながった。
Q.帰国して体調やコンディションは?
右手の指が黒く変色するくらいの凍傷をしてしまった。
何で右手だけかと考えたが、山頂などで写真を撮るために指を露出していたのが原因かなと。ほんの数分だったと思うが、マイナス40℃で風が強いところなので、数分であろうと素手を晒していたのが原因だと思う。
下山している途中でなにか感覚がおかしいなと思って見てみたら指がちょっと白くなっていて、これはまずい、凍傷だと思ったが、時々チェックするために手袋を外していた。すると運悪くその時に突風で手袋が飛んでいってしまい、そのまま素手で行ったら右手は完全にダメになっていたが、予備の薄い手袋を二重にするなどして対応しなんとか今の状態で済んだ。
ただ、指を無くすと分かっている状態で時が戻ったとしても、またエベレストに登ると思うし、命をかける価値があると思っている、それくらいエベレストは人生の中で重要なチャレンジだった。
Q.出発前にアルピニストの野口健さんから応援メッセージとアドバイスが送られたが、現地でどのように役立ったか?
(参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000034186.html)
野口健さんからは、キャンプ4でいかに仮眠を取るかが大事というアドバイスを頂いて、そこを意識して必ず寝ようと思っていた。キャンプ4を出発して帰ってくるまで20時間くらい歩いていたが、仮眠せずに歩いていたら途中で力尽きていたと思う。
風が強く、予定より出発が遅れたこともあり、キャンプ4でしっかり仮眠をとれたのが今回無事に帰ってこられたポイントと思う。
Q.壮行会では「チャレンジする人が一人でも多く増えてくれれば良いなと思っている」という発言があったが、チャレンジを終えて改めてどう思うか?
世界一のエベレストに行くためにはすごい準備が必要なんでしょうとか、特殊な才能が必要なんでしょうとか、そういう風に思われるかもしれないが、僕も毎日毎日10時間トレーニングするとかそんなことはなく、普段していることと言ったらなるべくエレベーターを使わずに階段で登るだとか、暇な時間があったら朝のジョギングとか、それくらいのことをしている程度。特別なトレーニングは実はそこまであまりしていない。そういう意味では普通で才能があるわけでもない、体調も体格も大谷翔平選手みたいなあんなムキムキというわけでもない、僕でもチャレンジする気持ちとかやってみようという気持ちがまず大事。それをコツコツ続けることで世界一高いエベレストも、世界一過酷なサハラマラソンもクリアできた。
何事も自分は特殊な能力があるわけじゃないからとか、恵まれているわけじゃないからと言うわけでもなくて、まずはやってみてそれでダメだったらダメなところとか足りないところを、トレーニングしたりとか人に助けてもらったりとか補っていけば、どんなところでも道は開けるんじゃないか。チャレンジのハードルをまずは下げてみる。
サハラ砂漠マラソンでよく言われるのが、泳げるようになってからプールに行く人はいない。泳げない状態からプールに行って、だんだん泳げるようになる。最初から無理って思わずに、できないところからみんなできるようになったりすることも多いので、まずはチャレンジしてみる、ということをやってもらいたい。
Q.TCBへのメッセージ
TCBを一旦辞めてからエベレストチャレンジをして、無事に帰って来れたら仕事に戻ろうと思っていた。自分勝手なことで会社にも迷惑かけてしまうので退職しなければと思っていたが、会社としても応援したいと言っていただき、スポンサーについてもらって手厚いサポートの中でチャレンジできたのは本当に良かった。
今回は形に残る結果を出せたのも良かった。こういうチャンスをもらえる人というのは本当に少ないと思うので、TCBには非常に感謝している。ありがとうございました。
TCBより中園医師へ、エベレスト登頂チャレンジ成功の特別報酬1000万円を支給
Q.今後について
人生でやりたいことをまとめた3大バケットリストがある。
1つ目は「世界一過酷なサハラ砂漠マラソン完走」、2つ目は「世界一高いエベレスト登頂」、3つ目は「家族と一緒に世界一周」。
そのうち2つは達成したので、残りは3つ目の家族と世界一周だが、ファーストクラスでまわるのか、ヒッチハイクでまわるのか、いろんなスタイルが考えられるが、とにかく人と感情を共有しながら旅を楽しみたい。
でも実は、その共有するパートナーを探すのがエベレストに登るより一番難しいのかも…(笑)
中園 秀樹 Hideki Nakazono
生年月日:1978年4月20日生まれ
出身地:久留米市生まれ、札幌市育ち
趣味:サウナ・Netflix
得意施術:糸リフト、目の下のクマ・たるみ取り
活動歴:
2016年 キリマンジャロ(標高5895m)登頂
2019年 マナスル(標高8163m)登頂
2021年 エベレスト(標高8848m)にチャレンジするもコロナウイルスの影響によりC3(標高約7300m)で断念
2023年 サハラマラソン(約250km)完走
2025年 エベレスト(標高8848m)登頂
本人より:僕は医者で冒険家でチャレンジャーです。より多くの方とこのチャレンジを共有できたらと思います。僕がチャレンジすることで何かを感じてもらえたら嬉しいです。
中園医師と登山との出会いは17歳の時、学校行事で北海道東川町の道内最高峰・旭岳(標高2291メートル)に登ったときでした。登頂した時の達成感に魅了されたことで登山にのめりこみ、世界中の名峰を攻略してきました。
2021年に初めてエベレストに挑戦したものの、山頂へのアタック待機中にベースキャンプでコロナウイルスが蔓延し、病院の酸素ボンベが不足したために涙を飲みながら撤退した過去を持ちます。
コロナの影響も落ち着いた今、中園医師はTCBのサポートを受け、高校生の時に抱いた約30年がかりの夢「エベレスト登頂」を見事実現させました。
・TCBクリニック概要
TCB東京中央美容外科は日本全国に105院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。
クリニック名:TCB東京中央美容外科
理事長:寺西 宏王
クリニック数:105院(2025年7月時点)
診療時間:9:00~19:00
(9:00~10:00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります)
休診日:院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】
オフィシャルサイト:https://aoki-tsuyoshi.com/
■本件に関するお問い合わせ
広報担当 石川 将之(一般社団法人メディカルアライアンス)
mail:ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp