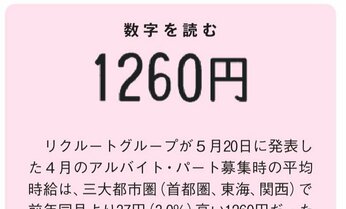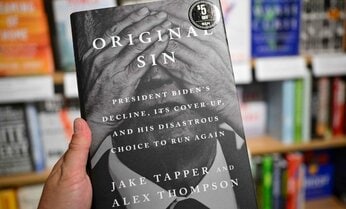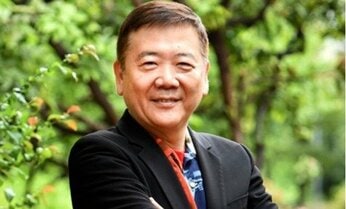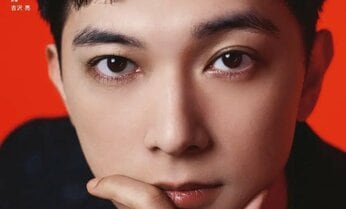「S&P500で配当も欲しい」人のETFベスト10/米国株の東証ETFまとめ!【新NISA応援】
東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 調査役の富田貴之〈とみた・たかゆき〉さん(撮影・戸嶋日菜乃)
長期投資で威力を発揮する「複利効果」。得られた利益を再投資することで元本を増やせば効率的に運用できる。だが、効率はさておき「配当が欲しい」というニーズも根強くある。S&P500への投資で配当をもらうには?【本記事はアエラ増刊「AERA Money 2025夏号」から抜粋しています】
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」をはじめ、新NISAのつみたて投資枠で選べるインデックス型投資信託はほとんどが分配金を抑制する(出さない)タイプだ。
投資信託の購入者に分配金を払い出さず、ファンドの中で自動的に再投資をしてくれている。
新NISAの非課税投資枠をきっちり使いながら効率運用ができるので、基本は分配金抑制タイプの投資信託を選ぼう。
ETFは分配金が出る
S&P500の組み入れ500銘柄からは、すべてではないが配当が出ている。
米国企業の間では四半期ごとの配当が主流だ。
個別株を保有している場合、配当は直接受け取ることになる。
投資信託の場合は、得られた配当を分配金として購入者(投資家)に支払うケースもあれば、ファンド内で再投資に回すケースもある。その判断は運用側に任されている。
S&P500をはじめとする米国株の投資でも配当が欲しい––––、そんなときは東証に上場しているETF(上場投資信託)を。
「東証」というと日本株のETFしかなさそうだが(実際、日本株ETFのほうが数は多いが)、S&P500に連動するタイプや、米国株の高配当株を組み入れたタイプもある。
主な10本を表にまとめた(次ページ上の表参照)。安いものは数千円から、高くても数万円で買える。信託報酬と呼ばれるコストも高くない。
S&P500のETFで一番人気は純資産総額1168.9億円(2025年2月28日現在)の「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」。信託報酬0.066%(年率、税込み、上限。2025年3月26日現在/以下同)と最安で、6000円台から買える。
最低投資金額が一番低いのは「iFree ETF S&P 500(為替ヘッジなし)」信託報酬0.077%。1500円前後から投資OKだ。
ETFの普及に邁進(まいしん)する、東京証券取引所金融リテラシーサポート部調査役の富田貴之さんに取材した。
本記事が丸ごと読める「AERA Money 2025夏号」はこちら!
商品価格¥1,320 詳細はこちら ※価格などの情報は、原稿執筆時点のものになるため、最新価格や在庫情報等は、Amazonサイト上でご確認ください。
「制度上、東証ETFは組み入れ銘柄から得られた配当は分配金としてすべて吐き出す(当該ETFの購入者に支払う)のが原則となっています。
分配金利回りはS&P500に連動するETFで現状1%前後です。新NISAでは成長投資枠で買い付けられます。
特定口座などの課税口座で分配金を受け取ると20.315%の税金が差し引かれますが、新NISAは分配金も非課税です」
とはいえ分配金の分だけ元本は目減りするため(分配落ち)、複利効果という意味では分配金抑制タイプの投資信託に比べて不利だ。
ETFではなく、投資信託の中で分配金が再投資される際、20.315%の税金は引かれない。
ただ、S&P500のように米国株から配当が出た場合、米国分の10%の税金は引かれたうえで再投資に回ることになっている。
「特定口座で買ったETFの場合、自動的に二重課税にならないように調整(米国分の課税は実質的に免除)されます。
新NISAではもともと分配金への課税がないため二重課税の調整はありません」
資産を増やすときに効率性は重視したいが、「他のポイント」に目を向ける投資家もいる。
投資で億超えの財を築き、2020年の秋に47歳で約25年間勤務した会社を早期退職した桶井道(おけいどん)さんは、自称「配当金大好きマン」だ。
2024年の1年間で受け取った分配金と配当金の総額は税込み323万円、手取りは249万円だった。
含み益237万円超
新NISAのつみたて投資枠では「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に毎月10万円ずつ投資している。
ETFでは「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」がお気に入り。
2025年3月19日現在のiシェアーズETFの評価額は436万8960円、含み益は237万4560円だという。
「iシェアーズのS&P 500 ETFを選んだのは、投資した当時から信託報酬が他より安く、純資産総額も大きめだったからです。
他のETFもたいていそうですが、二重課税調整制度の対象銘柄で、特定口座を通じて購入すれば確定申告で外国税額控除を行う必要がないのもラクでした。
世界最大の運用会社であるブラックロックが運用しているという信用力、ブランド力、安心感もあります。
本当はつみたて投資枠でもETFを買いたいぐらい(笑)」
この記事の完全版が読めるAERA増刊「AERA Money 2025夏号」が好評発売中です! Amazonや楽天ブックスなどのネット書店では「アエラマネー」で検索して、この表紙を探してみてください!(編集部より)
桶井道さんはなぜETFが好きなのだろう。
「分配金が欲しいからです。老後は個別株の配当金やETFの分配金を生活費にする予定です。
今は分配金を使ってショッピングのようにETFや個別株に再投資をしています。
早期退職していることもあり、分配金の入金の日は給料日のような気持ちになります」
桶井道さんは、勝手に振り込まれるところが好きなのだという。
「分配金や配当金は定期的に、自動的に振り込まれるのでラクです。価格が下がっても、分配金があると心の支えになります。
これまで増やしたお金を老後に使うとき、ちょうど暴落中だと取り崩しにくいと思うんです。
その点、分配金や配当金は自動入金なので」
運用効率だけにフォーカスすれば、ETFよりも投資信託のほうが優れていることは、桶井道さんも承知している。それを前提としたうえで、次のように述べる。
「私は投資を『効率=数字』だけでは捉えていません。つらくない投資、楽しい投資をすることこそ、長く継続していくうえで大切だと思っています。
通常の投資信託を、必要なときに必要なだけ取り崩せる方もいらっしゃると思いますので、そういう方はETFでなくても全然問題ないかと」
分配金をもらうのがうれしい、新しい銘柄を買うのが好き。生粋の「投資好き」であった。
地球儀投資
ちなみに、2025年2月下旬から3月初旬にかけて米国株が大きく下げた局面でも、桶井道さんは資産を増やした。
2月末時点の総資産額1億8451万円、3月19日(取材日)の総資産額1億8788万円。S&P500だけでなく、多国籍の個別株やETFに「地球儀投資」をしているらしい。
新NISAではS&P500とならんで全世界株式も人気だが、彼の言う地球儀投資は「桶井道式オルカン」のようなものだろう。
取材・文/中島晶子(AERA編集部)、大西洋平
富田貴之(とみた・たかゆき)東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 調査役。大阪大学経済学部を卒業後、東証へ入社。セミナー講師や「東証マネ部!」運営チームとして情報提供。数字に強い
桶井 道(おけいどん)個人投資家、物書き。投資歴26年。100銘柄以上の個別株、ETFを保有。最新刊は『時をかける貯金ゼロおじさん』(KADOKAWA)
編集/綾小路麗香、伊藤忍
『AERA Money 2025夏号』から抜粋