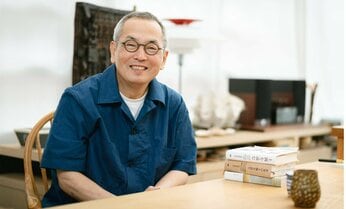【マクアケ開始2日で応援総額3400万円を突破!】ハンディタイプ高圧洗浄機にて歴代ランキング1位を獲得!
【完全ワイヤレス×圧倒的洗浄力】で史上最小かつ強力な「THE HYDRO CLEANER HANDY POWER」
- 谷村実業株式会社
谷村実業株式会社(本社:京都府福知山市、代表取締役社長:谷村 建一郎)が展開する「暮らしを革新する、プロフェッショナル基準。」をブランドコンセプトに掲げた「T-PROFESSIONAL(ティープロフェッショナル)」は、家庭でも外出先でも、電源・水道不要で本格洗浄を実現する「THE HYDRO CLEANER」シリーズから完全ワイヤレスの最新モデル「 HANDY POWER」を2025年7月19日(土)よりMakuakeにて先行販売開始しました。おかげさまで、プロジェクト2日にして3400万円の応援購入をいただき、Makuake高圧洗浄機ランキング1位を獲得したことをお知らせいたします。
一般販売価格は15,000円(税込)のところ、Makuakeでは35%OFFの9,750円でご提供しております。お得なリターンは数に限りがございますので、ご関心持っていただけた方は、お早めにご確認ください。
Makuakeプロジェクトページはこちら
【THE HYDRO CLEANER HANDY POWERとは】高圧洗浄機の概念を覆した、Makuake高圧洗浄機ランキング歴代1位の人気シリーズから登場!圧倒的洗浄力はそのままに、完全ワイヤレスで史上最小コンパクトサイズ
T-PROFESSIONALの中でも「HYDRO CLEANER」シリーズは、従来の高圧洗浄機の課題とされてきた「重い・大きい・コードが邪魔・水道接続が必要・収納に困る」などの問題を解決!洗浄力はプロ級を叶えつつも、軽量化、電源・水道接続不要、収納コンパクトまで叶えた人気シリーズです。
そんな「HYDRO CLEANER」シリーズからプロ級の洗浄力はそのままに完全ワイヤレスで史上最小コンパクト「HANDY POWER」が登場しました。ワイヤレスなので、これまで洗浄しずらかった高所や、狭いスペースでも楽々使用でき、さらに携帯可能のためキャンプ、公園などのアウトドアでの使用や、災害時など水道が使えなくなってしまった時などにも活躍します。
機能面でも、泡洗浄機能や多様な噴射モードを搭載し、ただの小型洗浄機ではないプロフェッショナル品質に仕上げています。
【まさに次世代モデル「THE HYDRO CLEANER HANDY POWER」 製品特長】・「コードレス」だけでなく「完全ワイヤレス」設計で圧倒的な操作性
電源も水道も不要。コードやホースに縛られないため、これまで使用しずらかった狭い場所やキッチン、お風呂場、玄関などの家の中でも外でもどこでも自在に使えます。
・強力洗浄&5つの水流パターン+泡洗浄
用途に合わせて選べる5パターンの噴射+泡洗浄で、車、バイク、ベランダ、玄関タイルなど多用途に対応。 最大2.5MPaの水圧が可能です。
・外出先でも、水道が近くになくてもOK。災害時にも活躍
アウトドアや車中泊の際、家に持ち帰る前に洗浄が可能です。災害などで急に水道が使えなくなった際にも使える次世代モデル
・付属のホースをつければ長時間使用も可能に!
ワイヤレスで使用したい時はペットボトルで気軽に、長時間使用したい時は付属のホースと折りたたみ式バケツに簡単変更が可能です。
【製品概要】・セット内容:本体の他に、泡洗浄のバブルボトル、折りたたみバケツ、ホース、ノズルがついてきます
・一般販売予定:2025年秋ごろを予定
・Makuake特別価格:9,750(税込、35%OFF)
・一般販売価格:15,000(税込)
・MakuakeプロジェクトURL:https://www.makuake.com/project/t-professional5/
「暮らしを革新する、プロフェッショナル基準。」をブランドコンセプトに掲げるT-PROFESSIONALとは?T-PROFESSIONALは、プロフェッショナルの知見とユーザーの声をもとに、プロ品質を日常に取り入れ、暮らしをより快適で便利に進化させることを目指し、高い信頼性、洗練されたデザイン、そして使いやすさを追求し、日々の生活に「HAPPY & SURPRISE」をお届けします。
・T-PROFESSIONALブランドサイト
シリーズ累計1億6000万円※以上の応援購入総額を達成し、多くのユーザーから高評価をいただいた「THE HYDRO CLEANER」とは?従来の高圧洗浄機の課題とされてきた「重い・大きい・コードが邪魔・水道接続が必要・収納に困る」などの問題を解決!洗浄力はプロ級を叶えつつも、軽量化、電源・水道接続不要、収納コンパクトまで叶え、シリーズ累計総額1億6000万円を超えた人気シリーズです。※2024年3月、2025年2月のプロジェクトの応援総額合算
・第1弾 Makuakeプロジェクトページ
・第2弾 Makuakeプロジェクトページ
【谷村実業株式会社とは】1896年創業、129年を超える歴史を持つ総合商社です。鉄鋼、金属製品をメインに取り扱う総合商社として、鉄鋼建材本部、産業機器本部、生活産業本部の3つの事業本部を軸に展開しています。
【会社概要】
会社名:谷村実業株式会社
代表者:代表取締役社長 谷村 建一郎
所在地:〒620-0856 京都府福知山市土師宮町1丁目84番地
設立:創業 明治29年(1896年)12月15日、会社設立 昭和28年(1953年)1月6日
主要取扱商品:
鉄鋼製品、生活用品、建設資材、産業機器、ビル用建材、住宅用建材、機械工具、物流機器
情報機器、冷暖房機器、生活日用品、エクステリア、農業資材、通信販売支援システム、メタル商品
会社HP:http://www.tasscom.net/
谷村実業株式会社
谷村実業株式会社 東京支店
担当:広報部
TEL:03-3479-3151
FAX:03-3479-1351
MAIL:seikatsu@tasscom.net