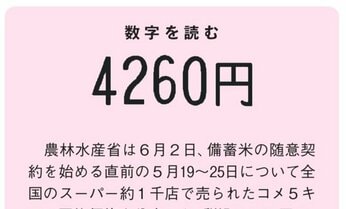新築に引っ越しても気づけばゴチャゴチャ! 片づけたら家族で過ごす時間が増えた
ソファの真ん中に洗濯物がドンと置かれたリビング/ビフォー
5000件に及ぶ片づけ相談の経験と心理学をもとに作り上げたオリジナルメソッドで、汚部屋に悩む女性たちの「片づけの習慣化」をサポートする西崎彩智(にしざき・さち)さん。募集のたびに満員御礼の講座「家庭力アッププロジェクト®」を主宰する彼女が、片づけられない女性たちのヨモヤマ話や奮闘記を交えながら、リバウンドしない片づけの考え方をお伝えします。
* * *
case.97 本当に整えたかったのは家族の現状 夫・子ども3人/教員
片づけに悩んでいる人は、もしかするとこう考えているかもしれません。
「新しい家に引っ越せば、きれいな環境で住めるのに……」
「時間があれば、片づけられるのに……」
でも、たくさんの片づけの実例を見てきた経験上、実際に引っ越しをしても、自由な時間ができても、片づけの悩みが解決するケースは多くありません。散らかってしまう“根本的な問題”を、解決できていないからです。
「新築の家に引っ越したのは、3年前。使いやすいように収納を考えて建てたはずなのに、暮らしているうちにモノの量が増えて、気づいたら家の中は散らかっていました」
こう話してくれるのは、夫と3人の娘と暮らしている理江さん。引っ越す前に住んでいた実家のすぐ近くに家を建てたので、必要なモノがあれば少しずつ移動させていました。そのうち、実家にあるモノを新居で買ってしまったり、実家の荷物を早く運ぶように言われてとりあえず持ち込んだりしていると、家の中はいつの間にかゴチャゴチャになっていました。
さらに理江さんは、小さな頃から部屋が散らかっていても「あとで片づけよう」と、後回しにする性格。いざ片づけると決めたら、休みの日などに長時間かけて終わらせていました。
リビングのソファには洗濯物などがいっぱいで、ゆっくり座ることができません。理江さんが仕事から帰ったときに目に飛び込んでくるのは、脱ぎっぱなしの服や食べっぱなしのゴミ。家では家族にイライラをぶつけていました。
片づけた方がいいとはわかっていても、自分たちの生活に合った片づけ方がわからず、片づける習慣もありません。収納に関する本を買ってみましたが、どこから手をつければいいのか途方に暮れてしまいます。
家族が集まれる場所になりました。キッチンカウンターもスッキリ/アフター
「家族とも、『もっときれいなおうちがいいよね』という話はしていました。でも、みんな具体的にはどうしていいかわからなくて、何もできていませんでした」
そこで理江さんが思い出したのが、家庭力アッププロジェクト®です。1年ほど前に“45日間で家を片づけるプロジェクト”の存在を知り、長期休みのタイミングで申し込もうとしていたものの、そのときは参加しませんでした。調べてみると、また長期休みと重なる時期にプロジェクトが始まります。
「1年前に行動できていなかったから、家は散らかったまま……。今、決断しなかったら一生このままかもと思って、『やるしかない!』と参加を決めました」
片づけ始めると、なぜこんなにモノが多いのかがわかってきました。理江さんは「いいな」と思ったら、必要かどうかを考えもせず、すぐに洋服やアクセサリーなどを買っていました。それは娘たちも同じで、コスメや文房具などが家中いたるところに散乱していたのです。
「ヘアアイロンなんて、いくつも出てきました。そんなに必要ないですよね。気に入ったアイテムを色違いでそろえたくなってしまう“収集癖”みたいなのもあって、モノがどんどん増えていきました」
モノが増える原因がわかると、何かを買うときに「本当に必要かな」と一旦考えるように思考がチェンジ。衝動買いや定期購入を見直し、安易にモノを増やすことをやめると、月に数万円セーブすることにもつながりました。
さらに片づけを進める中で発見したことは、モノは使う場所に置くということ。
理江さんは今まで、“子どものモノは子ども部屋に置くべき”というように、モノの置き場所について固定観念にとらわれていました。わざわざ使う場所まで持って行き、その後に戻すのが面倒で使った場所に置きっぱなしになっていることが散らかる一因だったのです。
「娘の行動を観察すると、メイクポーチを持って移動していたんです。洗面所にメイク道具を入れる場所をつくってあげると、出しっぱなしがなくなりました。『使いやすい場所に置けばいいんだ!』っていうのは、当たり前なんですけど、自分にとっては大きな気づきでしたね」
使うモノを使う場所に置くことで、日常の小さなストレスもなくなります。家事を分担している夫に、「洗った食器はここに置いてほしい」と置き場所をシェアすると、意識してやってくれるようになりました。時間の使い方も変わり、隙間時間を活用して片づける習慣が身についたので、わざわざ片づけのためにまとまった時間を確保する必要はありません。
定位置のないモノや飲みっぱなしの食器が放置されたダイニング/ビフォー
片づけが終わる頃には、暮らしやすい環境が整っていました。家の中はスッキリして、きれいになったソファが置かれたリビングには家族が集まります。
「モノが散らかっていたし、私もイライラしていたので、みんな自分の部屋にこもりがちでした。でも、今は自然とリビングで過ごすようになって、会話も増えましたね。片づけ終わってから家族旅行をしたときも、子どもたちがケンカすることもなく、夫婦の会話も多くて……。すごく楽しかったんです! 片づけを通して私が変えたかったのは、当時の家族の状況だったんだなって気づきました」
現状を変えることは、とても大変なことかもしれません。変えるためには、強い気持ちを持って行動することが大切だということを、理江さんは教えてくれました。
「片づけようと決めたとき、また後回しにしていたら、今でも家族はギクシャクしてケンカしていたかも……。私も毎日イライラしていたんでしょうね(笑)。この穏やかな生活がなかったと思うと、あのときの決断は間違ってなかった!」
すぐに片づけてきれいな状態をキープできるようになりました/アフター
こう話す理江さんは、今の生活がとても充実していることが伝わってくる、とても素敵な笑顔です。
「前に進む行動でしか結果は変えられないから、とにかく行動することが大事」という理江さんの姿は、片づけに悩む人の背中を少しだけ押してくれることでしょう。
人生が変わる片づけの習慣 片づけられなかった36人のビフォーアフター
商品価格¥1,650 詳細はこちら ※価格などの情報は、原稿執筆時点のものになるため、最新価格や在庫情報等は、Amazonサイト上でご確認ください。