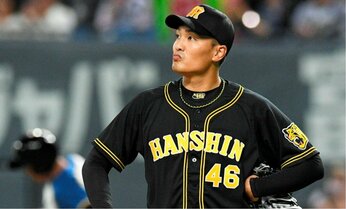地震保険はやはり必要か 都道府県別の世帯加入率トップは宮城県、最下位は?【能登半島地震で見直す備え】
写真はイメージですⒸgettyimages
1月1日の夕方に起きた能登半島の地震では住宅など建物の倒壊や火災が相次ぎ、自然災害の恐ろしさを見せつけられた。地震への備えとして、地震保険について改めて考える人も少なくないのではないか。
1日には石川県志賀町で震度7の強い揺れを観測し、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.6を記録した。
石川県輪島市では地震発生後に観光名所の朝市通りで大規模な火災が発生し、住宅など約200棟が全焼した。市内では7階建てのビルが倒れた様子も伝えられた。ほかにも津波で浸水したり、土砂崩れや液状化現象で家屋が倒壊したり傾いたりするなど被害は広がっている。
被害の全容はまだ分かっていないものの、各地で停電や断水も相次ぎ、自宅が壊れて避難生活を余儀なくされている住民は多い。地震で道路が遮断され、飲料水や食品、日用品といった必要な物資の手当てもままならない地域もある。
二重の負担が生じる恐れ
一刻も早い支援が待たれるが、被災者の頭を悩ますのが生活や暮らしの再建だ。ファイナンシャルプランナー(FP)の清水香さんは言う。
「自宅で暮らせなくなれば、新しい住まいを確保するのにお金が必要になるかもしれません。加えて、壊れた自宅に充てていた住宅ローンが残っている場合には返済は原則続くため二重の負担が生じる恐れもあります」
住宅が全壊するなど深刻な被害を受けた時には最大300万円が支給される「被災者生活再建支援金」をはじめ、公的な支援制度も整えられている。だが新しい住宅を購入したり、修理や補修をしたりするのには必ずしも十分とは言えない。
そこで助けになるのが、地震によって生じた住宅などの損害をカバーする地震保険だ。清水さんは「公的な支援制度が限られるなか、生活再建を支える有力な手段」と強調する。
地震保険は、地震やそれに伴う火災などで住宅や家財が受けた損害を補償する保険のことだ。火災や風水害によって生じた住宅の被害は、通常、火災保険で備えられる。しかし地震や、地震が原因で起きた火災や津波の被害は火災保険では補償されない。地震保険は噴火や津波、さらに地震が原因で起きた山崩れや液状化現象などによる損害も補償の対象となる。
ユニークなのが、国と保険会社が共同で運営する点だ。
「地震はいつ、どこで、どのくらいの規模で起きるかが分かりません。予測を超える被害が生じる可能性もある。民間の保険会社だけでは賄えない可能性があるため、官民一体の仕組みがあるのです」(清水さん)
四つの区分
地震保険は単独ではなく、火災保険とセットで加入する。対象になるのは居住用の建物と家財(生活用の動産)だ。工場や店舗、自動車、30万円を超える貴金属などは対象にならない。
保険金は火災保険の30~50%に設定するルールがある。加えて、建物は5千万円、家財は1千万円が上限だ。例えば建物の保険金が3千万円の火災保険に入っている場合、地震保険の保険金は900万~1500万円の範囲で設定できる。
被災時にもらえる保険金の額は、損害の程度に応じて決まり、損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の四つの区分に判定される点が特徴だ。
建物の場合は壁や柱、屋根といった「主要構造部」が時価の50%以上損害を受けたり、延床面積の70%以上が焼失、または流失したりすると「全損」となり、設定した保険金の100%が支払われる。大半損の場合は60%、小半損は30%、一部損は5%が受け取れる(下の表)。
清水香さんの資料をもとに作成。「主要構造部」は建物の基礎、柱、壁、屋根など。「一部損」は「全損」や「大半損」「小半損」に至らない建物が、床上浸水または地盤面から45センチを超える浸水を受けて損害が生じた場合に区分される
清水さんによれば、建物の主要構造部の損害に注目したり、被害状況を四つの区分で判定したりするのは、火災保険のように被害の状況を一軒一軒詳しく調べると、保険金の支払いまで相当の時間がかかる恐れがあることが理由という。より迅速な支払いができるように、こうした仕組みが用意されている。
保険料はどの保険会社でも一緒
保険料は地域や建物の構造によって違ってくる。日本損害保険協会のホームページで試算したところ、建物に保険金1500万円をかける場合の保険料は、東京都の耐火性能が高い住宅で年4万1250円(月3438円)、耐火性能が低い住宅で年6万1650円(月5138円)。石川県の耐火性能が高い住宅は年1万950円(月913円)、耐火性能が低い住宅は年1万6800円(月1400円)だ。保険料はどの保険会社でも一緒だ。
地震のリスクに対し、さらに手厚く備えたい場合には、一部の損保会社で「火災保険金額の50%まで」といった、地震保険の上限を超えて上乗せした補償が受けられる火災保険の特約がある。だが「補償は同じ額でも保険料は官民で運営する地震保険の倍以上となるケースもある」(前出の清水さん)。
損害保険料率算出機構によると、地震保険に加入する人は少しずつ増えているものの、世帯加入率は2022年になお35%にとどまっている。都道府県別では宮城県の53.6%が最も高く、沖縄県の17.9%が最も低かった。東京都は37.5%で大阪府に次ぐ7番目で、石川県は29番目の30.2%で平均を下回る(下の表)。
損害保険料率算出機構の資料をもとに作成
12年以前は年度ベースでの集計だったため単純には比較できないが、東日本大震災のあった10年度と直近の22年の数値を比べてみたところ、この間に世帯加入率が最も伸びたのは福島県(21.3ポイント増)で、熊本県(21ポイント増)や宮城県(20ポイント増)が続いた。反対に、伸び幅が最も小さかったのは東京都と高知県だった(7ポイント増)。
証拠保全は不可欠
損害保険各社は今回の地震を受けて、すでに災害対策本部を設けるなど、調査や支払いへ向けた対応を進めている。清水さんは次のように話す。
「保険証券が手元になかったり、契約先の保険会社がどこか分からなくなってしまったりしても、日本損害保険協会の『自然災害等損保契約照会センター』で契約の有無や契約先を調べてもらうことができます。また、保険金の請求期間は被災翌日から3年間ですが、証拠保全は不可欠。損害部分の写真を複数枚撮っておきましょう」
災害が起きた時には「保険金の請求をサポートします」「保険を使って住宅を無料で修理できます」などと勧誘する訪問業者が現れることもある。国民生活センターによれば、「無料だから」といって契約すると、ずさんな修理をされたり、解約時に高額の手数料を請求されたりするトラブルが各地で多数発生している。
清水さんは「被災後は直接、保険会社に連絡を。突然現れる、見知らぬ業者を相手にしてはいけません」と注意を呼びかけている。
(AERA dot.編集部・池田正史)