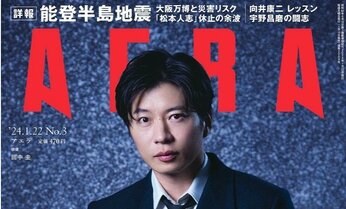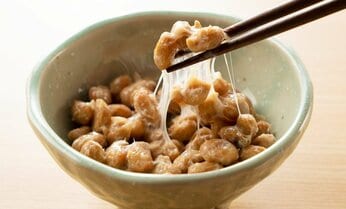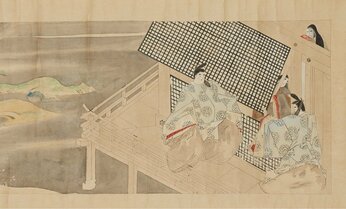【膀胱がん】血尿が自覚症状で最も多く、残尿感・排尿痛・膀胱炎も 再発する恐れが比較的高いがん
男性のほうが、女性よりも3倍かかりやすい膀胱がん。進行すると、膀胱を摘出しておなかに尿の出口を造る手術が必要になることも。尿検査で潜血反応を指摘されたり、肉眼で見える血尿が出たりしたら要注意。早めの受診がお勧めです。
本記事は、2024年2月下旬に発売予定の『手術数でわかる いい病院2024』で取材した医師の協力のもと作成し、先行してお届けします。
* * *
膀胱は骨盤の中にある袋の形をした臓器で、尿を一時的にためておき、一定の量になったらからだの外に排出する役割があります。膀胱に尿がたまってくると、その刺激が脳に伝わって尿意を感じます。排尿時には膀胱の筋肉が収縮して尿道の筋肉を緩め、排尿する仕組みです。膀胱がなければ、尿意を感じることも自然に排尿することもできない、重要な役割を持つ臓器です。
膀胱の内側は、尿路上皮という粘膜で覆われています。膀胱がんの90%はその粘膜の細胞から発生するもので、尿路上皮がんとも言います。
膀胱がんの罹患率は男性のほうが女性の約3倍多く、人口10万人あたりの患者数は19人程度(男性では約29人/女性では約9人)とされています。最も多い年代は60~80代以降ですが、40~50代でもかかることがあります。
高齢者に多いがんなので加齢が最も大きなリスクですが、男女ともに喫煙歴のある人がよりかかりやすい傾向にあり、喫煙もリスクの一つです。
最も多い自覚症状は血尿
膀胱がんで最も多い自覚症状は、血尿です。神戸市立西神戸医療センター泌尿器科部長の金丸聰淳医師は、次のように話します。
「尿検査で潜血反応が出て受診される場合もありますが、最も多いのは、ある日突然血尿が出て、びっくりして病院に来る患者さんです。血尿以外の自覚症状としては、尿が残る感じ(残尿感)や排尿する際の痛み(排尿痛)など、膀胱炎のような症状が出ることもあります。男性の場合、単純な膀胱炎はとてもまれなので、これらの症状がある場合や、病院に行って処方された膀胱炎用の抗菌薬を服用してもなかなか治らない場合には、泌尿器科を受診することを強くお勧めします」
検査方法は尿検査、エコー、膀胱鏡検査など
膀胱がんの検査ではまず初めに尿検査をおこない、尿の中に血液やがん細胞があるかどうかを調べます。その後、膀胱のエコー(超音波)検査や、尿道から内視鏡を挿入して膀胱の中を調べる膀胱鏡検査をおこないます。
膀胱の中にがんがあることがわかったら、CTやMRIなどの画像検査でがんの大きさや深さ、他の臓器への転移があるかどうかなどを調べることもあります。
治療と検査を兼ねるTUR-BT
膀胱がんの治療は、がんが表面の尿路上皮にとどまっているか、その下の筋肉などの組織(筋層)にまで広がっているかで大きく異なります。がんの広がりや、その悪性度などを詳しく調べるためにおこなわれるのが、TUR-BT(ティーユーアールビーティー:経尿道的膀胱腫瘍切除術)という方法です。
TUR-BTは、尿道から膀胱の中に内視鏡を入れ、がんの部分を削り取る手術をするとともに、削り取った組織を顕微鏡で詳しく調べる病理検査をおこないます。
検査の結果、がんが表面の尿路上皮のみにとどまっていれば、そのまま経過観察になることもあります。悪性度が高いと判断された場合には、追加のTUR-BTをおこなってさらに削り取ったり、膀胱の中に再発予防のための薬剤を注入する治療をおこなう場合もあります。
進行がんは膀胱全摘と尿路変向(変更)の手術
一方、がんが尿路上皮の下の筋肉の層にまで入り込んでいる場合には、膀胱をすべて摘出する手術(全摘)が必要になります。全摘では膀胱と骨盤内のリンパ節、男性であれば前立腺と精嚢(せいのう)、女性の場合は子宮や膣の一部、尿道を切除します。また、膀胱を取ると尿をためる場所がなくなるので、排尿の新しい仕組みを造る手術(尿路変向〈変更〉)も同時におこないます。
膀胱全摘と尿路変向の手術の前には、再発や転移を予防するため抗がん剤による薬物治療をおこなうのが一般的です。
手術には開腹手術と腹腔鏡手術があり、腹腔鏡手術には医師自身が腹腔鏡を使っておこなう腹腔鏡手術と、医師がロボットを操作しておこなうロボット手術があります。近年では、より細かい作業ができるロボット手術を含めた腹腔鏡手術が主流になっています。
患者が高齢だったり心臓や脳など他の病気があったりして手術ができない場合などには、膀胱を切除せず、TUR-BTと薬物治療、放射線治療などを組み合わせた治療を選択する場合もあります。
全摘後の尿路変向の方法は大きく分けて二つ
尿路変向の手術には、大きく分けて二つの方法があります。
一つは、腸の一部を使っておなかに尿の出口を造る方法(人工膀胱:ストーマ)、もう一つは同様に腸の一部を使い、おなかの中に膀胱の代わりの袋を造る方法(新膀胱)です。
ストーマを造った場合、おなかに開けた出口から尿が出てくるので、パウチという袋を装着し、2~3時間に一度程度、たまった尿を捨てます。
一方で新膀胱は、おなかにストーマができないのでボディーイメージは良いですが、おなかの中に袋はあっても尿意も感じず筋肉も収縮しないので、自然に排尿することができません。そのため定期的にトイレに行き、おなかに力を入れて、腹圧でたまった尿を排出する必要があります。
「ストーマの管理やケアは、患者さん自身や介護をする家族も、しばらくすれば慣れて支障なくできるようになりますが、新膀胱は管理が少し難しい面があります。定期的な排尿作業がルーズになったり、認知症で管理ができなくなったりすると、からだの中に尿が溜まった状態になってしまい、腎臓に負担がかかって腎機能が悪くなったり、慢性の尿路感染症などを起こす恐れもあります。ストーマにするか新膀胱にするかは、患者さんの生活背景や将来的なことも考え、慎重に判断することがとても重要です」(金丸医師)
治療のあとも定期的に検査を
膀胱がんの場合、再発する恐れが比較的高いので治療後も定期的に受診し、尿検査や内視鏡検査を受けることが大切です。
「例えば、がんが一つだけで3㎝以下、悪性度も低い、といった場合にはTUR-BTで削るだけで治る可能性もあるのですが、少し悪性度が高いと2年以内に再発してくることが多く、また1年以内に再発する人の場合、再発を繰り返すこともあります。ですので、治療後も医師の指示に従って受診し、検査を受けていただくことが何よりの再発予防になります」(同)
膀胱がんの7割程度が、初期で見つかるといいます。1年に一度程度は健康診断を受けて尿検査をしておくことが、有効な予防方法の一つと言えるでしょう。
(文/梶 葉子)
【取材した医師】
神戸市立西神戸医療センター 泌尿器科部長 金丸聰淳 医師
神戸市立西神戸医療センター 泌尿器科部長 金丸聰淳 医師