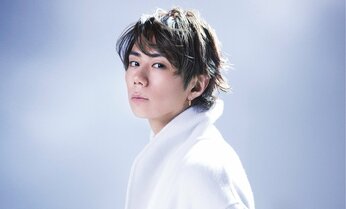柱の上に立って37年暮らした“ストイック”な聖人 「静かな生活」を求めたのに観光地化
シリア・アレッポにある聖シメオン・スタイライト教会の遺跡(写真:Getty Images)
キリスト教が勢力を急拡大するにつれ、利権を求める者たちの聖職者の地位争いによって都市の教会は腐敗した。その一方、信仰と真摯に向き合うことを願う者たちは孤独に修行する“隠修士”となった。中でも特筆すべきは、高い柱の上で37年生活したことから「柱頭行者」と呼ばれた隠修士だ。清涼院流水氏の新著『どろどろの聖人伝』(朝日新書)では、キリスト教国で愛され語り継がれてきた聖人伝が紹介されている。同著から一部を抜粋、再編集し、「柱頭行者」と呼ばれたシメオンを紹介する。
* * *
【関連記事を一気に読む】
#1 “サンタクロース”はキレて投獄されていた 隣人にこっそりお金を配っていた「聖人」
#2 十字架で処刑中に“人生大逆転” キリストの言葉で天国行きが確定した「善良な強盗」
#3 毒入りの盃はまっぷたつ 裸の女性で誘惑させたライバルは圧死 厳格な修道士の起こした「奇跡」
#4 「知らないものは知らん」キリストを置いて全速力で逃げた弟子 逆さまで処刑された場所は今
#5 「猛獣に噛み殺されたい」大観衆の前での処刑を喜んだ司教 直後に起きた大地震に皇帝は
#6 乳房を斬り落とされても元通り、喉に剣を突き刺しても平然 男の「憎」を奇跡で跳ね返した二人の聖女
#7 柱の上に立って37年暮らした“ストイック”な聖人 「静かな生活」を求めたのに観光地化
#8 天使の言葉を信じたジャンヌ・ダルク “魔女”として受けた「究極」の罰
#9 14カ所も刺して自分を殺した男の「回心」を、“死後”も願った11歳の聖女
ローマ帝国で最初は迫害されていたキリスト教が容認され、勢力を急拡大するにつれて、利権を求める者たちが聖職者の地位を奪い合い、都市の教会は腐敗しました。その一方、真摯に信仰と向き合うことを願う者たちは砂漠で孤独に修行する隠修士となりました。そんな隠修士たちが次第に共同生活するようになったのが修道院制度のはじまりですが、あくまで孤独を貫き、いつまでも群れるのを嫌った者たちもいました。中でも特筆すべきは「柱頭行者」や「登塔者」(英語名スタイライツ)と呼ばれるシメオンです。シリアのアレッポの近くに立てた高い柱の上の非常に狭いスペースで37年も生活したことから、彼は「柱頭行者」と呼ばれるようになりました。それ以前にそんな生活をした者は知られておらず、彼自身が発明した、それは修行の新ジャンルでした。
シメオンは10代前半の頃、最初は修道院に入り、極端に禁欲的で過激な独自の苦行を続けました。彼がヤシの葉をねじってつくった縄で全身を縛ったところ、それが肉に食い込んで死にかけたことがあります。その時は、修道士たちが液体で縄を柔らかくして切り裂くという治療を3日も続ける必要がありました。生還したシメオンは、「お前のように過激な修行を好む者に共同生活は無理だ」と、追放されてしまいます。
修道院を追われたシメオンは、以後しばらく崖のような狭い空間で、ひっそりと苦行を重ねながら暮らしていましたが、いつしか「だれよりもストイックな修行者」という彼の噂が広がり、弟子になることを希望する者が殺到したため、逃げ出します。
その後、シメオンは訪問者に修行の邪魔をされないように、高さ3メートルの柱の上で4年間、生活しました。彼は人々から隠れているつもりでそうしたのですが、逆に目立ってしまい、彼を訪ねる人が途切れませんでした。努力する方向を勘違いしたままエスカレートさせて、シメオンは、次に高さ6メートルの柱の上で3年、その後、高さ10メートルの柱での10年間を経て、最終的には高さ20メートルもの柱の上で20年も暮らすことになりました。支援者が運んできた食事を吊り上げて食べていたようです。柱の頂上には手すりがついて、シメオンは基本的に、ずっと立ったままでした。
最初は訪問者を避けるために柱に上る決断をしたはずなのに、皮肉にもその前代未聞の修行方法によって彼のカリスマ性が際立ち、シメオンは終生、彼の希望とは反対に、多くの弟子志願者を魅了し続けることになります。シメオンの柱は観光地化して、彼の指導を求めたクリスチャンたちやローマ帝国の皇帝、異教徒たちまでもが毎日見物に訪れたそうです。柱の上での生活を37年続けた西暦459年9月1日、シメオンは最後は立ったまま亡くなり、ようやく柱から下ろされ、近くに埋葬されました。
シメオンが発明した「柱頭行者」という斬新な修行ジャンルは、その後、多くのフォロワーを生み出し、彼のほかに同名の「柱頭行者シメオン」が3人います。本家は「大シメオン」、ふたりめは「小シメオン」、3人めは「柱頭行者シメオン3世」、4人めは「レスボス島の柱頭行者シメオン」と、それぞれ呼び分けられています。
【関連記事を一気に読む】
#1 “サンタクロース”はキレて投獄されていた 隣人にこっそりお金を配っていた「聖人」
#2 十字架で処刑中に“人生大逆転” キリストの言葉で天国行きが確定した「善良な強盗」
#3 毒入りの盃はまっぷたつ 裸の女性で誘惑させたライバルは圧死 厳格な修道士の起こした「奇跡」
#4 「知らないものは知らん」キリストを置いて全速力で逃げた弟子 逆さまで処刑された場所は今
#5 「猛獣に噛み殺されたい」大観衆の前での処刑を喜んだ司教 直後に起きた大地震に皇帝は
#6 乳房を斬り落とされても元通り、喉に剣を突き刺しても平然 男の「憎」を奇跡で跳ね返した二人の聖女
#7 柱の上に立って37年暮らした“ストイック”な聖人 「静かな生活」を求めたのに観光地化
#8 天使の言葉を信じたジャンヌ・ダルク “魔女”として受けた「究極」の罰
#9 14カ所も刺して自分を殺した男の「回心」を、“死後”も願った11歳の聖女
●清涼院流水(せいりょういん・りゅうすい)
1974年、兵庫県生まれ。作家。英訳者。「The BBB(作家の英語圏進出プロジェクト)」編集長。京都大学在学中、『コズミック』(講談社)で第2回メフィスト賞を受賞。以後、著作多数。TOEICテストで満点を5回獲得。2020年7月20日に受洗し、カトリック信徒となる。近著に『どろどろの聖書』『どろどろのキリスト教』(ともに朝日新書)など。