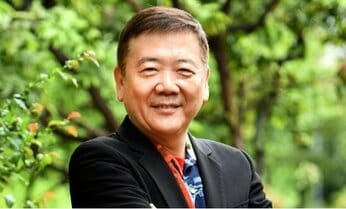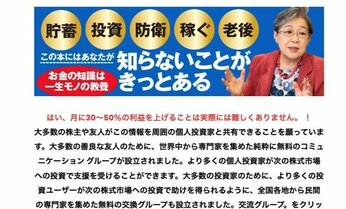「英国の貧困地域が『保育の砂漠』に 保守党政権で『失われた10年』」ブレイディみかこ
作家、コラムニスト/ブレイディみかこ
英国在住の作家・コラムニスト、ブレイディみかこさんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、生活者の視点から切り込みます。
* * *
英国で保育園の閉園が増えている。昨会計年度の閉園数は前年比50%増だ。理由は財政難である。光熱費の高騰、物価高、家賃上昇など、「生活費危機」の時代は「運営費危機」の時代でもある。特に、貧しい地域が「保育の砂漠」になっているとシンクタンクが警鐘を鳴らす。
他方で、政府は2025年秋までに、生後9カ月から小学校入学時までの保育を週30時間まで無償にすると発表した。この政策の背景は閣僚たちの言葉遣いでわかる。彼らは、もはや保育を「幼児教育」とは呼ばない。「子どものケア」である。大人が働いている間に誰かが子どもを見る。それだけでいいという考えが透けて見える。財務相は、この政策を発表したとき、「多くの女性にとってキャリアの中断がキャリアの終焉になっている」とし、「人手不足の解消」のために母親に職場復帰してもらわねばならないと言った。つまり、保育の無償化は教育政策ではない。ピュアに経済のためなのだ。
だが、まず貧しい地域の保育園を閉園から救う支援策を出さなければ、裕福な地域と貧困地域との格差は広がるばかりだろう。それに、経済政策としても、長期的には目の付け所を外しているかもしれない。米国の調査によれば、貧困層の幼児教育に1ドル使えば、成人後の効果は16倍になることがわかった。優れた幼児教育を受ければ、社会保障やメンタルヘルスケアを必要とする確率も減り、就業率が上がるという。
1997年に発足した労働党政権は、格差が経済を衰退させる要因と見極め、教育を優先課題とした。保育は単なる「ケア」ではなく「幼児教育」だという指針を打ち出し、保育の大改革を行った。貧困地域に焦点を定め、保育園併設の育児支援センターを次々と建て、就学時の子どもたちの発達格差を縮めようとした。まさに、政府が「親ガチャ」と闘おうとしたのだ。それは人手不足を母親たちで解消するという付け焼き刃的な政策ではなかったのである。
長期的視野をなくした保守党政権のもとで、英国は停滞し、貧困化した。「失われた10年」という、どこかで聞いたような表現が使われるようになったのは偶然ではない。
ブレイディみかこ(Brady Mikako)/1965年福岡県生まれ。作家、コラムニスト。96年からイギリス・ブライトンに在住。著書に『子どもたちの階級闘争』『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』『他者の靴を履く』『両手にトカレフ』『オンガクハ、セイジデアル』など
※AERA 2023年12月25日号