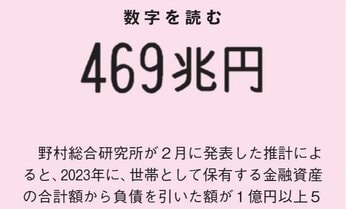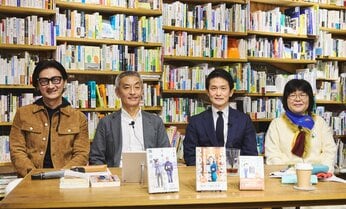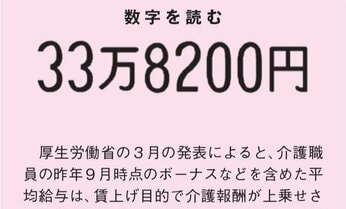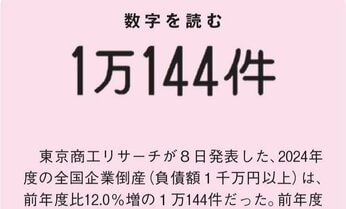
“お金さえあれば”だけでは通用しない時代に? ヒト・モノ・カネで経済活動において最優先にすべきは 田内学
AERA 2025年4月28日号より
物価高や為替、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年4月28日号より。
* * *
霜降り肉の脂が胃にもたれる。40歳を過ぎた頃から、赤身肉ばかり好んで食べるようになった。振り返れば学生時代も霜降り肉をほとんど食べなかったが、それはお金に余裕がなかったからだ。当時はお金の制約によって食べられず、今は健康の制約によって食べられない。同じ「食べられない」でも、理由は大きく異なっている。
私たちが日常生活や経済活動を営むうえでは、常に何かしらの制約が存在する。経済活動に必要な要素として、ヒト・モノ・カネの三つがよく挙げられる。日本が戦後復興を果たして以降、長い間「ヒト」と「モノ」は比較的潤沢だった。高度成長期やバブル期などの好況時や、災害時などには、一時的にヒトやモノが足りなくなるときもあったが、基本的に「お金さえあればなんとかなる」という状況だった。
経済を考える上でも、「いかに資金を調達するか」「どのようにお金を循環させるか」が主な議論になるように、大事なのは「カネ」だった。
ところが最近、状況が明らかに変化している。東京商工リサーチによると、2024年度の全国の企業倒産件数は1万件を超え、11年ぶりの高水準となったという。特に中小・零細企業の倒産が多い。興味深いのはその内訳で、「求人難」や「人件費の高騰」といった人手不足による倒産が前年度比で6割以上も増加し、過去最多を記録している。今や企業経営の最大の制約は「カネ」ではなく「ヒト」になってしまったのだ。
たうち・まなぶ◆1978年生まれ。ゴールドマン・サックス証券を経て社会的金融教育家として講演や執筆活動を行う。著書に『きみのお金は誰のため』、高校の社会科教科書『公共』(共著)など
2年ほど前の年越しテレビの討論番組で、「人手が足りなくなることが問題だから、少子化対策を何より優先的に解決しないといけない」と発言したところ、財務省出身の学者たちからは「そんなことよりも財源の問題が重要だ」と反論された。当時は、財源問題を強調する見方が主流だったように思える。その時の僕は、お金の制約を重視する考え方に対し違和感を覚え、将来への懸念を抱いていた。
しかし、その財務省が今年4月に発表した財政総論では、冒頭から人口減少による労働力不足の深刻さを指摘していた。財務省自身も、「ヒト」の制約が経済活動に与える影響の大きさを強く認識し、ようやく政策に反映させようとしているのだろうか。
人口予測は将来予測の中でも最も正確性が高いものの一つと言われている。20年前には、現在の20歳の人口はほぼ正確に予測できるからだ。つまり、私たちの生きている人手不足の現状は、かなり昔から確実に予測されていた将来だったはずだ。にもかかわらず、財源不足を理由に、子育て支援や少子化対策は長年後回しにされてきた。
財務省の役割を考えれば、彼らが「カネ」の制約を最重要視するのは自然なことだ。しかし、政府としては、「カネ」以外の制約条件である「ヒト」や「モノ」の不足をしっかりと考慮し、政策を優先順位づけする必要がある。
若い頃は「お金さえあれば」という考えで生きていけるが、年齢を重ねるにつれて健康や時間など他の制約に気づき、配慮するようになる。それと同じように、社会の高齢化が進む中で、経済活動においても優先すべき制約条件が変わっている。私たちはいつまでもお金の制約だけを重視するのではなく、新しい時代に合った視点で経済を考えなければならないだろう。
※AERA 2025年4月28日号