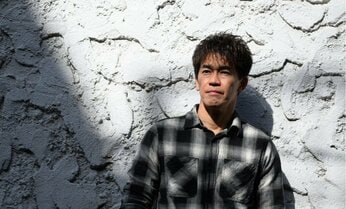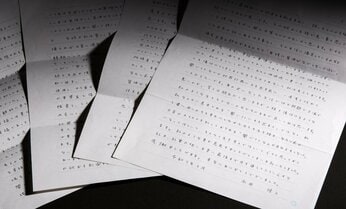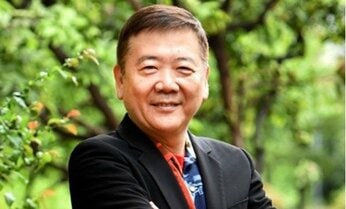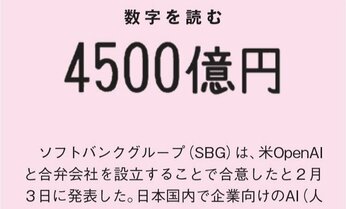さらば、明治の「瓶入り牛乳」 科学が証明した「おいしさ」にメーカーが今も「命をかける」ワケ
3月末で販売が終了する瓶入りの「明治牛乳」。銭湯で風呂上りの瓶牛乳を楽しみにしていた人も多いはずだ=米倉昭仁撮影
乳業大手の明治が瓶入りの牛乳やコーヒー飲料の販売を3月末で終了する。近年、大手乳業メーカーが相次いで瓶入り牛乳の販売を終了するなか、「瓶」にこだわり続けるメーカーや自治体がある。
* * *
湯上がりにぐいっと飲む瓶入り牛乳は、銭湯の醍醐味だろう。東京・高円寺の老舗銭湯「小杉湯」は、長年、明治の瓶入り牛乳を販売してきた。1本180円。
「50年前から通っています。銭湯に来ると瓶入り牛乳を飲むことが多い。ひんやりした瓶を口につける感触は家では味わえませんから」
風呂上がりの男性(60)は話す。
父親と小杉湯に来ていた8歳の男の子は、コーヒー牛乳を飲むのが楽しみだという。風呂上がりのコーヒー牛乳の味を聞くと、瓶を片手に指でGOODサインを見せてくれた。
銭湯で飲むコーヒー牛乳が好きだという男の子=米倉昭仁撮影
だが、ここ数年、瓶入り牛乳の取り扱いをやめる大手乳業メーカーが相次いでいる。小岩井乳業は2021年、森永乳業は24年にそれぞれ販売を終了した。1928(昭和3)年の発売以来100年近く親しまれてきた瓶入り「明治牛乳」の販売もまもなく終了する。
牛乳瓶を手に取り、スマホで写真を撮っている女性(30代)もいた。
「明治の瓶入り牛乳がなくなると聞いて、世田谷から来たんです。『銭湯といったら瓶入り牛乳』という感じなので、寂しいです」
小杉湯を営む平松佑介さんは、こう語る。
「うちは昭和30(1955)年ごろからずっと明治の瓶入り牛乳を販売してきました。そもそも、瓶入り牛乳を大々的に売り出したのが銭湯なんですよ」
昭和30年代、冷蔵庫は高級品で、一般家庭にはそれほど普及していなかった。瓶入り牛乳の宅配販売は行われていたが、常温では腐敗しやすく、消費量は伸び悩んだ。そこで乳業メーカーが注目したのが「銭湯」だったと。
「当時、東京には銭湯が2000軒以上ありました。地域の人々が集まる銭湯に冷蔵庫を置き、瓶入り牛乳を飲んでもらったのです」(平松さん)
瓶入り牛乳のおいしさは格別だ。だが、大手乳業メーカーの撤退が相次いでいる=米倉昭仁撮影
科学が証明した「瓶入り」のおいしさ
「瓶入り牛乳」の販売終了が相次ぐ背景には、いくつかの理由があるという。
最大の課題は「供給コスト」だ。瓶は洗えば繰り返し使えるが、洗浄や殺菌に費用がかかる。重さから運送費もかさむ。
「大手乳業メーカーは、『食のインフラ』を支えるという使命感から、瓶入り牛乳の供給コストを価格に転嫁しづらかったのでは」と語るのは、三重県伊勢市の山村乳業の山村卓也さんだ。
山村乳業は1919(大正8)年の創業以来、「おいしい牛乳には瓶が欠かせない」というこだわりを持ってきた。現在、日本最多の14品目47種類の瓶入り乳製品を製造する(自社調べ)。
「うちは瓶入り牛乳に命をかけています」(山村さん)
大手乳業メーカーでは、生乳を120~130度で2~3秒間加熱して殺菌する「超高温瞬間殺菌」が一般的だ。
「短時間で大量の牛乳を製造でき、コストダウンにつながりますが、高温加熱により『牛乳独特のにおい』が生まれてしまう面もあります」(同)
山村乳業は85度の低温で15分間かくはんしながら殺菌する「パスチャライズ殺菌」を採用している。
「手間とコストはかかりますが、たんぱく質や乳脂肪が熱変性することが少なく、牛乳本来の風味を味わうことができます」(同)
その牛乳本来の味をさらに引き立てるのが「瓶」だという。
明治食品開発研究所と金沢工業大学の研究によると、瓶入り牛乳は、牛乳とふたの間の空間「ヘッドスペース」に香りが凝縮し、ふたを開けた瞬間に濃厚な香りが広がる。コップよりも瓶で牛乳を飲むほうが、香りは約3倍強い。瓶の飲み口がくちびるに接触する面積はコップの1.4倍あり、心地よいひんやり感を生み出す。そのため、瓶で飲む牛乳はおいしく感じられるという。
前出の小杉湯の平松さんは、昨年4月、東京・原宿の商業施設「ハラカド」の地下1階に「小杉湯原宿」をオープンした。そこで提供しているのが山村乳業の瓶入り牛乳だ。1本300円。
「牛乳に詳しい知人から、『瓶入り牛乳なら山村乳業』と教えられた。飲んでみておいしさに驚いた」(平松さん)
牛乳本来の味わいを大切にしてきた山村乳業の瓶入り牛乳=米倉昭仁撮影
子どもたちには「瓶入り」が必要
瓶入り牛乳の学校給食にこだわる自治体もある。東京都日野市もその一つだ。
「子どもたちの評判もいいです。紙パックよりも瓶の牛乳のほうがおいしいし、飲みやすい、という声を聞きます」と、日野市教育委員会の担当者は言う。
同市では2005年春、大手乳業メーカーの工場改修にともない、一度は容器が瓶から紙パックに切り替わった。
「子どもたちの食育を進めるうえで、瓶入り牛乳のほうが優れている。保護者や栄養士会から『瓶入り牛乳に戻してほしい』という声が上がった」(日野市教育委員会の担当者)
瓶入り牛乳には、さまざまなメリットがあるという。①容器のにおいが牛乳にうつることなく、五感で牛乳本来のおいしさを味わえる。残食や「牛乳嫌い」が減る。②中身が見えるので、かたまりや異物がないか、目視で確認できる。③児童が飲んだ量を把握できるので教員が喫食の指導をしやすい。④紙パックだと、リサイクルするために切り開いて洗浄する際、周囲の牛乳アレルギーを持つ子どもに影響が出ないようにしなければならない――。
ただし、学校給食の牛乳は、都道府県ごとに設立されている学校給食会を通じて供給されるため、各自治体が業者を決めることができない。独自に瓶入り牛乳メーカーと契約を結ぶには、学校給食会から離脱しなければならず、国からの牛乳代の補助金も受け取ることができなくなる。
当時、周辺自治体の国立市や小平市では独自契約に踏み切り、子どもたちに瓶入り牛乳の提供を継続していた。瓶入り牛乳を求める声はさらに高まった。
「(日野)市は学校給食会から抜けることを了承してくれました。国庫補助がなくなったぶん、市の予算で『牛乳代補助』をつけていただきました」(同)
06年度、同市の学校給食に瓶入り牛乳が復活した。こうした動きは広がり、現在、都内では9市が瓶入り牛乳を小中学校の給食に提供している。そのすべてが郊外の乳業メーカーが製造するパスチャライズ殺菌の牛乳だ。
販売が終了する明治の瓶入り牛乳をスマホで撮影する女性=米倉昭仁撮影
おいしい「瓶入り」が果たす役割
骨と健康について研究してきた女子栄養大学の上西一弘教授は、「牛乳は比較的手軽にカルシウムが取れる、とてもよい食品。学校給食の牛乳が子どもの成長を担う役割は非常に大きい」と言う。
小学生から中学生にかけては「発育スパート」と呼ばれる時期で、十分なカルシウムを摂取できないと、骨が大きく、丈夫に成長できない。そのツケは高齢になったとき、骨粗しょう症や骨折となって表れる恐れがある。
「若いときにどれだけカルシウムを骨に『貯金』できるかが、老後の生活の安心につながります」(上西教授)
おいしい瓶入り牛乳が果たす役割は思いのほか大きいのだ。
(AERA dot.編集部・米倉昭仁)