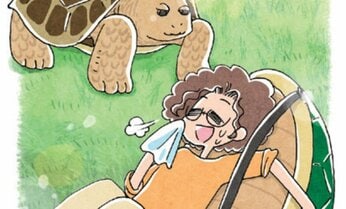「夕飯の時間だから早く帰ってこい!」…婚活で母親からの「親ブロック」に苦しむ女性たちの実像
婚活で「親ブロック」にあった菜摘さん
子どもが希望する就職先に親が反対する「親ブロック」があることは有名だが、実は婚活市場においても「親ブロック」は存在する。特に母親が娘に対して過剰に干渉し、せっかくの良縁が破談になってしまうケースもあり、専門家に悩みを相談しに来る女性も少なくないという。現場の婚活コンサルトが見てきた実態とは――。
* * *
親が結婚に口を出してくること自体は昔から存在していたが、現在の「親ブロック」はマッチングサービスを使って婚活するわが子の「交際相手の選別・否認」する点に特徴がある。特に、子が30代、40代になっても親の理想像を押しつけてくることから、本来であればうまくいった可能性の高い婚活が、親によって阻害されているケースが少なくない。
明治安田生活福祉研究所が2016年に行った「親子の関係についての意識と実態」によると、「子どもの婚活に関与したいか」という質問に対し、47.7%の親が子どもの婚活に関与したいと回答している。特に母親のほうが関与したいという意向が大きく、娘と息子ならば娘に関与したがっている。同調査によれば、娘を持つ母親のうち56.1%が関与したい意向を持っている。
親の干渉があっても、自分の意思を貫けばよいと考える人も多いだろうが、同調査によると、子ども(高校生、専門学校生、大学生、社会人等)のうち、男性42.6%、女性35.6%が反抗期と思える時期がなかったと回答している。親世代で反抗期がないと回答しているのは男性28.1%、女性26.4%なので、反抗期がない子も大きく増えているのだ(いずれも明治安田生活福祉研究所 「親子の関係についての意識と実態」親1万人・子ども6千人調査)。
紹介したデータは2016年少の調査なので少々古いが、私のところに恋愛相談に来られる方や、同業者から見聞きする「親ブロック」も母から娘に対するものが圧倒的に多い。
現在婚活中の美香さん(30代前半)もそんな1人だった。美香さんの家庭は、専業主婦の母親と会社員の父親、そして兄の4人家族というごく普通の家庭だった。美香さん自身、話していると自分の意思をしっかりと持つ女性だったのだが、こと婚活においては「親が気に入るかどうか」を相手選びの判断基準としていた点が気にかかっていた。
「家族に離婚歴があるのはちょっと……」
美香さんは就職を機に実家を離れ、地方で1人暮らしをしていたが、地元企業への転職を契機に実家へ戻った。ささいなことから親子げんがに発展した際、思わぬ言葉を母親から投げかけられた。
「どうせ結婚相手も親の言うことなんか聞かないで勝手に決めるんでしょう!」
けんかの内容とは関係ないのに、突然結婚相手に話題が飛んだことに、美香さんは戸惑った。と同時に、母親は以前から、「親が反対する人と結婚したらうまくいかない」と繰り返し口にしていたことを思い出した。この言葉をきっかけにして、そうした母親の思いが美香さんに重くのしかかり、結婚相手を見る際に、常に「母親ならどう思うか」を気にするようになった。
あるとき、婚活で出会った男性との2回目のデートで、彼から「姉は離婚歴のあるシングルマザー」と打ち明けられた。他にも気になる点がいくつかあったものの、美香さんはもう一度会うべきか迷い、母親に相談した。すると母親は「家族に離婚歴があるのはちょっと……」と難色を示した。その一言が決定打となり、美香さんは男性との交際をやめた。
当時のことについて、美香さんは「断る正当な理由を探していたのかもしれない」と振り返る。自分の一存で決断すれば、「高望みしすぎではないか」という罪悪感を抱いたり、後悔するのではないかという不安が生じたりすることもあるが、母の一言があったことで、安心して断ることができたと私に語った。
一方で「親ブロック」を乗り越えて結婚した女性もいる。
関東在住の菜摘さん(30代後半)は両親が早くに離婚し、祖父母の実家で母親と弟と育った。母親は公立保育園に勤務する保育士で、公務員信仰が強く、菜摘さんにも同様の道に進むことを願っていた。就活の際、菜摘さんは民間企業にも関心があったが、母親の反対を受けて断念し公務員試験を受けた。市役所の正規職員には不採用となったが、非常勤職員として採用されると、母親は満足した様子だったという。
大学生になっても門限は「夕方」
弟は市役所勤務で20代半ばに職場結婚し、母親は弟の結婚後に菜摘さんに婚活を促すようになる。そして菜摘さんが20代後になると、母親に結婚相談所に連れていかれた。
仲人から希望条件を聞かれ、菜摘さんは「フィーリングが合う人」と答えたが、母親が「公務員で長男以外」と割って入った。この出来事に強い違和感を持った菜摘さんは、一度婚活を中断。30代になると、「このままでは人生を親に握られる」と感じ、こっそり1人暮らしの準備を進めた。物件契約後に母親に報告すると、母親から「1人暮らしをするような不良娘を誰も結婚相手に選ばない」と強く反対されたが、実家を離れた。
その後、1人暮らしと転職を経て、菜摘さんはマッチングアプリで現在の夫と出会った。母親の反対を避けるため、先に彼の両親と会い、外堀を埋めた上で紹介する段取りを整えた。
「紹介したい相手がいることを電話で告げた際に『真っ先に公務員?』と聞かれ、会社員だと答えるとため息が聞こえました。『長男じゃないよね?』には『一人っ子の長男だよ』と答えたら、落胆が伝わりました。母親はこれまでも大げさな態度で罪悪感を与え、私の決断を止めてきました。しかし今回は、母親とは離れて暮らしてしばらく時間が経っていたため、母の気分に振り回されることはありませんでした。私は自分が無意識のうちに親の許可を必要としていると思い込んでいたのですが、そこから自由でいいのだとやっと気づいたんです」
そもそも、婚活で「親ブロック」が存在するといっても、当の本人は気がつかないことも多い。その根底には親の愛情があるはずだと思ってしまうからだ。
菜摘さんが最初に違和感を持ったのも大学生になってからだった。門限が日没だったことを友人から「小学生みたい」と指摘されたことがきっかけだった。彼氏とのドライブデート中に母親から何度も電話がかかってきたこともあり、あまりの着信の多さに電話に出ると「夕飯の時間だから早く帰ってこい!」と言われ、恋人が引いてしまった経験もある。こうした出来事が重なった結果、「自分の親は普通でないのでは」と感じるようになったという。
婚活「親ブロック」の8つのサイン
「親ブロック」のサインとしては以下のようなものが挙げられる。
1. 成人後でも転職、1人暮らし、結婚などに親の許可が必要という思い込みがある。
2. 親が気に入りそうかどうかを常に気にして相手を選んでいる。
3.実家暮らしを続けていて、日常的に親が意見を言ってくる。
4. 親からのLINEや電話が同年代の友人よりも多い。
5.子どもの前で大げさに悲しそうな顔やため息をつき、プレッシャーをかけて傷つけ、罪悪感を抱かせる。
6.「あなたのためを思って」「みっともない」が口癖である。
7.服装や髪形に口出しされる。
8.成人後も旅行禁止や門限があるなど、制約が多い。
このような親子関係であれば、婚活中には「この人どう思う?」と相談するのではなく、「結婚することになったから」と事後報告をするのが望ましい。相手探しの段階での相談は友人や婚活の専門家に任せたほうがいい。特に実家暮らしで門限があったり行動が制限される場合は、実家を出るなど物理的に距離を取ることも効果的だ。
親よりも長く過ごすパートナーを選ぶためには、まず何よりも自分の意向を大切にしてほしい。
(婚活コンサルタント・菊乃)