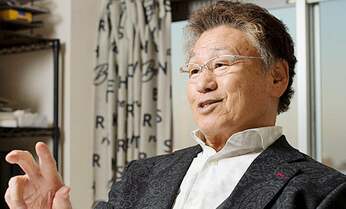
天龍さんが語る“稽古・トレーニング” 泥酔のアニマル浜口を怒鳴りつけた人物とは?
天龍源一郎(てんりゅう・げんいちろう)/1950年、福井県生まれ(撮影/写真部・掛祥葉子)
50年に及ぶ格闘人生を終え、ようやく手にした「何もしない毎日」に喜んでいたのも束の間、2019年の小脳梗塞に続き、今度はうっ血性心不全の大病を乗り越えてカムバックした天龍源一郎さん。人生の節目の70歳を超えたいま、天龍さんが伝えたいことは? 今回は「稽古・トレーニング」をテーマに、つれづれに明るく飄々と語ってもらいました。
* * *
相撲時代の稽古といえば四股と鉄砲だ。俺が二所ノ関部屋に入ったときは13歳で、親方が「子どもでまだ骨格ができていないから」と、入門してから半年は四股と鉄砲ばかりやらされていたね。その頃の兄弟子はみんな17~18歳だったから、13歳の俺が一緒に稽古したら、ケガをしてしまう可能性が高いと踏んだんだろうな。
入門前の夏休みに二所ノ関部屋に稽古見学に行ったとき、序二段くらいの先輩を見て「こんなのには負けないだろう」と思っていてね。そうしたら「あんちゃん、ちょっとやってみるか?」と言われて、まわしをつけて土俵に上がったら、0コンマ数秒でバーンと羽目板まで投げられちゃった。
俺は地元の村相撲じゃあ負けなしだったけど、ここでは部屋で一番下の力士より弱いんだからまいったよ。俺を投げたその人だって、番付は結局序二段止まりだったからね。こりゃあ大変だと思ったよ。親方は当時としては先進的な考え方をする人で、今思えば先にからだをしっかり作らせようというその判断は俺にとってよかったと思う。
半年間、みっちり四股と鉄砲でからだを作ってから、兄弟子たちに混ざって、土俵で相撲をとる“申し合い”をするようになったけど、そのときは調子よかったよ。まあ、部屋の中でも強い部類に入っていたんじゃないか。朝の4時から6時まで、当時は部屋に60人くらいいたから、みんなで入れ替わり立ち代わりで相撲を取るんだ。その頃に親方が言っていたのは「強いやつと数を切ってやれ」ということ。
弱いやつと20~30番やるよりも、強いやつと15番なら15番と決めて、しっかり稽古した方が強くなるということだね。親方はことさら俺と金剛に目をかけてくれていて、大鵬さんたちの稽古が終わると「よし、嶋田(俺)と吉沢(金剛)は三番稽古だ」と言われてね。これがキツイ。当時の俺は14歳で金剛は17歳かな。その年だと体格差があるうえに、俺の方が入門は早いもんだから、負けようものならほかの兄弟子から「この野郎、新弟子なんかに負けやがって!」って、ケツを叩かれたりね。それが嫌で全体の稽古が終わると裸足で浜町のあたりまで逃げていったもんだ(笑)。
6月24日に亡くなられた妻・まき代さんの写真と親子3ショット(公式インスタグラム@tenryu_genichiroより)■新シリーズ『WRESTLE AND ROMANCE』vol.6 /2022年9月4日(日)GONG12:00/東京・新木場1stRING (東京都江東区新木場1-6-24)/前売りチケット※当日券は500円UP▽特別リングサイド6,500円・指定席5,500円/天龍project…https://www.tenryuproject.jp/product/531
配信はhttps://tenryuproject.zaiko.io/item/3472
この同じ力士と延々1時間とか1時間半やる三番稽古がキツかったけど、一番キツイのはやっぱり“かわいがり”だね。これは稽古じゃないか(笑)。周りで見ている関取衆から「この野郎!」「負けやがって!」「のぼせるな!」と怒声がひっきりなしに飛び交う。コーチ役で部屋についている親方も「この野郎、力抜きやがって!」と言っては、バット、竹刀、ほうきとか、棒状のものでとにかく殴る。たぶん、フランスパンがあったらそれでも殴っていたと思うよ(笑)。さすがに相撲部屋にフランスパンは無かったけど。
そんな二所ノ関部屋の中でも特に稽古熱心だったのは、関脇までいった麒麟児だ。彼は俺の弟弟子でからだも小さくてね。いつもコツコツ稽古をしていた。そんな一生懸命な彼を見て俺たちは「なに無駄なことを頑張っているんだ」なんてからかっていたけど、あれよあれよと番付が上がって関脇になったからね。いやあ、稽古は嘘をつかいないよ。
これはよく思うんだが、相撲に入ったとき俺は周りから「横綱、大関になれる」と言われ、俺を相撲に誘った後援者の親戚縁者に東京でステーキをおごってもらったりとちやほやされていて、13歳にして有頂天になっていたんだ。だから大鵬さんのいる二所ノ関部屋に「入ってやった」という思いがあったんだよね。相撲からプロレスに転向したときのように一生懸命練習をしていたら、俺の相撲人生ももっと変わったものになっていたんだろうなと、今になってつくづく思うよ……。
プロレスに転向してからは、それまでしていなかったウエイトトレーニングもするようになった。ショックだったのは、チャック・ウィルソンがコーチをしている「クラーク・ハッチ」というジムで初めてベンチプレスをやったとき、60キロが上がらなかったことだ! チャックはいいからだをしているし、相撲も好きで俺のことも知っていたから余計に悔しかったね。相撲とは筋肉のつけ方が違うんだとつくづく実感したよ。
それからアメリカを行ったり来たりして、ジムの器具でのトレーニングを見よう見まねで覚えてからだを作るようになったんだ。ただ、当時の全日本プロレスは、マシーントレーニングは邪道とは言わないけど、好ましくないものとされていた。ジャイアント馬場さんもジャンボ鶴田も、走ったり、野球やバスケットボールでナチュラルに使える筋肉をよしとするような風潮があったからね。だから全日本の道場にトレーニング器具は多少はあったけど、どれも使った形跡がなくてほとんど錆びついていたよ。
それから俺がマシーントレーニングをするようになって、ようやく他のレスラーも始めるようになった。俺の下の世代の小橋(健太)とか川田(利明)は、いいからだをしているだろう。全日本がウエイトトレーニングをするようになったのは俺がきっかけなんだ。とはいえ、馬場さんが亡くなってから知ったんだけど、自宅マンションの地下にはトレーニングマシーンがあって、ホテルのジムでもトレーニングしていたんだって! そりゃそうだよね。じゃなきゃあのからだとコンディションは保てないもんね。
プロレスラーのトレーニングと言えばスクワットだって? たしかにスクワットは心身の鍛錬になる。同じ動作を延々と繰り返しながら、頭ではいろいろなことを考え、自分の気持ちや今後のことなどを整理するのに大切なトレーニングだ。ところが俺は「相撲で13年間四股を踏んでいたからスクワットなんてちゃんちゃらおかしい」とやらなかった(苦笑)。もう少し、やっておくべきだったかな……。
プロレスはテレビで見たことしか知らなかったから、スクワットもそうだけど、腹筋やブリッジ、首の運動など、あんなに練習しているとは思ってもみなかった。テレビで見たような試合の動きをなんとなくやればいいんだろうって思っていたからね。特にブリッジは壁から30センチくらいの場所に背を向けて立って、そこから後ろ向きに壁に手をはわせて徐々にブリッジをして、壁に鼻がつくまでやらないといけない。これが大変だったね。アメリカに行ったときに数カ月かけてようやくできるようになった。アメリカ時代はそれだけ暇だったと言えるが(笑)。
アメリカでは、プロレスが下手だと試合を組んでもらえないし、下手なヤツを出すとサーキットで稼ぎに来ているレスラーの食い扶持が減るからね。そこはシビアだし、トレーニングしてくれたドリー・ファンクもそこまでは面倒を見てくれない。プロレスは練習で技を何度も食らって、自分のからだで会得するしかないから、とにかく数をこなすことだ。ボディスラムもバックドロップもなんでも受けながら覚える。
だから、プロレスラーは歳を取るとからだにガタがくるんだよね……。特に頸椎、腰椎、足首。若いころはゆるんだ関節を筋肉でカバーできていたけど、筋肉が落ちてくるとどうしようもない。今、俺も自由がきかないからだになって、ハードなプロレスをやってきたんだなとつくづく思うよ。若いころは試合が終わってすぐに「さあ、飲みに行くぞ」と街に繰り出していたけど、あのとき少しでもアイシングしたり、なにかしらケアをしておけば……と思わなくもないなぁ。
プロレスラーで練習熱心だったのは小橋や大仁田厚が思い浮かぶが、一番はなんといってもアニマル浜口さんだ。しかも変わったトレーニングをするよね。朝起きたら太陽に向かって大声を出して気を吐いて、大声で笑うのは健康にいいって。「わっはっは!」とあの笑い方だろう。自分にとっていいと思ったものは積極的に取り入れるし、自分に正直に、まっすぐ生きている人だね。
“面白い元気なおじさん”という印象が強い一方で、浜さんは実はとてもシビアで厳しい人でもある。プロレス界では浜さんの怖さは有名で、特に物事に対して短絡的な考え方をしているとすぐに雷が落ちる。自分の「アニマル浜口ジム」でも若い人たちに生き方を間違わないように厳しく指導して、礼儀作法をしっかり身に着けさせている。プロレス界では「アニマル浜口ジム出身」というだけで一目置かれるんだ。浜さんからやかましくしつけられているからね。そんな厳しい浜さんも、奥さんの初枝さんは怖いらしい(笑)。
俺と浜さんが一緒に飲んでベロベロになってタクシーで浜さんの家まで送ったら、浜さんがまだ「源ちゃん、もう一軒行くぞ~」なんて言っているんだ。そこへ初枝さんが来て「浜口! しっかりしないさい!」と言うと、「はい!」って急にシャッキリしだすんだよ。浜さんも奥さんがちゃんと見守ってくれているという安心感があるからベロベロになるまで飲めたんだろうね。俺も女房がそうだったから、気持ちはよく分かるよ(笑)。いやぁ、プロレスラーにはしっかり者の女房が必要だね。プロレスラーだけじゃなく、奥さんがいる人は、たとえ尻に敷かれても怖くても、俺と浜さんのように奥さんを大切にするんだぞ!
(構成・高橋ダイスケ)
天龍源一郎(てんりゅう・げんいちろう)/1950年、福井県生まれ。「ミスター・プロレス」の異名をとる。63年、13歳で大相撲の二所ノ関部屋入門後、天龍の四股名で16場所在位。76年10月にプロレスに転向、全日本プロレスに入団。90年に新団体SWSに移籍、92年にはWARを旗揚げ。2010年に「天龍プロジェクト」を発足。2015年11月15日、両国国技館での引退試合をもってマット生活に幕を下ろす。

























