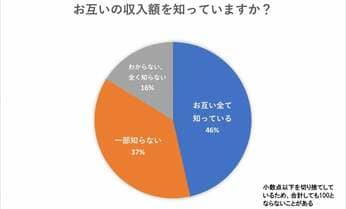お棺に落書き!? 増える「簡素な葬式」と「ユニーク葬」
野球場を映した「メモリアルスクリーン」。担当スタッフが撮影することもある(提供:むすびす)
「家族葬」や短縮型の「直葬」「一日葬」、お経、位牌(いはい)なしの「無宗教葬」に昔ながらの「自宅葬」、人を呼ばないんだからいっそセルフはどうかと「DIY葬」の動きも。コロナ禍で葬儀の自由化が進んでいる!? ライターの朝山実さんが、今ふうお別れの現場を歩いてみた。
* * *
7月はじめ。都内の駅から徒歩数分のセレモニーホールで、コラムニストの小田嶋隆さんの「送別会」があった。とてもいい見送りだった。
故人の「葬儀は要らない」の希望を尊重。「告別式」とは称さず、前夜と合わせて2日にわたってお別れの会が催された。色彩鮮やかな生花祭壇とともに印象的だったのは、僧侶の読経の代わりに小田嶋さんが還暦を機に習っていたギターの先生の演奏だ。
友人たちが故人との逸話を語る間、ジョン・レノン、ボブ・ディランなどの曲を静かに伴奏されていた。喪の場ではあるが笑顔を絶やさず、穏やかな弦の音色が心地よかった。
コロナ禍とあり、当初近親者だけの見送りとされていたが、問い合わせのあった人には伝えられるうち、両日で200人ほどが集まった。
しかし、複数の葬儀社を取材すると、コロナ禍の期間に大人数の会葬は珍しく、増えているのは10人前後の「家族葬」。通夜を省いた「一日葬」や、儀式は略し火葬場でお別れする「火葬式(直葬)」を選択されるケースも多いという。
「コロナの影響ですか? 選ばれるプランが、以前と比べ半分くらいの料金のものになってきていますね。『もう直葬でいいから』という人も増えています。変わったといえば『霊柩(れいきゅう)車は要りません』って言われることかなぁ(セット料金にはご遺体を病院から安置所まで移送する寝台車の料金が含まれている)。うちは関西で有名なタレントさんにイメージキャラクターになってもらって、白いレクサスの霊柩車のオプションサービスをしていたんですが、『ああ、そんなん要らんわ。セットの車で十分や』って」
笑いまじりにぼやかれるのは、京阪神をエリアとする「あゆみセレモニー」の川原昭仁社長だ。1日1家族限定で「ふるさとの家」を思わす古民家ホールと、国内に数台のハイクラスの「霊柩車」を売りにしてきたが、コロナで目玉のリムジンの出番が激減したという。
利用者の本音はどうなのか。昨年、父親を亡くされた図書館員のマユミさんに話を聞くことができた。
父親のトモヒデさん(享年84)は長年、学習参考書の編集者をされていた。長女のマユミさんの下には弟が2人いる。
「父は1年半ほど入院していて、息をひきとった翌日にホールの部屋で葬儀社の人に湯かんをしてもらいました。葬儀は親戚には知らせず、家族だけで見送りました」
実家に仏壇はあり、父の生家は日蓮宗だったが、トモヒデさん自身は無宗教者で「死んだら川に流してくれたらいい」と語っていたこともあり、祭壇も位牌もなし。棺の上には、母が持参した小さなスナップ写真を飾った。
シンプルながらも喪の時間の中でよかったのは、いつも父の傍らにいた愛犬オルが葬儀場に入れたことだという。
「弟が、葬儀社の人に、犬にお別れさせたいんですけどと尋ねたら、いいですよと言ってもらえて。オルが父の顔をペロペロとなめているのを見て、みんな泣いてしまいました」
耳を傾けながら、記者が、父のときにもそうしたらよかったなぁと思ったのが遺影写真だ。
額装の大きな遺影でなく小さな額にしたのは、「母は、ふだんから居間に家族の写真を飾っていて。大きな写真は好みじゃなかったんでしょう。実家に行くと母は父のその写真を見ているんですよね」
リムジンの霊柩車もそうだが、出棺の際に家族が胸に抱く大きな遺影は、会葬者に向けたセレモニーの意味合いが大きいのかもしれない。コロナ禍は葬儀の形も変えつつあるようだ。「お坊さん」も「位牌」もなしでもいいかと葬儀の簡略化が進むとともに、それぞれの価値観にあった「自由」な弔いが加速度的に広まりだした。
富士山を映した「メモリアルスクリーン」。担当スタッフが撮影することもある(提供:むすびす)
■故人らしさ演出 スクリーン祭壇
そこでユニークな試みをしている葬儀社を取材した。ひとつは、東京近県を拠点とする「むすびす」。近年は生花の祭壇が主流になっているが、こちらでは畳数枚分のシルクスクリーンを用いた祭壇づくりを提案している。
草野球に熱を入れていた故人なら、なじみの球場のホームベースを中心にした写真をスクリーンのように棺の背後に貼りだす。いつも夏祭りの先頭に立っていた故人のいなせな法被姿の写真を等身大に引き伸ばして飾るなど、故人にあった送り方を提案している。
「当社では、メモリアルスクリーンと呼んでいますが、故郷の風景、満開の桜など故人らしいオリジナリティーを出せることから、月平均250件施行させていただいている中の6割以上のご利用をいただいています」と語るのは、むすびす株式会社・葬祭事業部の吉岡雄次部長代理だ。
「費用面でも、生花の祭壇と比べて抑えられるという利点もあります」
そのために専用の大型プリンターを導入しデザイン部門も設けている。
「スクリーンもそうですが、当社が力を入れているのは、まず担当がご家族にインタビューし、ひとつひとつプランを練っていくこと。ですから、まったく同じお葬式というのはありません」
むすびすでのコロナ禍での変化を問うと「10人前後の家族葬」「無宗教葬」「自宅での葬儀」の増加をあげた。
葬儀の縮小がいわれる中、葬儀社が提示する価格プランも驚くほど下落している。ネットを検索すると家族葬だと30万~70万円をよく目にするが、火葬だけだと10万円以下(火葬料金は別途だが、自治体によっては無料、1万円のところもある)のものも出てきている。
さらにコストダウンを図りたいなら「セルフ」という一案もある。
一見サブカル本だが、丁寧な取材で葬儀のことがよくわかる
棺おけや骨つぼ、お坊さんの手配すらネットで可能な時代である。「3万円以下で火葬までできる場合も!」と節約マニュアル本も出ている。『DIY葬儀ハンドブック 遺体搬送から遺骨の供養まで』(駒草出版)だ。著者でライターの松本祐貴さんに都内で会ってみた。
「葬儀社の人たちの現場を取材。遺体の保冷庫まで見せてもらいましたが、取材するほど、本当に自分でやるとなると難易度は高いと思いました」
出版は2019年10月。地道に売れ続けているが、読者から体験したという反響はいまのところないという。企画の発案は葬儀社で働いていたことのある編集者によるもの。記者も読めば読むほど「セルフは大変だ」と思った。
「そう思います。だから本の注意書きに、やるには覚悟がいりますと書いたんですよね」
いちばんのハードルは、遺体の処置。体液が漏れ出さないように綿を鼻などに詰めていくのだが、「グイグイ押し込まないといけない。これは心理的にかなりキツイ」と松本さん。
■本人からが多いDIY葬儀相談
よく「高い」といわれる葬儀料金だが、仕事内容を細かくチェックしていくと、なるほどなあと納得するところもある。そもそも松本さんがこの本を書くことになったのは、父親の葬儀の体験がもとにある。
「ネットの紹介会社に頼んだんですが、あとからいろいろ後悔したんです。父はテレビのカメラマンでしたから、あのとき映像を使って何かしてあげたらよかったとか。初めてのことだけにどうしたらいいか。いろいろ話を聞いてもらえる葬儀社だったら、よかったんでしょうけど」
私事ながら記者も10年ほど前に父の葬儀を体験し、弔いに関わる取材をしてきた。葬儀社選びのポイントを問われると、松本さんが言うように「プランの説明の前に、まず話を聞こうとしてくれるかどうか」だろう。
『DIY葬儀ハンドブック』が出版された当初は、葬儀関係者から否定的な陰口を浴びたりもしたが、なかには好意的な葬儀社もあるもので「DIYをサポートします」という葬儀社があらわれた。鎌倉を拠点とする「鎌倉自宅葬儀社」だ。
名前のとおり、自宅での葬儀を専門とする。「自力葬」と名付けたプラン(税込み5万5千円。数回の電話相談などで完全サポートする)を始めたのは昨年6月から。
色とりどりの生花に囲まれた故人のベッドで、愛犬が眠っている(提供:鎌倉自宅葬儀社)
葬儀コンシェルジュの馬場偲さんを訪ねたところ、「残念ながら実施にいたったケースはまだゼロなんです」という。それでも問い合わせは開始から1年間で40件ちかく。意外というか、ゆくゆくを考えた本人からの事前相談が多いという。
「断念されるのは、やはりご遺体のケア。ひとつひとつ説明しはじめると、じっくり考えてみます、となります」
相談者が家族の場合は、本来の「自宅葬」を申し込まれるそうだ。
じつは、記者の知人で、先のハンドブックが出版される以前だが、DIY葬を実践した人たちがいた。病院で亡くなった後、棺おけと火葬場の予約だけは葬儀社に頼み(火葬場によっては一般からの受け付けは断られることがある)、病院から自宅への搬送も自家用のバンに載せ、2階の寝室にも数人で抱えて運ぶなどした。
故人が舞台演出家だったこともあり、遺族は通夜を「フェス」と呼び、平服で集った知人たちがワイワイガヤガヤと思い出話に花を咲かせる。その場に交じり落語みたいだと思ったが、故人の妻いわく唯一の失敗は「ぽかんと開いたままの口」。気づいたときには遅かったという。「でも笑っているみたいだったから、いいよね」
印象に残っているのは、小さな子供たちによるクレヨンの寄せ書きだった。棺の四方がスキマなく、カラフルな絵や言葉で埋まっていた。
その話をすると、馬場さんが「落書き、ああいいですよね」とニコニコする。馬場さんも過去にそういう葬儀に立ち会ったことがあるという。
■自分たちで考え見送った充足感
「鎌倉自宅葬儀社」の社員は馬場さん一人。社外のスタッフに協力を仰ぐことはあるが、ドライアイスの交換などは自身が日参する。欠かさないのは「故人のお人柄などを聞かせてください」とヒアリングするなど、遺族との対話を心掛けている。推奨するプランが一風変わっているのは、葬儀にかける日数だ。短くとも3日間。できれば7日間「自宅」で見送りをする。
近年、通夜を省略した「一日葬」が一般化しつつあることを考えると、時流に逆行しているように思えるのだが、「コロナ以降、受注は3倍近く伸びています」という。
シンプルプランで35万円(税別)。7日間が目安のセレモニープランだと85万円(同)。他社と比べそれほど価格は違わない。
しかし7日ともなれば、さすがに「長い」「間延びするのでは」と問い返してみた。馬場さんも「そうなんです」とうなずく。馬場さんは「故人と過ごしながら、何もすることがなくなってくる日常が大事なんです」。家から送りだす「最期の日」をどのようなものにするのか。「故人としっかり向き合い、ゆったりと考えていくことが癒やしにもなっていく」という。
棺に孫たちが色とりどりのクレヨンで言葉や絵を描いていくのもいい。最後の晩餐は故人が好きだったものを家族でこしらえたり取り寄せたりして、昔話に花を咲かせるのもありだろう。
「ペットのいるご家庭でよかったのは、一緒にお別れができたことですね。入院中に会えなかったりして、ホールの葬儀だと家族のような存在ながらお別れができないことが多いですから」
馬場さんが心動いた葬儀の例と話してくれたのは、ドライアイスの交換で訪れたときに、故人を寝かせていたベッドの布団の上で愛犬が眠っていた。
「私もなぜ、お葬式をするのだろうかと考えてきました。葬儀社にぜんぶを任せてしまうのではなく、自分たちで見送ったという充足感が大事なんだと思うようになり、なるべく日常のままにお見送りすることをテーマにするようになりました」
拠点は鎌倉だが、関東近県のみならず名古屋からの依頼にも応じている。
「確実に『自宅葬』の需要は増えてきていると思います。うちと直接のつながりはないですが、全国各地で『○○自宅葬儀社』を掲げる葬儀社も増えているんですよね」
馬場さんは葬儀の仕事をする前に写真を学んでいたこともあり、葬儀の際に家族が集まった写真を撮影させてもらうことが多い。一部を見せてもらったが「おじいちゃんの耳もとで語りかけるひ孫たち」。記念の集合写真にしても、にぎやかな声が聞こえてきそうなくらいの笑みを見せたものが多かった。
(文中カタカナは仮名)※週刊朝日 2022年10月14・21日合併号