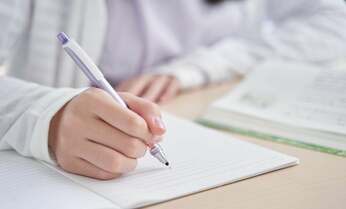
中学入試で「東大入試」と同じテーマを出題した学校は? 「詰め込みでは太刀打ちできない」
写真はイメージです(Getty Images)
2022年度の首都圏の中学入試の受験者数は5万1100人、受験率も17.30%前年度よりも上昇しました(首都圏模試センター調べ)。8年連続で受験者数、受験率ともに増加し、ますます過熱する中学受験ブームですが、入試そのものにも変化が起きています。AERA dot.では短期集中連載「2023中学入試の今」と題して、入試の現状を専門家の分析とともに紹介していきます。第1回は、脱知識型の入試問題について。従来のような知識の詰め込み対策だけでは太刀打ちできない、その場での読解力や思考力が問われる出題が目立ちます。工夫を凝らした各校の問題が受験生に伝えたいメッセージとは――。
* * *
テスト用紙を開いた受験生は、とまどったにちがいない。公文国際が17年度に行った社会科のテストは、最初の資料が婚姻届の用紙だった。資料2では婚姻に関して規定された日本国憲法の第24条を取り上げ、資料3と4に朝日新聞の同性婚に関する記事が続いた。問題の意図を、社会科主任の渡辺太郎先生は次のように話す。
「本校は毎年公民の問題に、実社会で起きている時事を取り上げています。17年は夫婦別姓が問題になった年でした。問題には、社会科をただの暗記科目にしてほしくない、社会に興味を持ってほしいというメッセージが込められているのです」
■大学入試の一歩先を行く中学入試
首都圏を中心に中高500校あまりの入試過去問題集を出版している声の教育社常務取締役・後藤和浩さんは「中学入試が面白い」と語る。後藤さんの業務は現在は渉外が中心だが、編集部にいたときには毎年250校、500以上の入試問題を解いていた。その経験からこう話す。
「大学入試改革や、センター試験が共通テストに変わった影響があるのでは、という説もあるのですが、実は中学入試のほうが先です」
とくに15年度あたりから記述が増えたり、小問数を減らして考える時間を増やしたりするなど、思考力を問う問題が増加してきたという。
「従来型の知識を問う問題も出されるので、中学入試の学習は必要です。ただ最近は細かな知識を問うよりは、その場で考えさせる問題や、文章で表現するような問題を出題する学校が増えてきた印象です」
後藤さんが「重箱の隅」をつつくような知識問題として挙げる過年度の難問例は「静岡県内の東海道新幹線各駅停車の西からの駅名」「タシケント(ウズベキスタン)の雨温図」「十字軍の遠征が世界に与えた文化的な影響」など。後ろの2問は中高校生レベルの問題ではないだろうか。
一方で、「資料として提示されたガイドブックを読み取り、旅行の計画を立てる」(清泉女学院)、「自分が日本代表の監督だったら消化試合をどう捉えるか」(慶応湘南藤沢)など、知識だけにとどまらない自身で考えるような問題が出題されるようになったという。
超難関校では以前から、深い考察を必要とする問題が出されてきた。たとえば灘や筑波大付属駒場の国語で出題される「詩」の問題は、受験生を戦々恐々とさせている。
「詩の形式を問うような学校もあるのですが、灘や筑駒は本質的な読解です。詩のような短い文章からは、その行間も読み解かなければならず本当に難しいのです。筆者が言葉に表さなかったことまで理解して、言葉に落とし込む。いわば芸術的な行為であるとすら思います」(後藤さん)
■数学者の定理が出題
明星学園の算数の最終問題では、「ユークリッドの互除法」「ヴェーダ数学」「カプレカ数」「オスターリー・マッサー予想」など、過去の数学者の定理が出題されたこともある。定理についての詳しい解説がなされ、それを読み解けば問題を解けるようになっている。本物の数学を知ってほしいという、教員の意気込みが伝わってくるようだ。
大妻多摩では22年度、東大と同じテーマの問題が出題された。大妻多摩の「日本のりんごが高価格であるにもかかわらず、台湾が日本のりんごを輸入するのはなぜだと思いますか」に対して、東大は「りんごの輸出量が増加している理由として図から考えられることを、2行以内で説明せよ」と、両校ともに日本の果物の輸出が伸びていることに着目。
社会科の森谷陽子先生は、出題の背景を次のように話す。
「小学校の知識に、自分なりの考えをプラスできないかと考えました。日本は工業製品の輸出では知られていますが、農作物の輸出はあまり知られていません。そこに目をつけました」
亜熱帯、熱帯地域の台湾ではりんごが生産できないこと、また赤や黄色を縁起が良い色として尊ぶ中華圏の文化など、いろいろな角度から考えられる問題だ。
「たまたまでしたが、東大とかぶったのはうれしかったですね」(森谷先生)
■入試は1日目の授業
後藤さんは入試を「1日目の授業」と称する。
「先生方は入試を、ただの選抜だとは思っていません。入学してから伸びてほしいと思う、指標でもあるんです」
大妻多摩の森谷先生は言う。
「地理は、覚えなければいけないことが多くて苦手意識を持つ生徒が多い。でも修学旅行に行くと主体的に学習します。社会科は生活に密着した教科です。関心を持って、情報を受け入れるだけでなく、発信もできるようになってほしいのです」
冒頭の公文国際は、公民で新聞記事を使った授業を行っている。同じテーマを扱った複数の新聞記事を比較し、視点の違いなどを生徒が話し合う。22年度の東大推薦入試で、同高校の原田怜歩(はらだ・らむ)さんが合格した。在学中に行った「LGBT(性的少数者)にとってのトイレ」についての研究が評価された。
「社会科の教員は、社会問題に関心がある生徒を育てたいという思いがある。そういう影響があったのかもしれません」(渡辺先生)
これからも思考型、読解型の入試は広がりそうだ。後藤さんは対策として、多くの人と話をすることが大切だと話す。
「同じニュースを見ても、立場の違いでいろいろな考えがあります。いろいろな人と話をして違いを知り、それ対して自分はどう思うのか考える習慣を身につけましょう」
(ライター・柿崎明子)
























