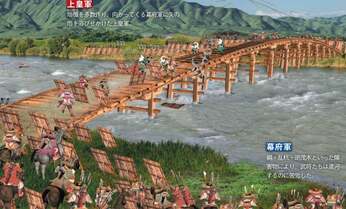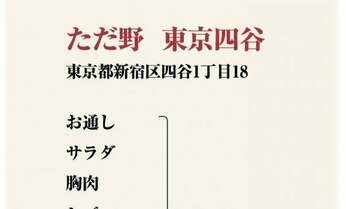梯久美子「“父と出会う旅”は死んで始まる」女性作家9人の父娘物語
梯久美子(かけはしくみこ)/ 1961年、熊本市生まれ。ノンフィクション作家。2005年のデビュー作『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。著書に『狂うひと』『原民喜』『サガレン』など。
「娘から見ると母の気持ちは理解しやすいのですが、父にはどこか謎があるんです」と、ノンフィクション作家の梯久美子さんは言う。
『この父ありて 娘たちの歳月』(文藝春秋、1980円・税込み)は小説家、詩人、歌人など9人の「書く女」とその父との関係を描いたもの。取り上げるのはいずれも、梯さんが愛読してきた作家だ。
石垣りんは、詩の中で父とその4番目の妻の関係を「鼻をつまみたくなるのだ」と表現した。
「父をここまで突き放して描いたのはすごいと思います。それほど父を嫌悪していたのに、りんは一人で働いて一家を支えたんです」
修道女の渡辺和子は9歳のとき、二・二六事件で教育総監の父・錠太郎が目の前で射殺されるのを目撃した。
「和子さんにインタビューしたことがあるのですが、戦後、叛乱軍の一人と会った際、相手に憎しみを感じたことを、『父の血が流れていると思ってうれしかったですね』と話されていました。自分に対してとても正直な人でした」
一方、二・二六事件で叛乱軍を支援した齋藤瀏(りゅう)を父に持つのが、歌人の齋藤史(ふみ)だ。彼女は父のことを「おかしな男」と歌に詠んだ。
「時代に左右されて、何者にもなれなかった父への気持ちが表れていると思います」
作家・島尾敏雄の妻である島尾ミホは、奄美の父を捨てたという思いを生涯抱えていた。
「実は養父でしたが、彼女はそのことを隠していました。自分が素晴らしい父の娘だったという物語を守りたかったのかもしれません」
本書に登場する女性は長命だった人が多い。
「父を描くためには、肉親としての『近い目』と、一歩引いた距離から父を見つめる『遠い目』が必要です。『遠い目』は年齢を重ねることで獲得できる面がある。長く書き続けることで、父の見方が変化することもありますね」
水俣病患者を描いた『苦海浄土』の石牟礼道子は、若い頃は家父長制を批判していたが、晩年には父の深い孤独に目を向けた。また、作家の田辺聖子は少女時代の日記で、父を辛辣に批判したが、後年には戦争で多くを失った父を哀惜している。
「その時代ゆえに、そう生きるしかなかったということに気づくと、父の気持ちが分かるようになるんですね」
梯さんの父は陸軍少年飛行兵学校を経て、戦後に自衛官となった。
「40代になって初めて書いた『散るぞ悲しき』で軍人をテーマにしたのは、父を知りたいという思いがあったからかもしれません。当時のことを調べるうちに、その時代に父が置かれた立場が理解できるようになった」
他に、萩原朔太郎を父に持つ作家・萩原葉子、詩人の茨木のり子、ノンフィクション作家の辺見じゅんが登場する。
「父が亡くなっても関係は終わらない。むしろ、そこから父と出会う旅が始まるのだと思います」
(南陀楼綾繁)※週刊朝日 2022年12月23日号