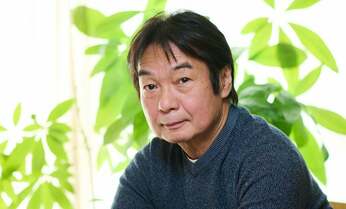「妻が怖い」「夫が不快」脳科学者が伝授する“既婚ボッチ”を抜け出す3つの方法
黒川伊保子さん 撮影/高橋奈緒(写真映像部)
不機嫌な妻に困っている夫のための『妻のトリセツ』や、使えない夫にイラついている妻のための『夫のトリセツ』などの著書が人気の脳科学者・黒川伊保子さんが新刊『夫婦のトリセツ 決定版』を出版した。「夫婦は必ずすれ違い、腹が立つようにできている」、「100%満足な夫婦の会話はあり得ない」と断言する黒川さんに、その理由と、少しでも快適なパートナーシップを築くために試してほしい超簡単な3つの方法を聞いた。
くろかわ・いほこ/脳科学・人工知能研究者、感性リサーチ代表。1959年、長野県生まれ。奈良女子大学理学部物理学科卒業後、コンピューターメーカーにてAI開発に従事。男女の脳のとっさの使い方の違いに注目し、研究結果をもとにした『妻のトリセツ』『夫のトリセツ』(ともに講談社)が話題に
* * *
「妻が怖い」
「既婚男性には人権がないのでしょうか」
そう訴える男性が増えていると黒川さんは言う。巷にあふれる「妻の機嫌を取れ」という本の通りにしても、夫にはその行為自体がストレスとなり、夫婦は互いに満たされず孤立し“既婚ボッチ”へと化していく。
「これまでのトリセツシリーズは『本当に厄介よね』『捨ててやりたいよね』というトーンで書いたので、『夫婦のトリセツ』は夫婦の共通言語として仲良く読める本にしたかったんです。男女の脳は大きさのバランスは違えど、同じ機能を持つ同じ臓器です。ただ、とっさに使う脳の回路が男女で違うことが多く、言ってほしい言葉と言いたい言葉が正反対。それが夫婦生活でどんなすれ違いを引き起こすのか、特に子どもを産んだときにどんな溝ができてしまうのかを知ってほしかった」
黒川さんによると、何か問題が起きたとき、脳内では主に2タイプの回路が起動されるという。ことのいきさつを振り返り根本原因を探る「ことのいきさつ派」と、今できることに集中してスピード重視で動き出す「今できること派」だ。意識的には男女ともにどちらも起動できるのだが、反射的には女性が前者、男性が後者を選ぶことが多いのだそう。
例えば、子どもの具合が悪いとき、多くの女性は「そういえば夕べ…」のように関連記憶をたぐって根本原因に迫ろうとする。一方で、男性は「体温計は?」と探し始める。妻にしてみれば、体温は二次的情報なのに(触れば高熱なんかないのもわかるし)、体温計で大騒ぎする夫にイラッとすることになる。
「夫婦はお互いに逆を選び合って、鉄壁の守備体制を取るようになっています。だから愛があるからこそすれ違う。必ず腹が立つ組み合わせなんです。単純に脳の選ぶ回路が違うだけなのに、相手のことを心がないひどい人だと人格を疑ったり、能力を低く見積もったりしてしまう」
夫婦の日常会話が噛み合わないのも、この違いによるものだ。
女性に多い「ことのいきさつ派」は結果よりも、そこに至った気持ちを訴える。例えば「荷物を持ってほしい」と言わずに、「ほら見て、どの夫婦も旦那さんが持ってる」「どうして私だけ?」「なぜあなたは……」と言うのだ。一方、男性に多い「今できること派」には、過去のことや心得を指摘されても、今どうしてほしいのかが伝わらないため、「気づかなかったんだからしょうがないだろう」「忙しかったんだ」と論点がズレていく。
■夫婦の会話「100%幸せはあり得ない」
この場合、男性は「しなかったこと」ではなく「気づかなかった気持ち」に謝るべきなのだ。「気づかなくてごめんね」のように。逆に女性は「持ってほしい」と率直に言えばいい。案外素直にそうしてくれて、「やっぱりあなたは頼りになるわ」とでも言っとけば、次からは黙って持ってくれることもあるそう。
「妻のために共感型の会話にする、夫のために結論だけを伝えるという工夫はできても、互いにストレスです。つまり、夫婦の会話でお互いが100%幸せという状態は、実はあり得ない。夫婦の会話は痛み分けなんですよ。そもそも100%思い通りの答えが返ってくる人に異性として惹かれますか? 予想と違う答えが返ってきて、良くも悪くもこちらの心に波が起こるから魅力的なのです」
積み重なるすれ違いの結果、パートナーがいても孤独に苛まれる“既婚ボッチ”が巷に溢れることになる。できることはあるのだろうか……。
今年こそ夫婦関係を良くしたいと考える人に、黒川さんがオススメする方法を3つ教えてもらった。
“既婚ボッチ”を抜け出すためには?
まず1つ目は、相手の話を肯定的に受け止めること。聞いた話に「いいね」「そうだね」「確かに」と言ってから、自分の意見を添える。これは従来から黒川さんが男性向けにアドバイスしてきたことだが、女性にもやってみてほしいと訴える。
「女性は女友達には共感できるのに、夫や家族にはそうしていないことも多い。腹立たしくても、1回は『いいね』です。本当に同意できないなら『そうかぁ』でもいい。子どもがいるなら、子どもに対しても使って欲しい。どんなことでも話していいんだという安心感が育っていきます」
2つ目は、何でもないことを話すこと。特に子育て中や仕事などで忙しく時間に追われている時は、用件を伝えるだけのコミュニケーションになりがちだ。「連絡事項がない会話は相手と触れ合うこと自体が目的。それに気付き愛おしく感じる人は多いでしょう」と黒川さんは言う。つまり、付き合いたてのカップルがやる、アレだ。
「結論のない会話は男性にとって非常に難しいことでもあります。それなら見たものをそのままLINEしてください。出張帰りの新幹の中から『小田原通過中』と打つだけでいい。電光掲示板に出てきますから簡単です。離れている間も、あなたのことを思ったという証拠を残しましょう。欠けがえのない存在だという感情がよみがえってくるはずです」
そして3つ目は、家事のリーダー制導入だ。「家事の手順も世界観も違う男女が一つの作業を協業するのは困難」なので、責任を持つ家事を分ける方が圧倒的に楽になる方法だという。
■「精緻なシングルタスク」と「無責任なマルチタスク」
「男性は買い物に行く前にきちんとリストを作り、計画的に進めたがる精緻なシングルタスク。一方、女性は無責任なマルチタスクです。やかんに水を入れている間に、野菜を切って、お風呂を洗って……と、頭に浮かんだことをどんどん片づけていくから1日の家事を終わらせることができる。20回に1回は鍋を焦がしてしまうぐらいの失敗は想定内のリスク。そのぐらい世界観が違うのです」
だからこそ、夫婦で家事分担を進めたい場合は「カビ取りリーダー」や「蕎麦茹でリーダー」など、得意なことから担ってもらうといいという。当番ではなくリーダーなので、誰かに指示してやってもらうことも可。ただし、リーダーがやることに決して偉そうに指示をしてはいけない。「失敗も糧になると覚悟を決めて、使う道具や洗剤、工程まで任せてほしい」と黒川さんは言う。
「愛があれば乗り越えられるのではなく、愛があるから男女はすれ違います。脳の違いが理解できれば、心理的安全性が保たれるいい夫婦になれるはずです」
最後にAERA dot.編集部に寄せられた読者からの相談にも答えてもらった。
【相談内容】
「出産してから夫へのイライラが止まりません。息子も5歳になり、パパとママが険悪だと可哀想だし仲良くできたらいいのにイライラが勝ってしまいます。(30代 広島市)」
【黒川さんの答え】
相談者さんは「イライラする」と書いてあるだけなので、夫が暴力を振るうなど明らかな問題があるわけではなく、おそらく感性の違いなのだろうと思います。
子育て真っ最中にイライラしてしまう理由の一つは、「今できること派」と「ことのいきさつ派」という男女の特性が、生殖・生存のために大きく振り切るからです。女性は子どもの変化を見逃さないようにものすごく共感型になり、守るものができた男性は狩猟本能が働き共感力が人生で最低レベルに落ちる。子育てに対する温度差も出てくるでしょう。
もう一つの理由は、母親の五感のレンジ(範囲)が子どもに合っているから。ずっと子どもの肌を見ていると、帰宅後の夫が脂ぎって、汚いもののように感じてしまいます。足音も冷蔵庫を閉める音もうるさくて、子育て期はとにかく夫がガサツで汚くて、わかってくれなくて、もうとにかくそこにいるだけで腹が立つという状態。何でもわかってくれる5歳の1人息子に対して、何もわかってくれない中年の夫。それは、夫にとってちょっと不利な状態です。
■子育て期は「夫を同居人と思ってやり過ごす」
離婚して別のパートナーを探すという選択ももちろんあると思いますが、夫婦になれば大体7年ぐらいで同じ状態になるはずなので、「気のいい男友達」と思って少しやり過ごしてみてはどうでしょうか。自分の夫でも子どもの父親でもない同居人が生活費を半分出してくれるってすごく良いなと思っていたら、数年後には情のような気持ちが芽生えているはずです。
私の研究では、人は免疫サイクルの影響により7年周期で精神的にも“脱皮”していきます。結婚7年目、14年目で離婚するカップルも多いし、転職も多い。今、相談者さんが結婚7年目で「この人じゃなかった」と思っているなら、1年間は慌てず騒がず、つかず離れず過ごしてみて。ある日、そこまで嫌じゃなかったって思えたりすると思います。
さらに子どもは8歳になると小脳が発達して因果関係が分かるようになり、言葉で説得できたり、子ども自身が解決策を提案してくれたりするようになります。以降、子どもは生活のパートナーになり、夫婦の時間を持ってお互いを見直す余裕が出てくると思います。その時に「やっぱり要らない」となってしまわないよう、すれ違う理由を知っていてほしいなと思います。