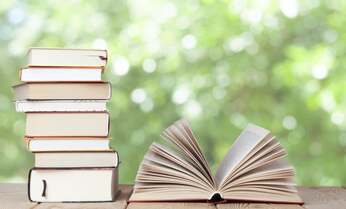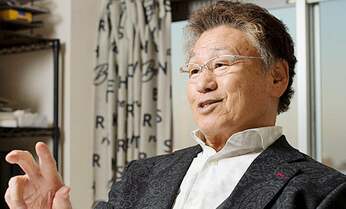「さらば青春の光」個人事務所で前代未聞の“ぼろ儲け”の真相
「さらば青春の光」の森田哲矢(左)と東ブクロ
最近、お笑いコンビ・さらば青春の光の勢いがすごい。各局のバラエティー番組に引っ張りだこで、11月からはテレビ東京系でMCを務める番組も始まった。22日放送予定の関西ローカルのバラエティー特番の収録で森田哲矢(41)は「ひと言でいえば儲かりました」と述べ、個人事務所「ザ・森東」の業績は順調だと語っている。
2008年に森田と東ブクロ(37)が結成したさらば青春の光は、2013年に所属していた松竹芸能を退社。フリー芸人として東京進出し、その後自ら事務所を興した。キングオブコントをはじめとする賞レースで結果を残しつつ、気づけばテレビでも引く手あまたの存在に。最近でも『あちこちオードリー』(テレビ東京、11月2日放送)に出演した際、「こんだけ働いても(年収が)億いかないってなると、メンタルは削られます」と発言し、話題になった。この発言の真意について、民放バラエティー番組のプロデューサーはこう明かす。
「この年収発言は業界内でも話題になりましたが、要は『ちゃんとした事務所なら億越えするほどの出演本数なのに、まだ働かないといけないのか』という思いなのでしょう。彼らの個人事務所のギャラ配分は、マネージャーと3等分というのは有名な話。しかも小さい個人事務所ですから足元を見られやすく、ギャラ交渉もできない。森田さんいわく、『テレビでギャラ交渉をしても3万が5万に上がるだけ。だったらすべて言い値でやって、テレビ露出を増やしたい』という戦略を取っているそうです、今のテレビ業界はお金がないですから、安くてうまい森田さんにオファーが殺到するのは当然といえば当然。彼らの場合、YouTubeが好調なので、テレビで知名度を上げてYouTubeや単独ライブの動員の集客につなげる考えなんです」
現在、YouTubeは6チャンネルも運営。メインチャンネルは登録者数85万人を突破し、彼らの主戦場としてしっかり機能している。
「6チャンネルをあわせると150万人ほどの登録者数になりますから、YouTubeだけでおそらく年間5000万円前後の売り上げになる計算です。相当成功している部類でしょう。彼らのチャンネルの魅力は『地上波では絶対にできない』ことを全力でやっているということ。『屁をこける女性をTwitterで募集 屁こきダービー』『東ブクロの私生活をGPSでガチ追跡』『GPS追跡風俗』など、テレビの企画会議には危なくてあげられないようなものばかり。当然リスクはありますが、YouTubeなので炎上覚悟でやれますし、個人事務所なのでスレスレの企画もノリで通してしまう。YouTubeとはいえ、大手芸能事務所所属ならばここまで下品なものはOKが出ない。なので、他の芸人は羨望(せんぼう)のまなざしで彼らを見ていて、コンプライアンスという重荷に苦しんでいる若いディレクターもまた憧れてしまう。予算も削られ、自由度も低くなり、『面白くなくなった』と言われて久しいテレビのカウンターとして、彼らの芸風が求められているのだと思います」
とはいえ、「本人たちは現状には満足してないはずだ」と言うのは、バラエティー番組を多く手掛ける放送作家だ。
「YouTubeでは過激なことをやればやるほどバズりますが、彼らはあくまでも“昔の深夜番組”くらいのレベルにとどめており、そのバランス感覚はお見事です。それがここまで人気コンテンツになるのだから、テレビ離れの恩恵を最も受けているのは、このコンビかもしれません。とはいえ、彼らはコントで世に出てきた芸人。『キングオブコント』では6回も決勝に進出しています。無冠のまま2018年に自ら卒業しましたが、やはり忸怩たる思いはあるでしょう。しかし、賞レースを自ら卒業したことでテレビ露出が増えたとも言える。今後、彼らのコントが単独ライブでしか見られない状況になれば、当然ライブの動員は増えるはずです。そのラインを狙っているのかもしれません」
■東ブクロの次なる醜聞対策もバッチリ!?
そんな彼らにも“弱点”はある。東ブクロは2013年に先輩芸人の妻との不倫スキャンダルを起こし、昨年も週刊誌で複数の元彼女に対し、中絶をさせていたと報じられた。
「最大のネックは、東ブクロさんがいつスキャンダルを起こしてもおかしくないこと。自ら女性好きを公言し、下半身にだらしないことをネタにしていますが、昨年の中絶スキャンダルでは収録したバラエティー番組がお蔵入りになるなど、実害も出ています。今春からようやくコンビでのテレビ出演がかないましたが、各局はかなり警戒しています。今、地上波のバラエティーに出るとき、森田さんは『スキャンダルがいつあっても編集しやすいように』と東ブクロを一番端に座らせるようお願いしているといいます。戦略家の森田さんだからこそ、リスクの高い相方自体を武器にしている面がありますが、次に大きなスキャンダルが出たときどうなるかは心配ですね」(前出の放送作家)
お笑い評論家のラリー遠田氏はこう述べる。
「さらば青春の光は、もともとネタに定評があり『キングオブコント』では前人未到の6回の決勝進出という記録を持っています。ネタ作りを得意としているだけでなく、トーク力や演技力、企画力にも秀でていて、YouTubeでも笑える企画を量産しています。彼らは何よりもまず“面白さ”という一点で突出しているからこそ、芸人や業界関係者、お笑いファンから一目置かれているのです。さらに言えば、大手事務所からの独立騒動、東ブクロさんの女性スキャンダルなどの逆風があっても、それを逆手に取って開き直ることで、独特のポジションを確立することにも成功しました。東ブクロさんだけでなく、森田さんも女性好き、風俗好き、ゴシップ好きのゲスいキャラクターをあえて前面に出すことで、そういう路線の仕事を総取りしています。転んでもただでは起きない“雑草魂”を持っていることが彼らの強みでしょう」
スキャンダルという“爆弾”を抱えながらも、徹底的に面白い笑いを追求していこうとする姿勢が、多くの人に支持されているのかもしれない。(藤原三星)