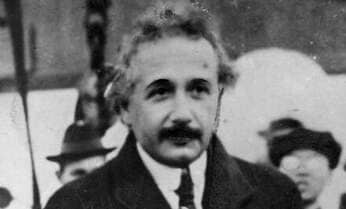半身不随の愛猫はハンデがあってもキャットタワーをすいすい お転婆娘と飼い主が描く将来とは?
足に障害があるピリカ(右)と小町(左)、つや姫(上)の“お米軍団”(提供)
飼い主さんの目線で猫のストーリーを紡ぐ連載「猫をたずねて三千里」。今回ご紹介するのは、東京都在住の40代の北村環奈さんのお話です。2匹の先住犬と暮らしていた北村さんは、動物愛護団体でのボランティア活動を機に、人生で初めて猫を家族に迎えました。同時に3匹、しかも1匹は足に障害のある猫です。日々世話に追われながらも、“無敵の可愛さ”に癒されているといいます。将来の夢も含め、大事な存在について語ってもらいました。
* * *
子どもの頃からいろいろな動物と暮らしてきましたが、なぜか、猫と暮らす縁がなかったんです。そんな私のもとに女子猫3匹がやってきたのは、昨年12月24日、クリスマスイブでした。まさに、クリスマスプレゼント、という感じです。
名前は「(ゆめ)ピリカ」(1歳2カ月)、「(秋田)小町」(推定2歳)、「つや姫」(推定3~4歳)。みんなお米の銘柄の名にしたので、“お米軍団”と呼んでいます(笑)。「ピリカ」は、アイヌ語で「美しい」とか「きれい」というような意味ですが、『Pirka』いうタイトルの写真集を以前に見て感銘を受け、そこから名づけた経緯もあります。
お米軍団と初めて会ったのは、昨年8月。体調を崩して仕事を辞めていたのですが、少し時間ができたので動物愛護団体で保護猫のボランティアを始めたんです。トイレ回りの掃除をしたり、ごはんをあげたり、一緒に遊んだり。ミルク猫への哺乳も経験しました。
ボランティアを始めた当初、シェルターには成猫と子猫が30匹以上いました。子どもの頃に野良猫にごはんをあげたことはありますが、シェルターにきて猫ときちんと触れ合い、喉を鳴らすあの音を聞きました。「これがあのグルグルか。猫によって音色や大きさも違うのだな」と新鮮に思ったものです。
ピリカの愛らしい赤ちゃん時代(提供)
ボランティアを続けているうちに、子猫の里親が次々に決まり、卒業していきました。でも1匹、誰よりも可愛くてやんちゃな子猫の家族が決まりません。実は両方の後ろ足がマヒして引きずるように歩き、トイレも人の手を借りないとうまくできないハンディキャップがあり、初めから団体が里親募集をしていなかったのです。それが、「ピリカ」です。
仲良し親子の小町(上)とピリカ(提供)
■普通の幸せを感じてほしい
「ピリカ」は母猫「小町」が“馬小屋”で産んだ子猫で、発見された時にはすでに下半身不随だったそう。馬が蹴ってしまったかわかりませんが、何か事故があったのかもしれません。
兄妹や他の子猫の卒業がどんどん決まるなか、残ってしまった「ピリカ」を見て、私は「この子にも普通の家庭で幸せになってほしい」「うちに来たらいいなあ」と、思うようになりました。背中に大きなハートのある「ピリカ」のことが、会うたび好きになりました。
私には、もう一匹、気になる猫がいました。白黒のくっきりした顔で体に牛のような模様がある「つや姫」です。そもそも成猫はもらわれにくいのですが、スタッフは「強面のお顔だから決まらないのかも」と推測していました。でも「つや姫」はかっこいいのです。
毛色はモダンな着物柄のようで、性格は親分肌。子猫がご飯を食べ終わるまで待っているし、オス猫には強めの猫パンチを浴びせたり、シェルターにいる大型犬に立ち向かったりする。そんな「つや姫」は、「ピリカ」と「小町」親子と気が合うようでした。
親分肌のつや姫(提供)
11月末頃、「小町」を希望する家が見つかり、トライアルに出ることになりました。その間に私は「ピリカ」と「つや姫」を家で預かりたいと思い、団体の代表に話をしました。預かれば、新たな猫をシェルターにいれ、里親に出すチャンスも増えます。そうこうしているうちに、「小町」が「家に慣れない」という理由でトライアル先から戻ってきたので、合流して、結局3匹がイブに家にやってくることになったんです。
もし我が家に慣れたら、預かりでなくいずれうちの子にという思いがあり、団体の方々も背中を押してくれました。そうして今年2月、“正式”に3匹が我が家の猫になりました。
真剣に遊ぶ姿も可愛らしい(提供)
■楽しい毎日には朝晩の圧迫排尿も
2階の夫の部屋を猫部屋にして、階下の犬と生活を分け、ドアの前には脱走防止柵とビデオカメラ、キャットタワーも設置しました。
犬ほどべったり甘えてこないけれど、遠慮がちにすりすり体を付けて、喉を鳴らしてくれる。みんな遊び好きで、猫じゃらしを振ると、一人ずつ順番待ち。たまに我慢できずに割り込む子もいたりして(笑)、全力で遊ぶのが面白く可愛いと思いました。
仲良く遊ぶ3匹、ケンカは一度もない(提供)
3匹の関係は良好で、家に来てからケンカは一度もありません。プロレスはしますけどね。「小町」と「つや姫」がレスリング中、ピリカは参加せずに、物陰からじーっと見ています。
かと思うと、「ピリカ」にはあざといところもあり、私が「小町」と「つや姫」を撫でていると、後ろで“ばたっ”と音がして。ふりむいたら、「ピリカ」が仰向けになっていて。「ここにいるよ」と気を引こうとして、わざと視界に入らない場所で倒れて(笑)。
ごはんも3匹一緒に。ピリカ(中央)の背にはハートマークがある(提供)
「ピリカ」も「小町」も「つや姫」を頼っている面があります。みんなの首輪を作るため、まず「小町」の首を計測しようとしたら、怖かったのか私に初めて「シャー!」。「小町」は言いつけるように「つや姫」のところにいったのですが、「つや姫」は「お母さんに向かって何してんだ」とでも言うように、ぽかんと「小町」の頭を叩いたんです。賢い!と思いましたね。
楽しい反面、大変なこともあります。
階下の犬の世話(腎臓を患って毎食手作りごはんの準備と一日おきに捕液)をしているし、散歩もあるし、そこにピリカの朝晩の圧迫排尿と排便とが加わったのですから。
圧迫排尿は、「ピリカ」にとって命綱のようなもの。しないと尿毒症になって死んでしまいます。水風船のような膀胱を外から探り、絞って尿を出します。私は立て膝をつき、「ピリカ」のお腹に手を当て、優しく均等に包み込むように絞ります。やり方は団体で習ってきましたが、「ここが膀胱ね」と自信を持って排尿させるまで、相当時間がかかりました。そして同じように、腸を押して圧迫排便をします。
ピリカはお転婆さん(提供)
「ピリカ」は布のパンツを履いています。紙のオムツだとかぶれるし、脱げてしまうので、犬の介護用パンツを作っている方に“特注”しました。パンツは8枚あって、手洗いしては干しています。勝負パンツはピンク色です(笑)
こんなふうにやることが増えて、体は前より疲れる。けれど気持ちは充実。無敵の可愛さですから!
■お転婆すぎて足を骨折
子猫だったピリカの成長は目覚ましく、わが家に来て逞しさが増したように思います。前足だけですいすい、すばやく忍者のように進みます。本人はそのハンディキャップをものともせず、ボルダリング選手みたいにキャットタワーを昇るので、肩周りと前足はムキムキ。
まるでアスリートのようにキャットタワーをのぼるピリカ(提供)
でも実は5月に、高所から落ちたのか後ろ足を骨折してしまったんです。本人には痛みの感覚はないのですが、パンツを履かせる時に違和感があり、慌てて動物病院へいきました。すぐに、キャットタワーも解体し、低い部分だけにしました。
澄んだ目がきれいなピリカ(提供)
最初にいった病院では、いずれ何かあれば断脚するという話も出たのですが、団体の代表がセカンドオピニオンで他の病院に連れていってくれて、ギプスを付けることになりました。6月にレントゲン検査をしたら、順調に新しい骨ができてくっついてきているとのこと。一カ月もすればギプスが取れるだろうと言われているので、あと少しです!
猫たちが来て半年以上が経ちましたが、SNSで写真を見た方や団体の方に「猫が楽しそう」「幸せそう」といわれると、我が家に迎えてよかったなと、嬉しくなります。もちろんこれからも、怪我のないよう見守りたいと思います。どうか、お転婆もほどほどに。
■ペットと描く将来の夢
並んで外をながめる3匹(提供)
今は犬の看病のため休職中の私ですが、じつはもともと看護師として長くリハビリテーション病院で働いていました。その後、ペットと入居できる有料老人ホームに勤め、愛犬を連れて出勤すると、皆さんに喜んでもらえるという経験をしました。
一方で、高齢の飼い主さんが入院や施設入居をすると、行き場をなくしてしまうペットの話を聞いて、どうしたものかと前から気にかかっていました。愛護団体でボランティアを始めると、高齢者からの保護が多い時期があり、その実情を肌で感じるようになりました。残されたペットも、シニアだと引き取り手が減ることも実感したんです。
本当ならば、飼い主とペットがお別れせず最期まで暮らせるのがいちばんの幸せです!(60歳を過ぎたらペットを飼わないでという意見もあるけれど、愛する動物と暮らしているほうが健康寿命が長いという分析もあります。)高齢になっても、安心してペットと暮らし続けられるシステムやサポートがあれば、多くの問題を解決できるはず……。
これは将来の私にも絶対に必要な環境なので、システムなどを自分で作りたいと思うようになり、現在、構想を練っているところです。「ピリカ」たちとの出会いが、私の夢をより明確に、強いものにしてくれたようです。出会えてよかった、心からそう思います。
(水野マルコ)
【猫と飼い主さん募集】「猫をたずねて三千里」は猫好きの読者とともに作り上げる連載です。編集部と一緒にあなたの飼い猫のストーリーを紡ぎませんか? 2匹の猫のお母さんでもある、ペット取材歴25年の水野マルコ記者が飼い主さんから話を聞いて、飼い主さんの目線で、猫との出会いから今までの物語をつづります。虹の橋を渡った子のお話も大歓迎です。ぜひ、あなたと猫の物語を教えてください。記事中、飼い主さんの名前は仮名でもOKです。飼い猫の簡単な紹介、お住まいの地域(都道府県)とともにこちらにご連絡ください。nekosanzenri@asahi.com