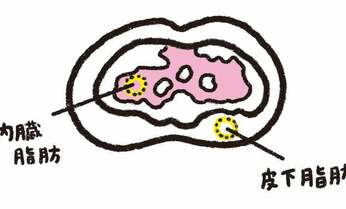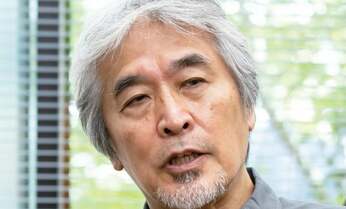勝間和代「湯水のようにお金を使っても幸せになれない」お金はなんのためにある?
最新刊は『100歳時代の勝間式人生戦略ハック100』(撮影/張 溢文)
勝間和代さんの好評連載、第6回のテーマは「お金は人生の選択肢を増やすためにある」。アエラ増刊「AERA Money 2023春夏号」より。
こんにちは、勝間和代です。こちらのコラムでは、お金の上手な稼ぎ方や使い方を知ることで、人生を豊かにするための「レシピ」について書いています。
今回のテーマは「お金は人生の選択肢を増やすためにある」です。お金を持っていれば「自分で選べること」が増える、これが一番のメリットだと私は考えます。
「今、やりたいと思ったこと」があるとしましょう。ある程度、お金に余裕があれば「今、やりたいと思ったこと」を実現できる可能性は広がります。自分のやりたいことが次から次へとかなえられたら幸せですよね。
とはいえ、それは湯水のようにお金を使えば幸せになるという話ではありません。
「常に高級な店で食べ、高級な宿に泊まれば幸せになれるか」について考えてみましょう。
私は無駄遣いが好きではないこともあり、チェーン店によく行きます。日本そばの「ゆで太郎」やイタリアンの「サイゼリヤ」、スイーツの「ミスタードーナツ」が大好きです。廉価なホテルチェーン「スーパーホテル」にも泊まります。
でも、高い店で食べ、高い宿に泊まるお金が財布に入っていないわけではありません。私がわざわざチェーン店を選ぶ理由は、どこにあるのでしょうか。答えはこうです。
「自分が高い店、宿を選びたいときは、もちろんそうしている。でもコストパフォーマンスを考えて、あえてチェーン店を選ぶときもある。そのほうが、自分がいろいろな面で快適に過ごせるから」
お金がないから「仕方なく」チェーン店を選んでいるのではなく、「自分の意思で」店やホテルを選んでいるわけです。そのことが、私の喜びや快適さにつながっているのだと思います。
私たちは、自分の力だけで自分の暮らしのすべてをまかなうことはできません。何らかの形で人の力を借りることになります。
そして家族や友人「以外」からの力を借りるときには、お金が必要になります。お金を多めに持っていれば、「どの人(会社)のどの力をいくらで借りるか」ということを自由に選べるようになります。
スーパーへ買い物に行き、夕飯に使う野菜を買うときの場合で考えてみましょう。
・見切り品、または特売品の野菜「しか」買えないのか
・オーガニック野菜まで含めて、いろいろな選択肢の中で「自分の中で最もバランスがいいもの」を買えるのか
自分の都合に合わせてどちらからでも選べるほうが、日常的に行くスーパーでも満足度は変わります。常に、値段が高いオーガニック野菜だけを買う必要はないということも重要なポイントです。
人との付き合いに関しても、お金がないと細かい面で不自由になるかもしれません。食事や旅行に誘われたとき、持ち合わせがさみしかったらどうでしょう。
本当はお金を理由に断りたいのですが、「お金がないから行けません」とは自尊心の面でなかなか言えない人も多いと思います。結局、他の予定が……などと違う理由をこじつけて断ることになります。
住宅ローンや車のローンなど一点集中型の高いローンを組むことを私が勧めないのは、自分の可処分所得(自分の収入のうち税金などを引いた手取り)の中で、あまりにも配分の高い項目ができてしまうと、それ以外の選択肢が狭まるからです。
よく聞くのが「身の丈に合わない住宅ローンを組んだため、他にほとんどお金が使えなくなる」というケースです。
子どもの小遣いが減ったり、家族旅行に行けなくなったり。結果、子どもも含めて人付き合いが不自由になることもあります。
最終的に自宅は残りますが、過度な節約生活は子どもの成長にいい影響を与えないのではないでしょうか。
「収入は安くても、やりがいがあればいい」という考え方も、程度問題です。あまりに低賃金で働き続けると、自分の将来の選択肢を削ってしまいます。
なるべく上手にお金を稼ぎましょう。そしていろいろな選択肢の中で、無駄遣いせずにコストパフォーマンスを考えながら消費するイメージを持ってください。そうすれば、お金に振り回されなくなります。
◯勝間和代(かつま・かずよ)/経済評論家、中央大学ビジネススクール客員教授。1968年、東京生まれ。早稲田大学ファイナンスMBA(経営学修士)、慶應義塾大学商学部卒業。当時、最年少の19歳で会計士補の資格を取得。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。スキルアップや起業、出版などをサポートする「勝間塾」や無料メルマガが大人気。ツイッターのフォロワー数75万人超。著作の累計発行部数は500万部を突破
構成/中島晶子(編集部)
※『AERA Money 2023春夏号』から抜粋