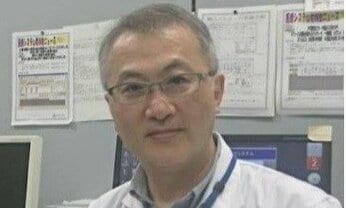「岸田政権は正気の沙汰とは思えません」森永卓郎氏 ガソリン「トリガー条項」発動ナシは誰の都合?
岸田文雄首相
ガソリン価格が高騰している。SNSなどではガソリン税を軽減する「トリガー条項」に踏み切るべきという声が上がるが、政府は比較的効果が少ない「ガソリン補助金」で対応することを決めた。背景にはどんな考えがあるのか。経済アナリストの森永卓郎さんに聞いた。
――トリガー条項に踏み切らない政府の背景にはどういった事情があるのでしょうか。
トリガー条項を発動させない理由は二つあると見ています。一つは、岸田文雄首相は予算をなるべく使いたくないという財務省の考えに染まっているのでしょう。岸田首相率いる自民党「宏池会(岸田派)」は、大蔵省(現財務省)出身者が多い。
今回、延長が決まった、石油元売り各社への補助金の内容は、レギュラーガソリンの場合、9月7日から年末までは、1リットルあたり185円を超えた部分は全額補助。一方で、168円から185円までの部分は10月4日までは30%、10月5日から年末までは60%を補助します。全国平均で175円程度を目指すとしています。
しかし、去年の夏まで実施していたガソリン補助は、168円以上になれば、最大補助額35円、さらなる超過分も50%を補助するという内容でした。これに比べれば、今回の補助はだいぶ絞ったことがわかります。
今回のガソリン補助金はは昨年度(22年度)の第二次補正予算から出すとしています。つまり、昨年度の二次補正予算をこれまで使ってきましたが、2兆円ほど残っており、その残りで済まそうとしているということです。
【こちらもおすすめ!】
処理水放出で相次ぐ迷惑電話は「中国の工作」と外交の専門家 背景に「包囲網」への不満か
https://dot.asahi.com/articles/-/200036
ちなみに23年度の補正予算は予備費として5.5兆円計上されており、その内4兆円が新型コロナ対策や原油・物価高対策を目的にしたものになっています。こちらには手をつけないということです。
昨年度予算の範囲内でやるから限界がある。逆算するとこの程度の補助しかできないということです。
トリガー条項を発動させてないもう一つの理由は、財務省の利権にかかわるからですね。
税金として徴収し、それを補助金として元売りなどにばら撒くことで、利権が生まれる構造があります。財務省としては税収も減り、利権にもつながらないトリガー条項の発動をやろうなどとは絶対に思わないでしょう。
――国民の生活が厳しくなっているなか、岸田首相の経済政策についてはどう見ていますか。
いま岸田政権は激しい緊縮財政を敷いています。安倍政権のときの2020年度の基礎的財政収支は80.4兆円の赤字でした。積極財政をしていたということです。その後、政府は赤字額を大きく減らしていまして、今年度予算の基礎的財政収支は10.8兆円の赤字にまで減っています。
赤字を減らすと聞くと、良いことのようにも聞こえますが、ここで意味するところは、景気が悪くなっているときに、政府は支出を切り詰めているということです。安倍政権と比較すると岸田政権は70兆円も支出が少なく、これは国の1年分の収入と匹敵する額です。
背景にあるのは財務省の思想です。財務省は「日本は借金まみれ」のような印象を与える主張をしています。しかし、それは間違いです。財務省が発表している20年度の政府の連結貸借対照表を見ると、1661兆円の負債がありますが、資産も1121兆円あります。差し引き540兆円の借金となります。ただ、日銀が保有する資産と負債もあわせて考えると、日本の借金はわずか8兆円になります。今年度末には借金がゼロになって、黒字になっている可能性が高いです。
それにもかかわらず、国民にお金を出さず、逆に増税する岸田政権は異常です。正気の沙汰とは思えません。岸田首相の判断は冷静な経済的、財政的判断ではなく、「財政を均衡させてなくてはいけない」という「財務省の教義」に捕らわれているのだと思います。
経済が厳しく景気をよくしていく必要がある中で緊縮財政を実施するなど経済政策としてあり得ません。財務省の主張はもはやカルトです。私は財務省のことを「ザイム真理教」と呼んでいます。
――トリガー条項を発動すると国民の生活に混乱が生じる、というのが政府の立場のようです。
混乱なんて生じるわけありません。ルール通りにやればいいだけです。トリガー条項は、レギュラーガソリンの1リッターあたりの価格が160円を3ヶ月連続で超えたら、臨時増税分の25.1円の課税を止め、価格を下げる。そして、130円を3か月連続で下回れば、課税を戻すというとてもシンプルなルールです。混乱のしようがありません。
混乱が生じることがあるならば、対策を講じておけばいいだけです。「混乱が生じる」という政府の答弁は9年前から同じと報道されていました。ルール通りにやっていれば、今ごろガソリン価格は、150円半ばくらいでしょう。国民もその効果を実感できたはずです。
ちなみに、9月使用分の電気・ガス料金が各社で値上がりします。政府はこれまで1キロワットあたり7円の補助金を出していましたが、9月使用分から半分の3.5円に減らします。9月に入っても暑い日が続いているので、10月にびっくりするような請求書が来ると思います。
岸田首相は「国民が効果を実感できるような物価対策を講じる」、「岸田内閣の最優先課題の一つは物価高対策」といったようなことを言っていますが、実際にやっていることは、セコイことしかしていません。
アメリカから米国製巡行ミサイル「トマホーク」を400発購入すると岸田首相は言っていましたが、それを購入するよりも、ガソリン代や電気・ガス代を下げる施策に力を入れたほうが、国民の暮らしを守ることにつながると思いますね。
――生活が苦しくなる中で、消費税減税を望む声も出ています。
私は消費税を減税することはできると思います。ゼロにすることも大丈夫だと思います。
財務省はこれまで日本が大赤字になると、国債と円が暴落し、ハイパーインフレが起きると危機感を煽ってきました。しかし、安倍政権時の20年度に80兆円の赤字を出しても国債の暴落も円の暴落も起きませんでした。私はこのことは安倍政権が実施した画期的な実験だったと思います。
――緊縮財政はこのまま続くのでしょうか。
少なくとも岸田首相がいる限りは続くでしょう。解散にいつ出るかわかりませんが、岸田首相が1年後の自民党の総裁選を乗り切ると、宏池会出身の首相の中で最長の在任期間である池田勇人元首相の1575日を抜く可能性も出てきます。岸田首相がここに色気を出し始めたら、国民の生活はより一層ボロボロになるでしょう。
安倍元首相は回顧録の中で、財務省は「省益のためなら政権を倒すことも辞さない」と批判していました。財務省の官僚は政治家に対して「ご説明」にまわっており、自分たちの教義を受け入れる信者を増やしています。自民党に限らず、立憲や共産党といった野党も信じている、メディアも国民も信じている状況です。
やはり国民の怒りがもっと高まらないといけないと思います。もし「日本は借金だらけで増税もしかたない」「いま減税できないのも仕方ない」などと思っているようであれば、それは財務省の教義に洗脳されています。早く目を覚ますべきだと思います。
(AERA dot.編集部・吉崎洋夫)