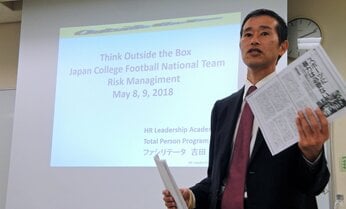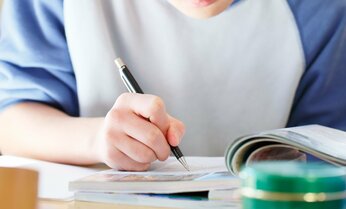中日は今や最も“入りたくない球団”に? 根尾の育成方針ブレブレ “お金ない”イメージも
中日・根尾昂
中日は過去10年間でAクラスは1度(2020年に3位)だけと苦しんでいるが、低迷期を脱出するために欠かせないのが若手の成長だ。
だが、有望な若手は多いものの、思ったように育ってこず「良い素材が中日に入団しても伸び悩んでしまう」と語るアマチュア球界関係者がいるほど。また、その他の要因も絡み最近ではドラフト候補の選手たちに中日が“不人気”になっているという声もある。
これからのチーム浮上のため、そしてドラフト候補に対する悪いイメージ払拭のため、選手の育つ環境があるところを見せておきたいところだが……。
若手が成長しない球団というイメージの象徴となってしまっている選手が、2018年のドラフトで4球団競合の末に入団した根尾昂だ。
「鳴り物入りでのプロ入りから鳴かず飛ばずの状態が続き『根尾も中日ではダメか』という雰囲気が出始めた。以前から若手の周辺環境に問題があるという声も聞こえる」(在京球団編成担当)
色々と若手が伸び悩む原因は考えられるが、根尾の場合よく挙げられるのはブレてしまった育成プランだ。
根尾は高校時代は投手としての評価も高かったが、プロ入り後は遊撃手一本に絞ってプレーすることを決意。だが、外野手へコンバートされるなどポジションが定まらず、昨年途中からは投手へ転向となった。球団の育成方針がコロコロと変わってしまったことが成長を阻害したとも考えられる。
「監督が交代した時期に入団したことも良くなかった。歴史を見ても中日の監督選びは球団内の力関係の構図そのもの。監督が代われば編成、強化を含めて体制が一変してしまう。根尾に関しても育成方針がブレてしまった」(名古屋在住スポーツライター)
【おすすめ記事】
勝てないだけが理由じゃない なぜ中日ファンは「ナゴヤドーム」に行かないのか
https://dot.asahi.com/articles/-/85039
与田剛前監督は投手としての可能性に見切りをつけ野手に専念させるつもりだった。しかし昨年就任した立浪和義監督は投手としての才能を以前から高く評価している。野球選手として最も伸び盛りの時期にどっちつかずならば、「成長しろ」と言っても難しい部分は当然あるはずだ。
根尾の他にも、石川昂弥、鵜飼航丞、ブライト健太らドラフト上位で入った選手たちの飛躍が今後期待されるが、中日は若手の成長を阻む“誘惑”があるチームとしても知られている。
「タニマチによる夜の接待が多いのは、阪神だけではない。中日も二軍クラスであっても地元で英雄扱いされ、連れ回して面倒を見たい人は多い。若手選手の伸び悩みやチーム全体の甘さに繋がっているという人は多い」(中日担当記者)
「名古屋は土地柄、見栄を張りたがる人が多い。中日の選手と知り合いならば大きなステータスとなる。またナゴヤ球場に隣接する選手寮は繁華街から近くて遊びに出やすい。一軍本拠地が市内から遠くて不平が多いだけに皮肉を感じる」(中日担当記者)
根尾に関しては“私生活”の部分に心配はないようで、「一人暮らしを始めて彼女もいるらしく、腰を落ち着けて野球に専念できている。素晴らしいセンスの持ち主だから、野球のみに集中して1日も早く一軍のローテーション投手になって欲しい」(中日OB)という声もあるが、グラウンド外の環境も新たに入団する選手にとって重要な要素の一つだろう。
また、中日はリーグ優勝9度を誇る名門球団ではあるが、長期の低迷期に入り、今や“弱小球団”のイメージも定着しつつある。
「今の若い選手は現実的なので中日へのイメージは両極端。弱い球団だから入りたくない選手がいれば、早い段階からレギュラーになれるチャンスと捉える選手もいる。球団スカウトは今まで以上に(入団前の)選手の本音を確認する必要がある」(在京球団編成担当)
そして近年は補強費を抑えているイメージもあり、資金力が豊富ではないという印象がどうしてもつきまとう。活躍した選手には“大盤振る舞い”をするソフトバンクとは対極的な存在だ。まだ成長段階の若手が多いこともあるが、今年の球団別の平均年俸はセ・リーグで最下位(全体では11位)となっている。
「球団自体は何とか回せているものの親会社の中日新聞社の経営が厳しい。新聞産業が斜陽な中、同業他社と同様に不動産ビジネスに本腰を入れ始めた。球団に投入する資金は限られており多額のお金は使えない。大型補強や大判振る舞いは今後も難しいだろう」(中日担当記者)
とはいえ、ドラフトで入る球団は選ぶことはできない。今ではフリーエージェント(FA)やメジャーへの移籍があるため、そこへ向けて中日で頑張ればよい話でもある。中日もそういった選手を後押しできる環境を揃えることで“入りたい球団”になることもできるだろう。
「希望球団があっても最後は本人次第。プロは試合に出続け、チームが上位争いできるように貢献することが重要。給料は上がり、FAなどで他球団やメジャーリーグに挑戦もできる。しっかり野球に取り組んで勝つしかない。中日に最も足りていない部分」(中日OB)
今年も昨年に続き最下位争いとなってしまっている中日だが、立浪監督のもとでチームが強くなることを待ち望んでいる名古屋のファンは多い。そのためには若手が成長する以外に道はない。彼らが活躍して強くなれば、チームのイメージも大きく変わり、入りたくない球団から入りたい球団に変わるはずだ。