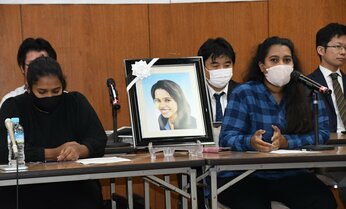「健康コスパ」ヨーグルトでより「腸活」に効果的なのは? 管理栄養士浅野まみこさんに聞いた
浅野まみこ(あさの・まみこ)/クリニックや企業での栄養相談の経験を生かし、食育活動やレシピ開発、食のコンサルティングなど多方面で活躍中(写真:本人提供)
消費に関する価値観としてコスパやタイパが重視される時代。管理栄養士の浅野まみこさんは、食の選択基準である「健康コスパ」を提唱する。AERA 2023年10月9日号より。
* * *
コスパやタイパもいいけど、食の選択基準には「健康コスパ」を──。今年4月からそう提唱しているのは各メディアで引っ張りだこの管理栄養士、浅野まみこさんだ。
健康コスパとは、「健康を軸にコストパフォーマンスを見る」という概念。食品の栄養素に特化して着目し、含まれる栄養素などからカラダへの価値やメリットがどのくらいあるのかを表す指標だ。一般社団法人「ウェルネス総合研究所」も注目し、普及啓発に取り組んでいる。
コスパ重視の時代こそ
健康コスパの意義について浅野さんはこう話す。
「コスパやタイパというキーワードが注目されていますが、食品を選ぶ際にはそれだけではベストな効果を得られません。健康維持を図る上で最も大切な栄養バランスも意識して食品を選択する習慣をぜひ身に付けていただきたいと思いました」
なぜなら、「食べる」ことの最大のメリットはカラダに必要な栄養素を取り込み、健康を維持することにあるからだ。ところが、この当然ともいえる価値基準がかすみがちなのも否めない。スーパーでもネット通販でも、安価な商品は価格表示を見れば一目瞭然。「見た目」においしそうな食品はあふれている。調理の手間がかからない総菜やサプリもコンビニで手軽に買える。食品の物価高も相まってコスパに目が向きがちだが、だからといって、安価で調理が簡単な食品ばかり口にして体調を崩せば元も子もない。「コスパが重視される時代だからこそ、目に見えない『健康コスパ』に注目してもらいたい」という浅野さんの主張に思わず、ハッとさせられる。
厚生労働省は日本人の理想的な食事の栄養バランスとして、一日に必要なエネルギーの13~20%をたんぱく質から、20~30%を脂質から、50~65%を炭水化物から摂取することを推奨している。食品のパッケージにはこれらの栄養成分が表示されている。原材料も、多く含まれる順に記載され、添加物やアレルギー表示も記載されている。とはいえ、一品一品、栄養素や原材料を調べて足し算しながら買い物するのも疲れる。そこで、実生活ですぐに役立ちそうな、日常でよく使う食品の比較や選択方法を浅野さんに手ほどきしてもらった。
AERA 2023年10月9日号より(写真:ウェルネス総合研究所提供)
まずはヨーグルトから。「腸にいい食品」というイメージが強いが、どのヨーグルトも健康効果は同じかといえば、そうではないという。
「乳酸菌、ビフィズス菌など含有している菌の特性によって健康効果は変わります」(浅野さん)
実はヨーグルトには、「乳酸菌のみのヨーグルト」と「乳酸菌+ビフィズス菌入りのヨーグルト」があり、健康コスパに差があるという。乳酸菌、ビフィズス菌のいずれも整腸作用が期待できるのは同じ。だが、「乳酸」を作り出す乳酸菌は主に小腸で作用するのに対し、ビフィズス菌は主に大腸で働き、乳酸だけでなく、短鎖脂肪酸の一つである「酢酸」を作り出す。酢酸は口から摂取すると胃腸で消化吸収されてしまうが、ビフィズス菌により大腸で生み出すことで「酢酸」が大腸で腸内環境改善に効果を発揮する、と浅野さんは強調する。
「腸活」に効果的なのは
「通常、『腸活』と言われているのは大腸の腸内細菌を整えることを指しています。ビフィズス菌を摂取すると、大腸で新しい栄養素が生まれ、乳酸菌単体よりも効果的な働きをしてくれます」
ビフィズス菌によって作られる短鎖脂肪酸は大腸のぜん動運動を活発にするほか、脂肪の蓄積の抑制や肥満、糖尿病の予防への効果が期待できる。また、免疫機能にも関与している。したがって、「乳酸菌+ビフィズス菌入りヨーグルト」のほうが、「乳酸菌のみ」より健康コスパは高くなる、というわけだ。「ビフィズス菌入り」のヨーグルトは、たいてい商品パッケージの目立つ位置に大きく表示されている。このため菌の効能に関する知識さえあれば、容易に違いを見極められるのがうれしい。
次に、ツナ缶とサバ缶を比較しよう。魚の缶詰の中でも使い勝手のいいツナ缶とサバ缶は好みやメニュー、価格でなんとなく選んでしまうことが多いが、これも栄養価で見ると意外に大きな差があるという。
大きな差はないけれど
ツナ缶(びんながマグロ水煮フレーク)とサバ缶(水煮)を100グラムあたりで比べると、DHA(ドコサヘキサエン酸)はツナ缶が440ミリグラム、サバ缶は1300ミリグラムと、サバ缶が約3倍。EPA(エイコサペンタエン酸)はツナ缶110ミリグラムに対し、サバ缶が930ミリグラムと、サバ缶が8.5倍も多い。DHAやEPAは生活習慣病や動脈硬化、認知症の予防などに効果が期待できる。浅野さんは言う。
「これは外せません。なぜかと言うと、今の日本人は魚の摂取量が少ない上、DHAやEPAの摂取量が少ないからです。これらを手軽に取るのにサバ缶は最適な食品なのです」
最後は豆腐。木綿豆腐と絹ごし豆腐は硬さだけでなく、栄養価にも違いがあると知る人はそう多くないだろう。着眼点は製法の違いだ。木綿豆腐は大豆をゆでて絞った豆乳をにがり(凝固剤)で固めたものを型に入れ、圧力をかけて水分を搾り押し固めて作る。一方、絹ごし豆腐は、豆乳ににがりを加えてそのまま固める。水分を抜いて凝縮して作る木綿豆腐は、たんぱく質やカルシウムなどの大豆本来の栄養素が多く含まれ、絹ごし豆腐に比べて全体的に少しずつ栄養価が高い。反対に水分量が多い絹ごし豆腐は、栄養価はやや下がるが、カロリーが低く、カリウムが多いのが特徴という。
「栄養面での大きな差はありませんが、より多く栄養素を含んでいるという点では、木綿豆腐のほうが、少しだけ健康コスパが高いといえます」(浅野さん)
コロナ禍による環境の変化などで健康意識が高まっている今だからこそ、同じ価格や似たような食品ならできるだけカラダに良いものを選びたいというニーズも高まっている。浅野さんはそう考え、健康コスパを提唱した。
自分にとってベストな食品とは何か。効率だけではない、日々の選択の積み重ねがものを言う。健康は一日にして成らず。肝に銘じたい。(編集部・渡辺豪)
※AERA 2023年10月9日号