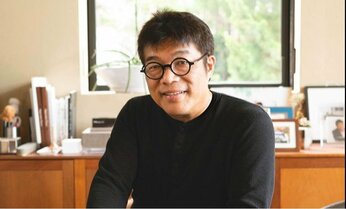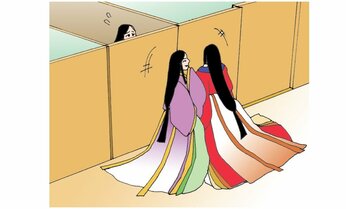伊藤かずえ「30年もののシーマ」レストアの舞台裏 メカニックがつぶやいた一言とは
伊藤かずえ/1966年神奈川県生まれ。小学生から東映児童研修所に入所し、1979年に映画「花街の母」でデビュー。18歳の時に出演したドラマ「スクール☆ウォーズ」の富田圭子役でブレイク。2020年に、愛車である日産「シーマ」の1年点検の様子をSNSへ投稿し話題となった
日産自動車の高級セダン「セドリック」や「グロリア」の上級車種として1988(昭和63)年に発売された初代「シーマ」。バブル景気といわれる中で爆発的にヒットし、「シーマ現象」は同年の新語・流行語大賞の流行語部門・銅賞を受賞した。
このシーマに、90(平成2)年から30年以上乗り続けているのが、俳優の伊藤かずえさんだ。2020年、伊藤さんが愛車の1年点検の様子をSNSに投稿し、投稿を見たSNSユーザーから「日産はレストアを検討して!」「やっちゃえ、日産!」という声がわき起こった。その後、日産がレストアに乗り出したことは車好きには知られた話だ。
伊藤さんは、3月20日発売の『TOKYOレトロ探訪 後世に残したい昭和の情景』でインタビューに応え、シーマへのこだわりや思いの丈を語っている。本の発売を記念して、そのインタビューを公開したい。
***
シーマは、私が買った3台目の車です。3年乗った後に、買い替えようとは思ったんですが、当時、乗りたい車が他にありませんでした。
もともとの造りや素材が良かったというのもあるとは思いますが、特にシートの座り心地が気に入っていたからです。もう少し乗ろうという気になり、車検はもちろん、ことあるごとに調整をしてもらっていました。自分の中では、「ただ大切に乗ってきた」結果として、30年たったっていう感覚です。
シーマを買ったのは24歳ぐらいの時でしたが、20代前半の女性がこのセダンに!って思ったこともありました。その前は、スポーツタイプの車に乗っていたんですけど、初めてのシーマに試乗した時に、いい感じって思って、今まで乗ってきた車より、体にフィットする感じがありました。
実際に乗ってみると、大きく見えても小回りも利くし、立体駐車場で「3ナンバーは、入れません」という場所でも、ギリギリ入れちゃうんです。幅はそんなに広くないんです。今のクラウンとかと比べて全体的にコンパクトに仕上げてあるのも気に入っているところです。さらに、視界が広いので、運転しやすい。車高も低いですしね。慣れているってこともあると思いますけど。
旧車ならではと思わせてくれるスピードメーター。伊藤さんのシーマは、1988年に3桁化された「分類番号」も2桁のまま。いまや長期所有の証だ
でも、どんなに大切に扱っても、いつかは傷がつくし壊れるものです。さすがに30年たつと「塗装がまだらになってきたなぁー」って感じ始めて、だんだん気になるようになっちゃって。
そこで、全塗装してもらおうと思ってディーラーの方に相談したら、100万円ほどかかることが判明して迷いました。日産さんにお願いすると、全部ドアを外して、見えない部分も、塗装がはがれているところはやり直してくれるそうです。塗装が古くなってるってことは、エンジンやその他のパーツもガタがきているだろうと考え、遅かれ早かれ修理しなくてはならない部分が出てくるのは目に見えていました。あと2年か3年乗ったら買い替えになるだろうと予想してましたが、もう少し乗ってみて、それから考えようと思いました。
新しく買う車を探し始めてみると、欲しい車がないんです。セダンが欲しかったんですが、最近の車は馬力も上がったし、環境にも優しくなっているんだろうけど、丸っこい車体が多く、私の好みではありませんでした。セダンはやっぱりある程度カクカクしてたほうがそれっぽいなって。
そんなこんなで結局気が付いてみれば、30年も乗り続けることになりました。もちろん、それはシーマが気に入っていたからというのが一番の理由でもあります。
ちょうど30年目の点検をお願いしている時に、神奈川日産 宮前店さんに、お花をいただいたんです。「長いこと大切に乗っていただいてありがとうございます」というメッセージが添えてありました。それをボンネットに載せて、「30年たちました」ってブログに載せたら、それが反響を呼んで、いきなりすごいことになっちゃって。日産さんにもあらゆるところから連絡が来たらしく、「こんなに大切に乗っているんだから、レストアしてあげたら」って。
ブログに載せて、半年もたたないうちに、日産さんから連絡が来ました。その前に、町工場みたいなところで、安い値段でやってくれるって話もあって、そちらにお願いしていたところに、日産さんからの驚きの連絡。フルレストアでやってくれるって言っていただいて、「じゃあお願いしよう」ということになったんです。
エンジンの出力も変えてません。10万キロの時に載せ替えたんですけど、そこからでも22年たっています。だから、今回のレストアは、言ってみれば「奇麗」にしていただいた、いわば「元の状態に戻す」というレストアの本道だと思います。
今、旧車の人気が高いみたいですね。YouTubeでもよく見かけるし、値段が上がっています。いろいろな車を楽しみたいオーナーもいて、欲しい人はすぐに買い替えちゃう。そういう時代ですよね。
シーマレストア完成お披露目会の日、かけられたシートが開いた時に思わず涙が出ました。あのままでも愛着はありましたが、もともと乗ってた車が、思った以上に素敵な仕上がりで、納車したての新車の香りまで感じました。「よみがえってくれて、これからまだまだ乗れる」と思ったら感動しちゃって。細かいところまで、心を込めて作業をしていただいたからでしょう。
相棒っていう思いはあります。こんなに長く付き合っていると、魂が宿っちゃっているような感じで、私の意識とは別に、車が危ないよって、危険回避してくれる、車が勝手に危険を察知して避けてくれたんじゃないかと思う瞬間までもあります。
レストア後は、どこも擦ってないし。危ない目にも遭ってないので。物を大事にするってそういうことなのかなって、改めて感じています。私にとって、旧車に乗り続ける「意味」って特にないのですが、好きだからずっと乗っているだけなんです。
今走っていると結構目立ちますね。信号待ちでトラックの運転手さんに手を振られたり、駐車場でガン見されたりしますね。昭和ではありませんが、良き旧車です。平成2(90)年モデル(Y-31、TYPEⅡリミテッド)です。いまだに人気があって、トミカからミニカーも売られています。ミニカーには、レストアした私の車「伊藤かずえ仕様」もあります。
シーマとの長い付き合いについて話すにつれ、伊藤さんの目が輝いていく。シーマに対する熱い思いが、聞く者にダイレクトに伝わってきた
レストアをしていただいたメカニックの方に対しては、「感謝、感謝」しかありません。ホイールも、同じものをわざわざ作ってくださったり、すごく輝いているなって感じています。時々見学に行くと、メカニックの方たちも楽しんでやってくれてる雰囲気が伝わってきました。 作業の一番最後にエンブレムをつけるんですが、「これでお別れって、なんだか寂しいですね」ってメカニックの方がポツンとつぶやいたのを今でも思い出します。ついていた古いエンブレムは、フォトブックの中に入れてくれました。かけがえのない宝物です。
車に限ったことではありませんが、一昔前ならちょっと故障するとすぐに手放してしまうという傾向はあったと思います。一つのものを大切に使うのって、特に今の時代、一つの認識だと思うんです。それと、ずっと乗り続けるのが、究極のエコだとも思います。解体するにも汚染されたりするわけだし、不必要なものは、捨てなきゃいけないわけで。何でもかんでも、捨てちゃうのではなくて、車に関しても、魂が宿っているのを感じるのは、長く乗ってないと、湧いてこない気持ちだと思います。
車庫に入れて、今日はもう運転しないけど、「今日も一日ありがとうね」って声をかけて、エンジンを切るんです。
(文 今村博幸 写真 関口 純/生活・文化編集部)
【PR by 暮らしとモノ班】
超懐かしい〜♪80年代レーサーレプリカ&デートカー。本物は高いからプラモで手に入れよう
https://dot.asahi.com/articles/-/230520
令和に復刻した「昭和レトロ」にZ世代も昭和世代もメロメロ!その理由は?
https://dot.asahi.com/articles/-/230525