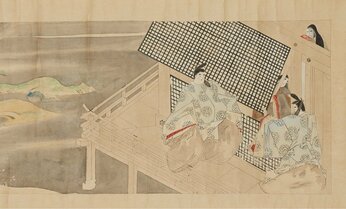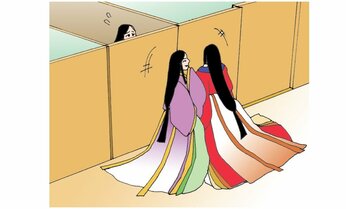小川哲「昔から野球のストライクとボールが納得いかなかった」 小説執筆に役立った理系的な脳とは
大宮エリーさんと小川哲さん[写真:本人提供(大宮さん)、写真映像部・高野楓菜(小川さん)]
作家・画家の大宮エリーさんの連載「東大ふたり同窓会」。東大卒を隠して生きてきたという大宮さんが、同窓生と語り合い、東大ってなんぼのもんかと考えます。理I出身の小川哲さんは小説の執筆は数学を解くような感覚と言います。
* * *
大宮:書きたいものって、どこから生まれてくるんですか。
小川:僕の場合は、書きたいこと、伝えたいことがあるというよりは、小説を通じて、考えてみたいことがあるっていう感じですね。こういう立場の人って何を考えてるんだろうとか、どうしてこういうことをしたんだろうとかを、小説というツールを使って考えてみたいんです。
大宮:じゃあニュースの事件から、発想したりもするんですか。
小川:そういうこともありますね。
大宮:小説の着想が湧いたときには、結構調べるんですか。それとも自分の空想で展開するんですか。
小川:調べながら書く感じですかね。ただ、調べすぎちゃうと、読者と知識量というか、視点が離れちゃうことがあって。だから、知らない人が興味を持続してくれる“距離感”みたいなのを、自分の中で適宜、調節しないといけなくて。
大宮:それでも、物語の結論を出すのは、自分じゃないですか。
小川:調べて分からないことをあれこれ考えるのも楽しいですし、調べて分かっちゃったことでも、資料にそのプロセスや理由が書いてあるわけじゃない。その人からどういうことを考えて、どういう経緯で、そこにたどり着いたのか、必要があれば考えるっていう感じですかね。
大宮:やっぱり理系的な脳が発揮されてるんですかね。東大では理Iでしたよね。
小川:どうなんですかね。小説を書く上で、論理的に矛盾しないように、というのは意識しますけど。小説を書き終わったらまた頭から読み直すわけですよね。そうすると、間違いとか、面白くないところとか、登場人物の行動がとっぴに感じられる箇所があったりして、直します。それって、数学で途中式の間違いに気づいて、全部書き直すみたいな感覚に、すごく近いです。
【こちらも話題】
直木賞作家・小川哲が大宮エリーに語った“寝ること”の重要性 「執筆は、睡眠不足でできる工程が1個もない」
https://dot.asahi.com/articles/-/213519
大宮:そうなんですね。
小川:僕、人間の行動とか、せりふとか、決断とかのつじつまが合わないのはめちゃくちゃ気になるんで。
大宮:そういう性質って、日常生活に、支障をきたさないんですか。
小川:どうなんだろうな。でも、日常生活の支障が、今の小説の僕の、豊かな大地になってるところがあるんですよね。
大宮:豊かな大地?
小川:まあ例えば、僕、子どもの頃、野球のストライクとボールっていうのが、納得いかなかったんです。
大宮:えーっ。
小川:ストライクって動詞じゃないですか。ボールは名詞で、もっというとアウトは形容詞じゃないですか。全然意味が分かんなくて、野球部員に「おかしくない?」って聞いたり。
大宮:理屈っぽいとか言われそう。
小川:いやまあ、そうですね。でも、みんなが気にしてないことを気にすることって、作家にとってすごく重要な視点の一つだと思っているんで。
大宮:子ども時代にいじめられたりしなかったですか。
小川:そういう記憶はないですけど、……まあ面倒くさいやつとは思われていたかもしれませんね。それに、子どものころは、大人って話が通じないやつらだ、とばかにしてたんで。「なんでボールはボールなの?」とか聞いても、「そんなこといいから、さっさと行け」みたいな感じで。
大宮:じゃあ自分の中で、妄想する癖がついてたりしたんですかね。
小川:そうですね。まあ、昔から考え事をしたり、調べてみたりするのは、たぶん多かったんじゃないかなと思いますね。
大宮エリー(おおみや・えりー)/1975年、大阪府出身。99年、東京大学薬学部卒業。脚本家、演出家などを経て画家として活躍。主な著書に『生きるコント』(文藝春秋)。第80回ベネチア国際映画祭に監督・脚本を務めたVR映画「周波数」がノミネートされた
小川哲(おがわ・さとし)/1986年、千葉県出身。東京大学大学院在学中の2015年に『ユートロニカのこちら側』で第3回ハヤカワSFコンテスト大賞を受賞しデビュー。18年、同大学院総合文化研究科博士課程を退学。23年、『地図と拳』で第168回直木賞、『君のクイズ』で第76回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門を受賞
※AERA 2024年2月19日号
【こちらも話題】
七転び八起きは、なぜ「七起き」じゃないのか 小説家・小川哲が小学校時代に気になっていたこと
https://dot.asahi.com/articles/-/196379