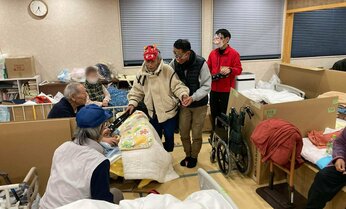43%の夫が不機嫌ハラスメントの被害者か 夫婦生活を調査して分かった意外な構図
※写真はイメージです(Getty Images)
日本には様々な結婚のカタチが存在するが、「結婚生活=日常生活」はさらに多様化している。一方で、二人がどんな夫婦関係を営んでいるのかをリアルに探る調査は少ない。中央大学教授で家族社会学者の山田昌弘氏は、2023年2月に夫婦の家庭生活における「パートナーの親密関係の変容に関する実証研究(以下、「親密性調査」)」を実施。山田氏の新著『パラサイト難婚社会』(朝日新書)から、日本人の結婚生活の実態について、一部抜粋・再編集して紹介する。
* * *
「フキハラ」をするのは夫か妻か
様々な「愛」の形があるならば、多様な「結婚」の形があってしかるべきと考える人々がいる一方で、「結婚」に伴う「不幸」の様相も、日本では多様化しています。おそらくどんな時代でも「結婚(生活)」に対する不満や不幸、悲しみや怒りは存在したはずですが、それがネーミングされるほど事例が増えているのが、現在の日本社会の特徴です。
結婚生活を送りながら不仲で没交渉状態であることを「家庭内別居」「家庭内離婚」と呼ぶようになったのは1990年代からでした。「DV(ドメスティックバイオレンス)」は、その名が付かない前近代でも存在しましたが、「働かない夫」や「ダメンズ」「家事育児をしない妻」などと共に、人生相談で取り上げられることが増えてきました。
【こちらも話題】
ただの友達「ただトモ夫婦」増殖中
https://dot.asahi.com/articles/-/8475
最近、注目を集めるのは「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」です。初めて耳にした時は「フキノトウか?」と思いましたが、違いました。配偶者が一方的に不機嫌になることで、結婚生活が良好に維持できない状況を指す言葉だそうです(「婚活」という言葉をつくった時も、「え、トンカツ」と聞き間違えられたことも多々ありましたが)。
もちろん昔から陽気な人もいれば、ネガティブな人もいて、自分の意のままにならない時にすぐ怒る男性など、特に昭和の「ガンコおやじ」と呼ばれる層に大勢いたと思いますが、それが度を越すと「ハラスメント」になる時代になったということです。
「DV」との違いは、必ずしも相手に身体的暴力を振るうとは限らないこと。「モラハラ」との違いは、相手の人格をことごとく否定するほどの、言動の暴力性はないこと。
ただし、些細なことですぐに不機嫌になり、一週間口をきかない、モノに当たるなどの状態が続けば、配偶者は非常な心的ストレスを感じます。さらにはその事態を解消するために(あるいはその事態を繰り返さないために)常に自分が謝ったり、相手の機嫌を取り続けたりしなくてはならないのが共通項のようです。恒常的、かつ一方的に不機嫌をぶつけられる妻(あるいは夫)は、相手の機嫌を取るために、本来しなくてもいいはずの「感情労働」をさせられている、というわけです。
【こちらも話題】
30代美人姉妹 妹が先に結婚できた理由は「理想と現実」
https://dot.asahi.com/articles/-/119961
実際、フキハラはその名が付くずっと以前から、日本の家庭生活ではよく見られた現象でした。それについては「妻が耐えるべきこと」「妻の美徳」と捉えられがちだった昭和の時代に比べ、「本来、異常なこと」「夫婦とはいえ、男女は平等のはずだから、一方が我慢し続けるのは正常の状態ではない」と人々が考えるようになったわけです。
ところが一歩進んで最近気づいたのは、決して「妻(女性)だけが耐え忍んでいるわけではない」ということです。一般的にフキハラのイメージは、「イライラして不機嫌になる夫」と、それに「耐え忍ぶ妻」という構図です。ドラマや漫画でもよく描かれていますし、SNS上でも人生相談の欄でも、こうした悩みは決して少なくありません。社会学でフキハラを研究している大阪大学大学院生の岡田玖美子さんも、分析の中心は夫から妻へのフキハラです。
しかし、「親密性調査」でフキハラの項目を訊いてみたところ、フキハラをしているのは夫(男性)側だけではなく、妻(女性)側にも多い実態がわかってきたのです。
「相手が不機嫌になった時、自分が謝ったり、ご機嫌をとったりする」と答えたのは、25~34歳の夫(男)が最多で、43%でした。一方、一般的にフキハラの被害者と目されがちな55~64歳の妻(女性)で「謝る」人は、わずか7%だったのです。そして55~64歳の妻の27%が「自分も不機嫌になる」と答えており、44%は「放っておく」と答えていました。自分も不機嫌になる割合は夫より妻が多く、年齢による差はあまりない。配偶者が不機嫌になった時の対応は、若年であるほど、そして妻より夫の方が謝ったりご機嫌を取る、つまり感情労働をする割合が高いことがわかります。よく、「夫婦喧嘩で、夫が謝る方が波風が立たない」と言われることがありますが、それを裏付けるデータでしょう。
【こちらも話題】
「実家を出たくても出られない」経済的独立が困難な若者たち
https://dot.asahi.com/articles/-/93867
ここから導き出される結論は二つです。一つ目は、世間で言われているほど、「不機嫌で強い夫」と、「それに耐える弱い妻」という構図は少ないのではないかということです。実際には「不機嫌で、イライラを振りまく妻」と、「それに耐える夫」という関係性が、世の中には大いに存在しているということです。だからといって、家庭では妻の方が権力があるとは言えません。夫に対して抵抗する数少ない手段が「不機嫌になること」だという場合もあるからです。
もう一つは、「声の大きい者勝ち」という現実です。ママ友コミュニティでも、ネット空間でも、新聞のお悩み相談欄でも、フキハラを訴えるのは、圧倒的に女性が多いのです。それはどうしてなのか。
一般的に男性は、家庭の悩みをあまり外には出しません。男性コミュニティで、妻の悪口で盛り上がるという場面には遭遇したことがありませんし、愚痴をどこかで発散するということもほとんどありません。これは男性の方が人格的に優れているからではなく、男女のコミュニティ形成の在り方の違いです。その場にいる同性と、配偶者の愚痴や悪口で連帯感や共通意識を持てるのは、共感能力の高い女性である場合が多いのです。
一方、男性は共感社会というよりも競争社会に生きており、常に社会的立場や縄張り意識を敏感に察知しながら、自分の立ち位置を確認している生き物です。そこで自分の結婚相手を不必要に貶めることは、妻の立場のみならず、配偶者である自分のポジションをも下落させる行為です。プライドや世間体もあるのでしょう。結果的に、妻の悪口は言わない(言えない)夫も多く、だからこそ、ひとり家庭で悶々と耐え忍ぶ……という現実も少なくないと見ています。
【こちらも話題】
50代ひきこもりと80代親のリアル 毎年300万円の仕送りの果て
https://dot.asahi.com/articles/-/127449