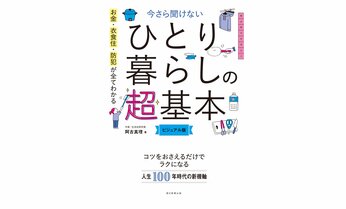「ただ一緒に生活できるということが本当に幸せ」 憧れの人だった夫と結婚、喧嘩はゼロ
鈴木雄大さんと鈴木佳奈子さん(撮影/写真映像部・東川哲也)
AERAの連載「はたらく夫婦カンケイ」では、ある共働き夫婦の出会いから結婚までの道のり、結婚後の家計や家事分担など、それぞれの視点から見た夫婦の関係を紹介します。AERA 2024年4月15日号では、塾の経営と食事・学習支援事業に夫婦で取り組む鈴木雄大さんと鈴木佳奈子さん夫婦について取り上げました。
* * *
妻22歳、夫32歳で結婚。長男(21)、長女(20)、次女(18)、次男(17)、夫の母と7人で暮らす。
【出会いは?】夫が勤めていた学習塾に、妻が学生講師として入った。妻は中学生時代、同じ塾で夫の授業を受けたときから憧れていた。
【結婚までの道のりは?】一緒に仕事をするようになり、「やっぱり好き」と感じた妻が押し切った。
【家事や家計の分担は?】洗濯と掃除は妻。他はふたりで。弁当は夫、デザートは妻。財布は一緒。
夫 鈴木雄大[54]慶翔ゼミナール 塾経営/NPO法人メダカのお弁当 理事長
すずき・たけひろ◆1969年生まれ、横浜市出身。神奈川大学法学部中退。学生時代から働いていた学習塾に就職。退職、結婚を経て塾を設立。「メダカのお弁当」や学習支援の無料塾にも力を注ぐ
塾を始めて22年、いろんな危機があったけれど、彼女は決して否定的なことを言わず、常に「なんとかなるだろう」。日々感謝してます、言いませんけれど。
食事支援や学習支援の活動をしているのは、これまでいろんな方に助けてもらってきた恩を他の方に送るため。毎朝彼女と並んで台所に立ち、無料配布する弁当を20食ほど作っています。うちは子どもが4人いて毎食たくさん作るから手慣れたもの。手間は大して変わらないんです。
夫婦は喧嘩してなんぼ、なんていうけれど、したことがないですね。あえて彼女に何か伝えるなら「ろれつがまわらなくなったら救急車呼んで」と「痛風が痛いから足を踏まないで」くらいかな。
僕たちは10歳違い。女性のほうが平均寿命が長いから、彼女は20年くらい一人になるかもしれない。これだけずっと一緒にいると、それって耐えられないんじゃないかな。逆に僕もそうですけど。そこどうしようかな、困ったな、というのは今考え中です。
鈴木雄大さんと鈴木佳奈子さん(撮影/写真映像部・東川哲也)
妻 鈴木佳奈子[44]慶翔ゼミナール 塾経営/NPO法人メダカのお弁当 事務局長
すずき・かなこ◆1979年生まれ、横浜市出身。杏林大学社会科学部を卒業し、第1子を出産。同年、夫と塾を始める。一方でお弁当版子ども食堂「メダカのお弁当」や学習支援にも携わる
塾の生徒だった中学時代から憧れの人だったので、たまたまご縁で一緒に働けることになり、うれしくて。「これはいくしかない」とアプローチしました。結婚は前世から決まっていたことです(笑)。
喧嘩は全くないですね。基本的に尊敬しているので。やると決めたことは絶対に投げ出さないし、いつも隣にいて、どんなときも支えてくれます。たとえば役所とのやりとりなど、私がはっきり言えないところをフォローしてくれたり。そういった小さなことの積み重ねなんですけれど。
昔は「自分が努力すれば結果は出る」と思っていました。でも一緒に仕事をしていくうちに、努力しても実らないことってあるんだなと。物事にはご縁やタイミングがあるというのもわかり、「努力しなければ」と自分を追い詰めることが減った。少し力を抜けるようになりました。
ただ一緒に生活できるということが、本当に幸せ。特別なことは必要ないので、これからも何げない毎日を一緒に過ごしていければいいな。
(構成・大塚玲子)
※AERA 2024年4月15日号









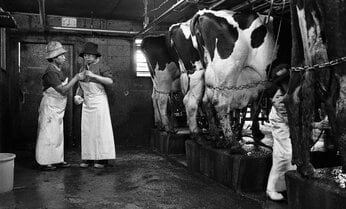





![[京都橘大学]AIとデジタルから見る未来](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/3/346m/img_73b89081ee2bd5f52a9c19d11913110c200846.jpg)