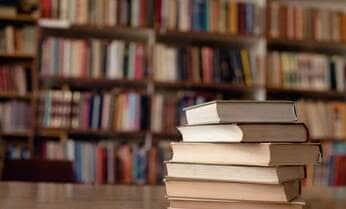上田慎一郎が語る「カメ止め」旋風「『見たことある?』って聞かれました」
上田慎一郎さん(右)と林真理子さん (撮影/写真部・松永卓也)
「カメラを止めるな!」で一躍脚光を浴びた上田慎一郎監督。作家・林真理子さんとの対談では、独学で監督を目指した「カメ止め」以前のこと、社会現象を自覚したヒット後のことなど盛りだくさん。
【前編/上田慎一郎・最新作は男性器が飛ぶ? 制作のきっかけは“妻の言葉”】より続く
* * *
林:私、「カメ止め」は映画館で見たんですけど、前の上映回が終わって人がぞろぞろ出てきたら、向こうから「ぴあ」の社長(矢内廣氏)が来たんです。「おもしろかったですか?」って聞いたら、「いやあ、おもしろかったよ」とおっしゃるので、こういうのが社会現象ってことなんだな、と思いましたよ。映画館で知り合いとすれ違うってめったにないし。
上田:僕、「『カメ止め』って映画、見たことあります?」って聞かれたことありますよ。
林:えっ、そんなことが。
上田:「あります!」って言いましたけど、「これが社会現象なんやな」と思いました(笑)。
林:それはすごくうれしいですよね。最高ですよ。私もそんな目にあってみたいな。
上田:僕、子どもがいるんですけど、壁に「カメ止め」のキーホルダーがかかってるのをベビーシッターさんが見て、「上田さん、『カメ止め』好きなんですか? 私、3回ぐらい見に行きました」って言われて、「僕がつくったんです。ここで撮影したんです」って(笑)。
林:あれ、ご自分のおうちなんですか。ちょっとショボい1LDKぐらいの……。
上田:そうです。ショボい1LDKです(笑)。
林:今は引っ越しました?
上田:引っ越しました。都心のほうへ。
林:よかったですね(笑)。いまもちゃんと結婚指輪をしていて、すてきです。
上田:妻も映画監督をやっていて、「カメ止め」のときはポスターなんかをつくってくれました。
林:そうなんですか。そういえば、「あの主演女優さんが上田監督の奥さんだよ」って、間違えてる人がけっこういましたよ、当時。
上田慎一郎 (撮影/写真部・松永卓也)
上田:虚実がないまぜになっているところがあって、監督の役をやった濱津(隆之)さんを本当の監督だと思ってる人が、けっこういるんですよ。映画を見終わったあと、濱津さんに「監督、おもしろかったです」みたいに言う人がいて(笑)。
林:「俳優さんにギャラを払えたのがいちばんうれしくて、みんなが人気者になったのもうれしい」とおっしゃってましたね。
上田:うれしいですね、それは。
林:どんぐりさん(竹原芳子)という方、すごいじゃないですか。私、「カメ止め」でどんぐりさんを見たときに、すごいインパクトだな、と思いました。あの方、今や引っ張りだこで、ドラマ「ルパンの娘」でもおばあちゃん役で出てましたよね。
上田:そうなんですよ。どんぐりさん、ほんとにパワフルな方で、50歳を過ぎてから俳優を始めたんです。裁判所の事務をやっていて、NSC(吉本総合芸能学院)という吉本のお笑いの養成所に入って、そこに何年かいて、それから俳優を志したそうで、映像演技はあれが初めてだったんです。
林:そういう人を見つけてくるところがすごいですよ。上田監督は昔から映画を撮ろうと決めてたんですか。
上田:中学校のころからハンディーカメラで映画を撮ってました。
林:スピルバーグみたいじゃないですか(笑)。
上田:放課後、友達と集まって、その場の思いつきで毎日撮っていたような感じです。撮るのが楽しいから撮ってただけで、映画監督になろうとは思ってなかったんですけど、高校に進学するときにはじめて、職業として映画監督を意識しました。
林:日芸(日大芸術学部)とか、日本映画学校(現・日本映画大学)とかに行こうとは思わなかったんですか。
上田:僕、お笑いがすごく好きだったので、将来は映画監督かお笑い芸人かで迷ったんですよ。高校のときは演劇をやっていて、近畿で2位ぐらいになったんです。それで大学からオファーをいただいて。
林:あ、演劇もオファーがあるんですね。スポーツだけじゃなくて。
上田:「うちの大学で劇団をやらないか」というのが来たんです。でも、生意気だったんで、ハリウッドに行こうと思ってそれを蹴って、1年間英語を学んでからハリウッドに行こうと思って英語の学校に行ったんです。でも、そこでなじめなくて中退して、そこからは完全に独学で映画を撮るようになりました。
林:独学ってどうするんですか。カット割りをメモしながら映画を見てたって、誰かから聞いたことがありますけど。
上田:とにかく浴びるように見て撮って、見て撮って、体で学んでいった感じです。そして20代半ばで初めて映画制作団体に加入して、大きいカメラでの撮り方とか、音声の録り方とかを学んだんですよ。でも、ここでも生意気なところが出ちゃって、「自分でできる」と思って、自分の制作団体を立ち上げたんです。そこで10本ぐらい自主映画をつくったあとに「カメ止め」をつくったという感じですね。
林:失礼だけど、その間の生活はどうしてたんですか。
上田:バイトをしてました。長かったのは携帯電話ショップの店員で、最後はその店の副店長になりました。
林:そうなんだ。けっこう社会生活に参加してるんですね(笑)。
上田:そのあと保険のコールセンターの深夜受付をやったんですけど、そこは役者とか歌手とかのタマゴが多かったので、自主映画の主題歌を仲間につくってもらったりしてました。
林:へぇ~、おもしろいですね。顔が見えないところに、俳優のタマゴ、歌手のタマゴ、そして監督のタマゴがいるんですね(笑)。
上田:今でもつながってる人が多いです。そこは時給がすごくよくて、月40万ぐらい稼いでましたね。一時、講演会とか結婚式を撮って、編集したりする仕事をしてたんですけど、それはすごくしんどくて。自分が好きなものだけ撮って、好きなように編集すればいいわけじゃないですからね。だから、ちゃんとバイトして、生活の地盤があったうえで、自分の好きなものだけを撮るほうが性に合ってるなと思って。
林:そのときはもう結婚されてたんですか。
上田:えっと、結婚はいつだったか……。5、6年前かな。
林:忘れちゃった? 奥さんに怒られちゃいますよ(笑)。いずれにしても「カメ止め」を撮る前ですよね。家庭を持ったタイミングって、売れないお笑い芸人とか役者の人が夢をあきらめて、ふつうの会社に入るってパターン、よく聞きますけど、なんで監督は家庭を持っても「映画をやるぞ!」と思えたんですか。
上田:妻も映画監督だったことは大きいですね。それと、僕は妻と出会ってから、いろんなことがうまくいき始めたんですよ。だから、妻には感謝というか。
林:それはよかったですね。いつまでも仲良くして、これからも見た人が度肝を抜かれるようなおもしろい映画をたくさんつくってください。
上田:はい、頑張ります!
(構成/本誌・直木詩帆 編集協力/一木俊雄)
上田慎一郎(うえだ・しんいちろう)/1984年、滋賀県生まれ。中学生から自主映画を撮り始め、高校卒業後も映画を独学。2009年、映画制作団体を結成、代表を務める。18年、劇場用長編映画デビュー作「カメラを止めるな!」は興行収入31億円を突破、国内外の映画賞を多数受賞した。その後も「イソップの思うツボ」(19年、共同監督)、「スペシャルアクターズ」(19年)、「100日間生きたワニ」(21年、共同監督)など、話題作を監督。1月14日から、脚本・監督を務める映画「ポプラン」が、全国ロードショー。※週刊朝日 2022年1月21日号より抜粋