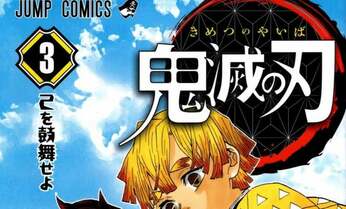「子どもの進学費用が…」37歳で手取り20万円 首相は保育士の悲鳴が聞こえているか
保育の現場からの声は届くのか(写真と本文は関係ありません)
岸田文雄首相が保育士に対し、平均給与の3パーセントに当たる月9000円の賃上げ方針を掲げている。ただ、現役保育士たちからは「9000円では焼け石に水」と冷ややかな声も聞こえる。薄給の上、ギリギリの人員配置に疲弊する保育士たちの現実が、首相は見えているだろうか。
* * *
「毎月、生活はかつかつですよ」
都内の保育園に勤務する保育士・三枝健太郎さん(37=仮名)は給与明細を見ながら言葉をしぼりだした。
月約40時間の残業代込みで、手取りは20万円をやっと超える程度。2児の父で、都内の賃貸住宅に妻と4人で暮らす。都心ほどではないが家賃相場は低くない。家賃と光熱費だけで10万円を軽く超える。
7年間の幼稚園勤務を経て、今の保育園は5年目。経験を生かし、リーダー職を担う立場だ。三枝さんはこの園で勤務を始めた後、労働組合「介護・保育ユニオン」に加入。団体交渉によって保育士全員の月給が2万円上がった。さらに、横行していたサービス残業も一定の改善があり、残業代もつくようになった。それで、この手取りである。
「今後も給与はほとんど上がりません。50歳まで頑張っても年収は400万円に届かないでしょうね。子どもの進学費用をどう工面していくか…」
■「天の声」に保育現場は疲弊
お金だけが問題ではない。職場にも“ブラック”な現実が垣間見える。
株式会社が経営する保育園なのだが、現場の声は上に届かない。そればかりか、突然降ってくる“天の声”に現場は疲弊する。
「教材が全然売れていない。何をやっているんだ!」
2年前、三枝さんたち保育士は、会議の席で運営会社の社員からこう詰め寄られた。
会社が突然決めた、ある教材の採用。それを、園児の親全員に売るように圧力をかけられたのだ。
「保育士はみんな子どもが大好きで、子どもの成長を一生懸命考えています。なのに、使う意義すら分からない教材の販売をなぜ一方的に強いられるのか。本当に悔しかったし、辛かったですよ」
同僚たちも憤ったが、会社からの圧力で次第に心を病むようになり、一気に5人が退職した。職場の保育士の2割もの人員、しかもみんな20~30代の若者だ。
会社の方針転換で、その教材は1年もたたずに扱わなくなった。
「さらに問題なのは、その後の人員補充がないこと。薄給のため、募集しても人が来てくれない。現場が少人数で疲弊していくなか、それでも会社は給料をあげようとせず、人員補充に本気の姿勢を示さないんです」(三枝さん)
本来は4種類のシフトがあるが、今はなし崩し。保育士同士で時間を融通しあい、ギリギリの状況で仕事を回しているという。
■人件費を削って会社が潤う現状
給料が低すぎるといわれ続けている保育士。岸田首相は、保育士の月給を9000円上げるとうたっている。だが、現状は国の制度の運用に大きな欠陥があり、その9000円ですら保育士に届く保証はない。
私立の認可保育所には、市区町村から毎月、国の「公定価格」に基づき、運営に関する「委託費」が支払われており、これが主たる財源だ。この公定価格自体が低すぎるという指摘はかねてあった。さらに2000年までは「人件費が全体の8割」と使途が定められていたが、同年に国が待機児童解消を名目に株式会社の保育参入を解禁し、同時に委託費の「弾力的運用」を認めた。
この「弾力的運用」をいいことに、保育士の人件費を削り、経営者や会社ばかりが潤っている保育園がある。委託費の恣意的な運用が許され続けているのだ。
会社の姿勢に疑問を募らせた三枝さんは労働組合を通じ、会社に運営費の書類を開示するよう求めたが、当初は拒否された。最終的に開示に応じたが、ほとんどの数字が黒塗りされ、人件費の割合はおろか、経営実態はなにも分からなかったという。
三枝さんは、「会社は保育士たちに『本当はもっと給料をあげたいんだけど』などと不可抗力かのように言うのですが、まったく信用できません」と憤り、疑問を口にする。
「委託費の運用にルールを作らないと何も変わらないと思います。それと、保育士の平均月収が30万円ちょっとで、その3パーセントで9000円だそうですが、ボーナスを入れても月収30万円に達している保育士は少ないと思いますよ。この平均月収はどういう計算で出したものなのか」
■「休憩つぶしたのは勝手な判断」と言われ
東京23区内の保育所に勤める吉岡明美さん(50代=仮名)。5年前、まったく別の仕事から転職を果たした吉岡さんが見たのは、薄給と激務に希望を失い、息子や娘のような若者たちが次々と職場を去っていく、むごい現実だった。
「保育士がみんな20代で辞めていく。2年前には、職場の半数に当たる保育士が一斉に退職しました。キャリアを積んだ中堅の保育士が、ただの一人もいません」
約30時間の残業代込みで、手取りは20万円代。年2回のボーナスも手取りで数万円だ。昇給はほとんどなく、サービス残業も横行している。
「保育士の仕事は、日誌や個々の園児のようすの記録など、書類の処理業務が非常に多いんです。やむなく休憩時間をつぶしてそれをこなしていましたが、会社側は『休憩は取ってください』の一点張りでした」
昨年、運営会社に異議を訴えたところ、幹部はこう言い放った。
「休憩時間をつぶしたのは、あなたの勝手な判断でしょ?」
離職する保育士が相次ぐ現状に、
「ギリギリの人数では、安全で安心な保育はできませんよ。ずっとこのままでいるつもりですか」と問いただしたが、幹部の対応はそっけなかった。
若い労働者が辞めていく前提で、薄給で使い倒す。まさにブラック企業と似た構図である。
「10年、20年とキャリアを積んだ質の良い保育士がいた方が、園児の成長にもつながりますし、預ける親たちだって安心です。この当たり前のことを会社は考えようともしない。社会経験が長いと会社に意見するようになるので、ベテランがいない方が好都合なんでしょうね」
12月19日の日曜日、「介護・保育ユニオン」が東京・新宿で保育士たちによるデモを行なう。
(1) 委託費の使い道のルール化(2) 国が定める保育士の人員配置基準の改善(3) 上の(1)(2)を実現したうえでの公定価格の引き上げ
の3つの柱を訴える。
三枝さんも吉岡さんもこのデモに参加するという。
「委託費や人員の問題が全然改善されない。保育士らの待遇改善を岸田首相自らが打ち出した今がチャンスだと思って、声を上げる決意をしました。野党も文句だけを言うのではなく、新しい仕組み作りにしっかり動いてほしい」(三枝さん)
吉岡さんもこう強調する。
「保育士に転職して、若い保育士たちが、子どもたちの成長をどれほど真剣に考えているのかを身をもって知りました。その子たちが希望を失い去っていく現状を何とか変えたい。年上の私が、行動しなければと思ったんです」
岸田首相と与党だけではなく、野党も知恵を絞り動かねばならない。彼らの苦しみを知らず、文通費などを“ごっちゃん”してる場合ではないのだ。(AERAdot.編集部・國府田英之)