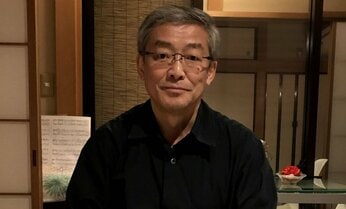
「山崎元の遺産は全世界株式VT1000口と…」相続税はいくら? 山崎元さん妻が初登場・後編/新NISA応援
経済評論家の山崎 元さん。緊急事態宣言中、誕生日を自宅で祝った。妻・薫さんお手製のフルコースを前に。白ワインもたっぷりと(2021年5月8日)(写真提供・山崎 薫)
2024年1月1日、65歳でこの世を去った山崎元さんと20年近く連れ添った妻の薫さんがメディア初登場。聞き手は楽天証券の投資メディア「トウシル」の武田成央(さだちか)さん(山崎さんと深酒する仲だった)。薫さんに山崎さんの遺産額、「家庭での山崎さん」についても語っていただいた。【本記事はアエラ増刊「AERA Money 2025夏号」から抜粋しています】
* * *
※本記事は後編です。前編はこちら
(山崎 薫)とりあえず山崎がずっとお世話になっていた税理士さんに連絡しました。納税者が死亡したときの準確定申告をお願いするためです。
税理士さんは「さあ相続だ」とばかりに構えているわけです。ところが、山崎が遺した資産は相続税なんて全っ然発生しない額でした。
(武田)ダイ・ウィズ・ゼロ。
(山崎 薫)いやもう本当にそれですよ。山崎の共著者、水瀬ケンイチさん(『ほったらかし投資術』全面改訂第3版/朝日新書)がSNSでコメントされていたのですが、これ。(と、薫さんがその場で見せてくれたスマホ画面にはこう書かれていた)
「山崎さんは年収3000万円がある一方で、ご自身の預貯金や運用資産はほとんどなく、そもそもDWZ(Die With Zero)を地で行っているようなものです」
お金の話は一切しなかった
経済評論家、山崎元さんの配偶者の山崎 薫さん(撮影・佐藤創紀/朝日新聞出版写真映像部)
(山崎 薫)山崎から毎月の生活費を渡されていましたが、そもそもいくら稼いでいるかは聞きそびれていました。
三菱UFJ銀行と楽天証券に口座があることは知っていましたが、残高がいくらあって何に投資しているかも不明でした。甘えていたんですね。
生活は普通に回っていたので、本人が言いたければ言うだろう、くらいに考えていました。
(武田)山崎さんは何に投資していましたか?
(山崎 薫)相続手続きを開始してはじめて「バンガード・トータル・ワールドストックETF(VT)」(ETF=上場投資信託)を持っていたことを知りました。
VTは私名義の口座に移管し、時価換算して相続分配しました。
このインタビューを受けることになって、このVTはいつ、いくらで買ったものかを調べようとしたのですが、移管されるとその前の持ち主のデータはなくなってしまうんですね。現在、私の口座の表示では平均取得価額「0ドル」となっています。
本記事が丸ごと読める「AERA Money 2025夏号」はこちら!
商品価格¥1,320 詳細はこちら ※価格などの情報は、原稿執筆時点のものになるため、最新価格や在庫情報等は、Amazonサイト上でご確認ください。
「遺産は相続税が全然発生しない額でした」(撮影・佐藤創紀/朝日新聞出版写真映像部)
(山崎 薫)山崎もずっと言っていましたが、「過去にいくらで買ったのか」というのは実はどうでもいい情報です。
山崎が100ドルで買ったとしても1000ドルで買ったとしても、今の私には全く関係がなかった。保有し続けるか売却するかの判断材料として「過去の情報っていらないな、山崎の言ってた通りだな」と実感しました。
仮に損が出ていたとしても、それは私の判断に何の影響も与えません。とりあえず当面のキャッシュはあるから、今は取り崩す必要はない、それだけでした。(後日、薫さんから追加情報)
(山崎 薫)VTの話はこれでおしまい、と思っていたら、続きが出てきました。『ほったらかし投資術』を改めて読んでいたら、第3版で新たに加えられた鼎談(ていだん)の中で、山崎は「2016年にVTを1000口買った」と明かしていたんです。
リアルタイムでも公表していて、水瀬さんをはじめとした投資ブロガーさんたちの間でとても話題になったようです。
知らなかったのは妻の自分だけ……と、一瞬思ったところで「山崎が今、一度に突っ込める金額って500万〜600万円なんだ」と考えた記憶がうっすらよみがえってきました。おそらく私も当時、ネットで読んではいたものの、すっかり忘れていたんでしょうね。
遺族は大変
(武田)相続税がかからない程度の現金とVT1000口、以上。かっこいいです。
(山崎 薫)いやいや、残された家族からしたら大変ですよ。大学生と高校生の子どもがいるのに。「これからいくらかかるのよ?」って話です。
長男が大学受験を終えたところで就活をしました。2024年2月に出版された『経済評論家の父から息子への手紙お金と人生と幸せについて』(Gakken)が売れて、本当に助かりました。
その後、勤務先がいま一つしっくりこなくて1年と少しで辞めることに。昔取った杵柄(きねづか)で制作プロダクションを立ち上げ、ほそぼそと映像制作の仕事をしています。
楽天証券 トウシル&メディア編集部 部長の武田成央〈さだちか〉さん(撮影・佐藤創紀/朝日新聞出版写真映像部)
(山崎 薫)長男は大学3年生ですが、大学院に進むことも視野に入れているようです。娘はようやく今春、大学に入学し、学生寮で新生活をはじめたばかり。まだまだお金はかかります。
(武田)亡きあとも印税で家族を養っている!
(山崎 薫)売れるか売れないかわからないわけですから、無計画にもほどがあるでしょ(笑)。
山崎はあの本を生きているうちに出版したくて、ものすごく急いだんです。ゲラ(試し刷り)のチェックを残すばかりになって、「(2024年)1月中に出せたらいいな」って言っていました。彼に、書店に並んだ本を見せたかった。
経費で飲むのはダサい
(武田)薫さんご自身の投資は?
(山崎 薫)結婚前に、設定して間もないハンセン中国企業指数ETF(02828)を400口、買っています。
経済評論家で、ピーター・リンチやウォーレン・バフェットの投資哲学をいち早く日本に紹介し、翻訳を多く手がけた故・三原淳雄さんの番組を担当していた時期があるんですが、三原さんはいつも「20年、30年と成長するような企業を見つけてその株を買いなさい」と勧めていました。
さまざまな事情で個別株を買うことはできませんでしたので、中国という国の成長を買ってみようと思いました。何十年か後に、「山あり谷ありを経て、今はいくらになっています」と三原さんと酒飲み話をするつもりだったんです。
三原さんは山崎を番組ゲストに指名したことが何度もあったため、どうやらご自身がキューピッドだったと思っていらしたようです。
山崎は常々、『お金に名前を書いたりタグを付けたりすることはできないし、過剰な思い入れを持つと判断を誤る』と言っていましたが、このETFについてはよほどお金に困窮しない限り、世界経済がどう動こうと持ち続けます。
(武田)話は変わりますが、一緒にお酒を飲みに行くと、いつも山崎さんのおごりでした。払おうとしても、払わせてもらえなくて(笑)。
(山崎 薫)自分より若い人がいるときは、人数に関係なく払っていたはずです。経費で飲食するのは心の底からダサいと思っていたようです。
どこで撮ったものか思い出せないが家族3人で。テーブルに空ジョッキ(2005年夏)(写真提供・山崎 薫)
(武田)自分は浪費家だと山崎さんは書いていました。
(山崎 薫)日頃は理詰めで物事を考えるのに、消費に関しては全く合理的ではありませんでした。
特に好きだったのは家電量販店の福袋です。3万円か5万円くらいの。ヨドバシカメラとビックカメラがお気に入りでした。
整理整頓は下手だから、買うたびに部屋にモノがあふれていく。そのくせ「モノのないすっきりしたホテルみたいな部屋に住みたい」って大まじめに言うんです。「使わないモノを買ってきて狭い部屋をさらにごちゃごちゃにしてるのはあんたやろ」って突っ込みたくなりましたね。
服もやたら高いものを買いたがるんですよ。センスを磨くことをとうの昔に諦めていて、そこはブランドに丸投げしているんです。信託報酬の0.01%にこだわるくせに。(一同、爆笑)
ハイブランドのTシャツを買ったときのことです。1着、数万円もしました。あるとき無印良品で、そのTシャツとそっくりなものがあったので買ってきて、並べてみました。
すると山崎本人が「これ、作っている工場は同じだよね」って。生地も糸も縫製も同じにしか見えません。でも値段は数倍違う。
こうしたとき、山崎はビジネスモデルの違いをおもしろがりはしますが、「損した」などとは露ほども思いません。
「どちらが得かを調べるのは時間と手間の大いなる無駄」だと考えていました。
「いいと思ったら、さっさと買う!」、これが消費における彼の合理性でした。
山崎元の著書2強
(武田)薫さんが一番好きな山崎さんの著書は?
(山崎 薫)山崎が書く本は大別して「投資」「転職」「人生相談」の3分野でした。投資の決定版が『ほったらかし投資術』だとすれば、人生相談では『がんになってわかったお金と人生の本質』(朝日新聞出版)です。
情報の扱い方、保険、時間と仕事、お金とは、幸せとは。これが山崎の最後の本になりました。がんであってもなくても、究極の人生相談の答えが書かれています。
山崎さん47歳の頃。自宅で長男を抱いて(2005年夏)(写真提供・山崎 薫)
(山崎 薫)山崎は初の人生相談本『リスクとリターンで考えると、人生はシンプルになる!』(ダイヤモンド社)で「人生選択の考え方は『投資』に似ている」と書きました。
先のことを確実には見通せない中、リスクを考えながらできるだけいい結果を求めて、何にかけるかを決める。
「不確実性下の意思決定」という文脈で、がん治療と投資には共通点があります。これはゲーム理論とも通じていて、山崎は最後まで人生というゲームを存分に楽しんだと思います。
(武田)山崎さんのいない今、どんなことを思い出しますか。
(山崎 薫)11時頃に起きて昼食、彼にとっては朝食を一緒に作って食べて、コーヒーを飲みながら新聞を読み、原稿を1本仕上げて夕方近くに出かける。これが日課でした。
今、昼食を作っていると、彼と一緒に何かをすることはないんだと思います。
「失敗・成長の法則」
(武田)山崎さんの印象的な言葉は?
(山崎 薫)「失敗・成長の法則」です。これ、人は失敗を乗り越えて成長するっていう話ではありません。
「隠したウソや失敗は隠しきれなくなるまで大きく育つ」。育ったあとはどうなるか? たいがい破綻(はたん)します。山崎が見いだした法則です。
古くは簿外債務が発覚して大手証券会社が破綻しました。少し記憶に新しいところでは、中古車販売会社で保険金の不正請求が明るみに出ました。
課長レベルで不正をストップして謝っておけば世間に許してもらえたかもしれませんが、社長レベルで会社全体で隠していたら、もう許してはもらえません。
こういった大きな話ではなく、子育てやパートナーとの関係といったプライベートでも「失敗・成長の法則」は効くなぁと私は思っていて、心に留めています。
(武田)投資家のみなさんに山崎さんが一番伝えたかったことは何でしょう。
(山崎 薫)「必ず勝てる方法」ではなく、「正しく考える方法」ではないかと。何かを研究し尽くしたり、大きな資金があったりすれば投資に成功するわけではないですよね。運用には何らかの不確実性が伴い、勝ちも負けもあって。
ゲーム感覚でマーケットを楽しむには、知識や理論を持ったうえで運を受け入れ、自己を律し、その先を考えよう。彼が強調していたことは、こんな感じではないでしょうか。
町内会の新年会で、ホテル椿山荘東京(東京都文京区)にて(2016年1月3日)(写真提供・山崎 薫)
(武田)山崎さんのファンに向けて、メッセージをお願いします。
(山崎 薫)最後の著書『がんになってわかったお金と人生の本質』の元になった「note」には、今も毎日「スキ」と「フォロー」をいただいています。本人が目にすることも更新されることもないのに、ありがたいことです。
それでも「スキ」や「フォロー」をポチッとして気持ちを伝えてくださる。この場をお借りして感謝申し上げます。
山崎が亡くなって以降、マーケットはドラマチックに動いています。「オルカン1本で本当にいいのか」と脅し、「インデックスより○○投資」とあおる記事や動画も見かけました。
インデックス投資家のみなさんはこうしたコンテンツに惑わされず、ご自身が投資をはじめた際のロジックを忘れずにいてくださればと思います。
どんな相場でも「長期・分散・低コスト」で続けていただければ、山崎も「俺が伝えたことが人の役に立った」と満足しそうな気がします。
インデックス投資自体に自信が持てなくなった方は、山崎元の残した記事や動画を検索してみてください。トウシルさんだけでも400本の記事を無料で読むことができます。
山崎元の著書をそばに置いていただき、原点に立ち返るために読み返していただければ、家族としてこんなにうれしいことはありません。
【山崎薫さんから提供いただいた山崎元さんメモリアル写真4枚はこちら】
自宅でお子さんとテーブルテニス(2014年12月30日)(写真提供・山崎 薫)
奥多摩にて。見えづらいが、石で水切りをする山崎さん。「運動神経ゼロでしたが、石切りは案外うまくて驚きました。ちなみに、彼は縄跳(なわとび)ができませんでした」(2017年7月20日)(写真提供・山崎 薫)
長女の誕生祝いに母娘でディズニーランドへ行った日、晩酌中の山崎さんに土産話をしていたら、おどけてポーズ(写真提供・山崎 薫)
正月の昼間から上野の「せんべろ」系酒場へ。夫婦2人で(2019年1月5日)(写真提供・山崎 薫)
取材・文/中島晶子(AERA編集部)、大場宏明
山崎 元(やまざき・はじめ)個人投資家に「正しいこと、合理的なこと」を伝え続けた経済評論家。最後の著書『がんになってわかったお金と人生の本質』(小社刊)もベストセラーに
山崎 薫(やまざき・かおる)2024年1月1日に亡くなった経済評論家、山崎元さんの配偶者。写真付きでのマスコミ取材は初
武田成央(たけだ・さだちか)楽天証券 トウシル&メディア編集部 部長。山崎元さんが最後に勤めていたのが楽天証券経済研究所。武田さんは山崎さんが連載していた楽天証券のオウンドメディア「トウシル」の編集長として山崎さんと何度もお酒を酌み交わした
この記事の完全版が読めるAERA増刊「AERA Money 2025夏号」が好評発売中です! Amazonや楽天ブックスなどのネット書店では「アエラマネー」で検索して、この表紙を探してみてください!(編集部より)
編集/綾小路麗香、伊藤忍
『AERA Money 2025夏号』から抜粋

























