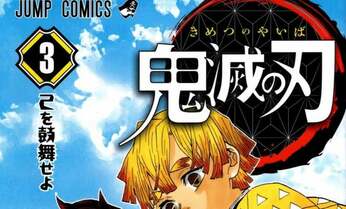
なぜ我妻善逸は猗窩座戦に参加しなかったのか――善逸が「ひとりで戦う」理由 植朗子
我妻善逸(右)画像はコミックス「鬼滅の刃」3巻のカバーより
【※ネタバレ注意】以下の内容には、今後放映予定のアニメ、既刊のコミックスのネタバレが含まれます。
28日、アニメ「鬼滅の刃」無限列車編が最終回を迎えた。フィナーレでは上弦の鬼・猗窩座と炎柱・煉獄杏寿郎が文字通りの死闘を演じた。この“炎柱の最後の戦い”を炭治郎と伊之助がすぐそばで見届けたのに対して、善逸だけはその場にいなかった。なぜ善逸は“ひとり”別の場所にいたのか? そこには、善逸ならではの“戦い方”の流儀があった。<本連載が一冊にまとめられた「鬼滅夜話」が即増刷され、好評発売中です>
* * *
■善逸は弱虫?
我妻善逸(あがつま・ぜんいつ)は、騒がしく、訓練をサボりがちな、お調子者の「弱虫キャラ」である。鬼殺隊の入隊試験時には誰よりもおびえた様子を見せ、「鼓の鬼」がひそむ屋敷では、鬼の恐ろしさにふるえながら炭治郎(たんじろう)に助けを求めた。
<炭治郎 なぁ炭治郎 守ってくれるよな? 俺を守ってくれるよな?>(我妻善逸/3巻・第21話「鼓屋敷」)
やがて「鼓の鬼」の血鬼術(けっきじゅつ=鬼の特殊能力)によって、善逸は炭治郎と引き離されてしまった。善逸はたったひとりで、「正一くん」という名の一般の少年を守らねばならなくなった。
■善逸の真の姿
自分の強さに自信がない善逸は、緊張が極限まで高まると昏倒(こんとう)してしまう。しかし、彼はこの「昏倒」によって、真の強さを発揮する。
<雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃(へきれきいっせん)>(我妻善逸/3巻・ 第23話「猪は牙を剥き 善逸は眠る」)
「本当の善逸」は強い。雷鳴を思わせる爆音をたてながら地面を踏み切り、稲光を思わせるようなスピードに乗って、強烈な威力の剣技を放つ。善逸は「雷の呼吸」の後継者のひとりで、すさまじい必殺技を持っていた。しかし、本当の意味での「善逸らしさ」は、実はこの必殺技の前のコマで描かれている。
緊張から眠りに落ちた善逸は、意識を失っているにもかかわらず、正一くんの悲鳴に反応し、彼を襲う鬼の前に立ちふさがった。「霹靂一閃」を放つための抜刀直前、正一くんをかばうように広げられた善逸の左手。“守る”という強い意志。このたった1コマから、善逸の優しさが伝わってくる。鬼におびえて泣いていた正一くんの涙が止まる。
■善逸の戦いの動機
かつて善逸は何度も泣いて剣術訓練の邪魔をしたために、兄弟子である獪岳(かいがく)に厳しく叱責されていた過去があった。
<なぜお前はここにいるんだ!!なぜお前はここにしがみつく!!>(獪岳/4巻・第34話「強靭な刃」)
当時の善逸は獪岳の問いにうまく答えられなかった。しかし、善逸には夢があった。
<幸せな夢なんだ 俺は強くて 誰よりも強くて 弱い人や困っている人を 助けてあげられる いつでも>(我妻善逸/4巻・第34話「強靭な刃」)
表面上は鬼殺の任務を嫌がる善逸であったが、弱音を吐きながらも、彼は他者のために懸命に戦っていた。恐ろしい鬼と、弱い自分の心と向き合いながら。善逸は誰かを助けられる自分になりたかったのだ。
■無限列車での善逸の戦い方
こんなふうにアンバランスな「優しさと強さ」を抱えた善逸は、無限列車編ではまだまだ“責任感”が足りていない。炎柱・煉獄杏寿郎(れんごく・きょうじゅろう)から、無限列車には鬼が出ると聞かされると、「降ります!!」と堂々と叫んだりしている。
しかし、下車する間など当然なく、すぐに「下弦の壱」の鬼・魘夢(えんむ)との戦闘へ突入することになった。高速で走る8両編成の列車内という細長い空間、守らなくてはならない一般市民200人という過酷な状況によって、炭治郎たちは戦力を分断されてしまった。
炭治郎は禰豆子の戦闘力を信じて、彼女をその場に残し、自分は離れた場所で戦い始めてしまう。列車内の乗客を守る奮闘の中で、禰豆子は四肢をもがれそうになった。そんな彼女の危機を救ったのは、兄ではなく善逸だった。
「禰豆子ちゃんは 俺が守る」(我妻善逸/7巻・第60話「二百人を守る」)
■禰豆子を「守る」善逸
禰豆子は以前も善逸に「守られた」ことがあった。まだ事情を知らない伊之助(いのすけ)から、「鬼だから」という理由で攻撃されたことがあったのだ。それを助けたのも善逸だったが、その時、禰豆子は「箱」に入ったままだったので、善逸の姿を見てはいない。
それに対して、無限列車内の救出シーンでは、禰豆子は戦闘中の善逸の姿をかなり間近で見ることができた。善逸の強さと、自分を「守る」という言葉に、禰豆子の心が動く。
禰豆子は鬼だ。ともすれば、炭治郎に匹敵するほどの強さを持ち、傷の修復力は鬼殺隊の隊士よりはるかに上だ。しかし、そんなふうに強い「鬼の禰豆子」を見ても、善逸は彼女のことをまるで「か弱い人間」のように扱った。善逸にとって禰豆子は、守らねばならない人のひとりなのだ。陽光という弱点、鬼を滅殺する集団の中での危険な戦闘、長時間の睡眠の必要性など、禰豆子のパワーの”不安定さ”を考えれば、善逸の判断は正しい。
■なぜ善逸には“ひとり”で戦う場面が多いのか
「鼓屋敷」で正一くんを守った時、伊之助に攻撃されそうな禰豆子を守った時、「那田蜘蛛山編」で炭治郎と禰豆子が危険な鬼の住処に入山してしまった時など、自分が誰かを守らなくてはならない時、善逸は“強くなる”。そうした場面で善逸は単独で戦い、その「強さ」を発揮してきた。この特性のため、善逸の初期の戦闘シーンは“ひとり”なのだ。
無限列車編でもそうだった。煉獄と猗窩座の死闘の最中、その場から離れることができない炭治郎と伊之助の代わりに、車両のけが人たちをフォローし、日光が弱点である「鬼の禰豆子」を太陽から守った。炭治郎が戦いに集中し、禰豆子への注意が散漫になってしまった時、善逸は身を挺して彼女を守り続ける。善逸の集中力と戦闘力は、「誰かを守る時」に飛躍的に上昇する。無限列車の戦いで、善逸のフォローがなければ、禰豆子はかなり危険な状態にさらされていたはずだ。激しい列車の横転と、上弦の参ですら逃走する陽光から、善逸はたったひとりで禰豆子を守った。個人で柔軟に状況に対応できる善逸の機転が、この後の戦いでも生かされていく。「孤立」した状況と、「他者への愛」が善逸を強くする。
■ひとりで戦う善逸
無限列車編後、善逸は任務に出かけることを嫌がらなくなる。煉獄の死が、そして“煉獄の死”に胸を焼かれる仲間たちの悲嘆が、善逸を大きく成長させた。この後の「遊郭編」では、善逸は仲間たちと「連携しながら戦う姿」を徐々に見せるようになる。
そうして皆と戦えるようになった善逸だったが、最終決戦では、再び“ひとり”で戦うことになる。今度は「眠る」ことさえ許されない。最大の悲しみが善逸を襲い、その苦悩に善逸はたった1人で向き合うのだ。勝利というにはあまりにもつらい「決戦」が、彼を待ちかまえる。
「無限列車編」は、善逸の大きな転換期のエピソードでもあった。「遊郭編」では、善逸の姿に新たな成長をさらに感じることができるだろう。
鬼滅月想譚 『鬼滅の刃』無限城戦の宿命論
商品価格¥1,650 詳細はこちら ※価格などの情報は、原稿執筆時点のものになるため、最新価格や在庫情報等は、Amazonサイト上でご確認ください。
◎植朗子(うえ・あきこ)
1977年生まれ。現在、神戸大学国際文化学研究推進センター研究員。専門は伝承文学、神話学、比較民俗学。著書に『「ドイツ伝説集」のコスモロジー ―配列・エレメント・モティーフ―』、共著に『「神話」を近現代に問う』、『はじまりが見える世界の神話』がある。AERAdot.の連載をまとめた「鬼滅夜話」(扶桑社)が11月19日に発売されると即重版となり、絶賛発売中。

























