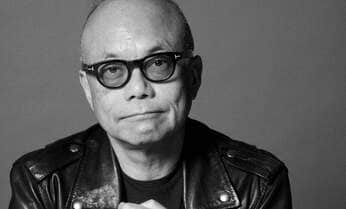
妻夫木聡は邦画界に欠かせない俳優 『ある男』の快挙にもらい泣き
延江浩(のぶえ・ひろし)/TFM「村上RADIO」ゼネラルプロデューサー (photo by K.KURIGAMI)
TOKYO FMのラジオマン・延江浩さんが音楽とともに社会を語る、本誌連載「RADIO PA PA」。「映画『ある男』」について。
* * *
最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀脚本賞、最優秀主演男優賞、最優秀助演男優賞、最優秀助演女優賞、最優秀録音賞、最優秀編集賞と、映画『ある男』が本年度日本アカデミー賞8部門獲得の快挙を成し遂げた。
原作は平野啓一郎さんの同名小説。平野さん然(しか)り、主演男優賞に輝いたブッキーこと妻夫木聡さん然り、長年親しくさせてもらっている友人二人が深くかかわっている作品だけに、吉報が何より嬉しかった。
「文學界」2018年6月号に掲載された原作のリードには、「愛にとって、過去とは何だろう? 人間存在の根源に迫る最新長編」とあった。
550枚を一挙に読み、感動に震えながらラジオ番組の取材先、兵庫・淡路島で待つ平野さんに開口一番、「素晴らしい!」と伝えたのがつい先日のようだ。
初日取材後の夕食の席だったが、駆け付けた僕は立ったまま平野さんに握手を求めた。羽田から空路徳島へ、気分が高揚し、夜の大鳴門橋を渡っての道中が何とも長く感じられた。
そして、この小説は書籍化されると読売文学賞を受賞したが、そのストーリーは……。
主人公・弁護士の城戸への相談は何とも奇妙なものだった。
次男を脳腫瘍(しゅよう)で失ってしまった傷が癒やされることなく、離婚した女性は故郷に戻って再婚、新たに生まれた女の子と穏やかな日々を送っていた。ところが夫は事故死、そこで衝撃の事実が明らかになる。
「愛したはずの夫は、まったくの別人でした」
夫はどんな人物で、どんな人生を送っていたのか、身元を調べて欲しい。妻からのそんな依頼だった。
「ある男」の正体を追う弁護士に妻夫木聡さん、依頼人の主婦里枝役に安藤サクラさん、「ある男」として別の人生を生きた大祐役は窪田正孝さん。彼らの演技に人生の極を感じ、その儚(はかな)さと切なさに僕はしばらく席を立つことができなかった。
『ある男』(大ヒット上映中)(c)2022「ある男」製作委員会
『ある男』(大ヒット上映中)(c)2022「ある男」製作委員会
また、弁護士城戸と、刑に服しながらも真相への手がかりを与える詐欺師小見浦憲男役柄本明さんの壮絶なやりとりは、「羊たちの沈黙」のジョディ・フォスターとアンソニー・ホプキンスの鬼気迫る対決に匹敵するシーンのようにも感じ、隠された真実への道のりの過酷さを象徴していた。
映画館から自宅に帰るまで、往来をゆく顔、顔、顔を眺めながら、彼らのプロフィールは果たして本人が記した履歴書通りなのだろうか。そんなことまで考えた。
日本アカデミー賞受賞の場で石川慶監督へ感謝の言葉に触れた妻夫木さんは、こらえきれずに感涙にむせんでいた。自分の受賞のところでは泣かなかったのに、監督のところで泣いてしまったのは、「監督の苦労を目の前でずっと見てきたから、込み上げてしまいました」
僕もブッキーのそんな言葉にもらい泣きした。
優しさと人生への思いやり。役への真摯な取り組みとストーリーに対しての洞察。山田洋次、阪本順治、行定勲、犬童一心、李相日、三谷幸喜など名だたる映画監督作品に出演、俳優・妻夫木聡は日本映画になくてはならない俳優だ。ブッキー、おめでとうございます!
『ある男』(大ヒット上映中)(c)2022「ある男」製作委員会
『ある男』(大ヒット上映中)(c)2022「ある男」製作委員会
延江浩(のぶえ・ひろし)/1958年、東京都生まれ。慶大卒。TFM「村上RADIO」ゼネラルプロデューサー。小説現代新人賞、アジア太平洋放送連合賞ドキュメンタリー部門グランプリ、日本放送文化大賞グランプリ、ギャラクシー大賞など受賞。新刊「松本隆 言葉の教室」(マガジンハウス)が好評発売中※週刊朝日 2023年4月7日号

























