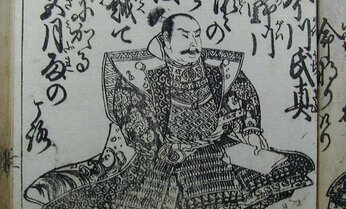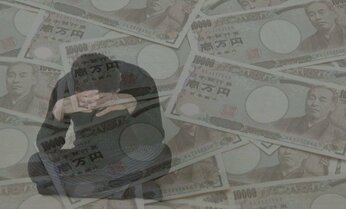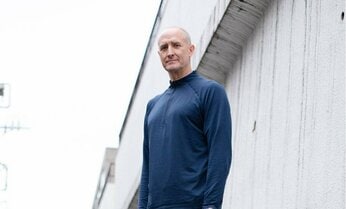女性社長の名前 12年連続「和子」が最多はなぜ? 背景に日本企業の深刻な事情も
写真はイメージです(gettyimages)
東京商工リサーチによると、全国の女性社長は2023年に61万2224人に上り、初めて60万人を超えた。一番多い名前は「和子」で、12年連続トップだという。「和子」が首位の座に長く君臨するのはなぜか。
23年の女性社長の数は、調査を始めた10年から13年間で約3倍に増えた。今や全国の社長の6~7人に1人が女性にあたる計算だ。女性社長の割合も年々緩やかに上昇しているという。
女性社長が増えた理由について、東京商工リサーチは、創業支援など女性の活躍推進に向けた国や自治体の取り組みが効果を上げている点や、同族経営で高齢の代表者から妻や娘に事業を引き継ぐケースが増えていることなどを挙げる。
女性社長の名前で最も多かった「和子」は6184人だった(次のページの表)。2位の「幸子」(5745人)や3位の「洋子」(5575人)、4位の「裕子」(4877人)を引き離して首位が続いている。東京商工リサーチの担当者は言う。
「『和子』は昭和初期から20年代半ば(1950年前後)まで生まれ年別で最も多くつけられた人気の名前です。男性も含めて国内の社長は全体的に高齢化が進んでいることもあってトップが長く続いているのではないでしょうか」(情報本部)
例えば、明治安田生命が同社の保険契約者などを対象に毎年行っている生まれ年別の名前の調査をみると「和子」は昭和2(1927)年から昭和27(1952)年までの25年間のうち、昭和15(1940)、昭和17(1942)、昭和24(1949)年の3回を除いてずっと1位だった。「和子」が首位を譲ったこの3回も、いずれも2位に踏みとどまっている。
【こちらもおすすめ】
「あらゆる選択肢を排除せず」なら為替介入の寸前? 市場関係者の当局口先介入“早見表”を入手
https://dot.asahi.com/articles/-/201276
「和子」がこの時期に人気だった理由として、昭和の年号から「和」の字を取ったことがよく挙げられる。この時期(1927~52年)に生まれた人は、今年、71~96歳になる。
東京商工リサーチの別の調査「全国社長の年齢」によれば、今年1月に発表した直近の22年で社長の平均年齢は63.02歳で過去最高となった。社長の高齢化は進み、60代以上の割合は6割を超え、70代以上も33.3%を占める。
こうした状況を考え合わせると「和子」の1位はもう少しの間続くかもしれない。前出の担当者は続ける。
「あくまで肌感覚ですが、名前に関して今後1~2年の間は状況は変わらないかもしれません。でも、あと10年くらい経つと違った形になっている可能性は高そうです」
「和子」はいつまで1位であり続けるか。キラキラネームが上位に顔を出すのはいつか。企業の新陳代謝やトップの世代交代が進んだり、女性の活躍の場が一段と広がったりすれば、別の名前が取って代わるタイミングも前倒しされるかもしれない。
(AERAdot.編集部・池田正史)