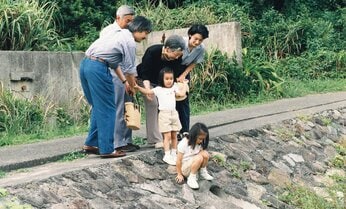引退発表した鈴木おさむ 29歳のときに起きた出来事とその後に強く感じたこととは
放送作家の鈴木おさむさん
鈴木おさむさんが、今を生きる同世代の方々におくる連載『1970年代生まれの団ジュニたちへ』。今回は、「辞める」ことについて。
* * *
この原稿は10月12日の夕方に書いています。今日、32年間やってきた放送作家業と脚本業を来年、3月31日に辞めることを発表させて貰いました。沢山の方からメッセージをいただきまして、本当にありがたいです。
僕が25年近くお仕事させていただている方からのメッセージで「放てば手に満てり」という言葉をいただきました。手にしているものを手放さないと何かをつかめないという意味ですね。辞めることが怖くないかといえば怖いです。でも、今のまま続けていくのがもっと怖いんですよね。
初連ドラ脚本に挑戦
29歳の時に初めての連続ドラマの脚本に挑みました。「人にやさしく」というドラマでした。初めての連続ドラマで、「笑っていいとも」「SMAP×SMAP」「めちゃめちゃイケてるっ」の3本はドラマの出演者も出ていたのでやっていたのですが、あとは半年お休みさせていただくことにしました。
【あわせて読みたい】
SMAP解散から6年 中居正広と香取慎吾の“対面”を見た鈴木おさむが感じた多くのこととは
https://dot.asahi.com/articles/-/12467
そのときに、お休みさせて貰おうとしたら、結構、クビになりました。「ごめん、それだったらいいや」と。でも、そんななか、「いきなり!黄金伝説」のプロデユーサーは、「頑張って来いよ! 休んでる間もギャラは払い続けるから! 戻ってきてよ。期待してる」と。
なんと。半年間、会議も行ってないのにギャラを払い続けてくれたのです。数百万円ですよ。
でも、おもしろいもので、半年たって戻ったときに、その「黄金伝説」をきっかけに、そのスタッフからまた番組は増えていきました。
クビになった番組は、正直、自分のハマりが悪い番組でした。失った番組も多かったけど、その「黄金伝説」きっかけの番組がどんどん増えていき、クビになった番組の本数をすぐに超えていきました。
だから、「手放すこと」の大事さを、そのときに強く感じました。
そしてもう一つ。ここで書いておきたいこと。
【あわせて読みたい】
天国に旅立たれた鈴木おさむのただひとりの師匠。 僕もこれから、逃げずに、人の夢の種を撒いて生きます
https://dot.asahi.com/articles/-/39625
僕はここ数年、仕事で「怖い」と言われることが多くなりました。自分は笑顔のつもりだったのですが、そうじゃない。
最近、思っていることがあります。努力を努力と思わない才能というものがあります。
成功してる人は努力と感じてない。
僕もありがたいことに若い頃から努力を努力と思っていなかった。だけど、作家を始めて3年ほどたったときに後輩が入ってきて、自分がそれまで当たり前にやってきたことをやらせたら辞めてしまいました。
ここ数年、番組などを成功させるための自分の当たり前が当たり前じゃなくなっていたんだと思います。自分でやった方がいいと思ってやったことが、冷たく思われたり。
「怖い」と思われていた!
おもしろく言ってるつもりが、相手はそう感じていなかったり。
だから「怖い」と思われていたことが多い。
これは本当に駄目だなと思っています。僕と近い年齢の方は、こういう経験結構あるかもしれませんね。
人を楽しませるためのものを作っているのに、近くにいる人を傷つけているのって、本当に駄目だなと。
それを一度リセットするためにも、「辞める」ことが必要なんだと思います。
スイッチをオフにしたところから、今一度大切にしなければいけないものを確認しないといけないんだなと。
ただ、あらためて、この辞めるという決断を受け入れてくれた人、そして仕事をしている人たちには本当に感謝しています。
この半年、辞めるということに向き合いながら、辞めるからこそ出来るものを作っていきたいと思います。
鈴木おさむさん、大島美幸さん夫妻(本人ブログから)
夜店でスーパーボールすくいをする鈴木おさむさんと息子の笑福君、後ろで見守る妻の大島美幸さん(本人インスタグラムから)
キックボクシングのトレーニングの様子=本人のインスタグラムから
大島美幸
■鈴木おさむ(すずき・おさむ)/放送作家。1972年生まれ。19歳で放送作家デビュー。映画・ドラマの脚本、エッセイや小説の執筆、ラジオパーソナリティー、舞台の作・演出など多岐にわたり活躍。パパ目線の育児記録「ママにはなれないパパ」(マガジンハウス)、長編小説『僕の種がない』(幻冬舎)が好評発売中。漫画原作も多数で、ラブホラー漫画「お化けと風鈴」は、毎週金曜更新で自身のインスタグラムで公開、またLINE漫画でも連載中。「インフル怨サー。 ~顔を焼かれた私が復讐を誓った日~」は各種主要電子書店で販売中。コミック「ティラノ部長」(マガジンマウス)が発売中
【あわせて読みたい】
「結婚はあまりお勧めしません」鈴木おさむが結婚16年目に思うこと
https://dot.asahi.com/articles/-/115846