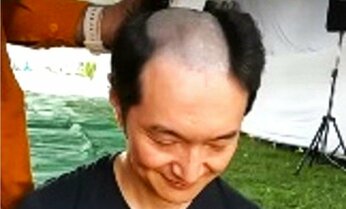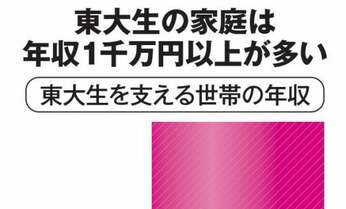健康、お金、孤独の「3大不安」を軽減するには 「老後」という考え方をやめるメリット
老後に対する不安はつきものだが……(※写真はイメージです Getty Images)
老後のこと考えると、どうしてもお金や健康の問題、孤独感などがつきまとうもの。そんな老後不安をいかにコントロールするかが、人生の後半戦の幸福度を左右する。医師の小林弘幸氏は、定年後の隠居生活を意味する老後を「やめる」マインドが大切だという。朝日新書『老後をやめる 自律神経を整えて生涯現役』から一部を抜粋、再編集して解説する。
* * *
老後をやめると「3大不安」は怖くない
朝日新聞のアンケートでは、回答者の97パーセントが「老後の生活に不安を感じる」と答えていました。では、具体的にどんなことに不安を感じているのでしょうか。内訳を見ていきましょう。
圧倒的に多いのは、「自分が病気になる」(76パーセント)、「介護が必要になる」(73パーセント)といった健康面についての不安です。
次に多いのは、「収入が減ってしまう」(33パーセント)、「資産が予定より早く枯渇してしまう」(32パーセント)といったお金に関する不安。
そして「社会とのつながりが希薄になる」(33パーセント)といった孤独についての不安です。
つまり、老後の3大不安は、「健康」「お金」「孤独」であることが、このアンケート結果から浮かび上がってきます。
【こちらも話題】
失敗学の提唱者も陥っていた「大失敗のパターン」 免許返納を勧めた家族が駆使した「知見」
https://dot.asahi.com/articles/-/212872
いずれも一筋縄ではいかない、難しい問題です。しかし、老後をやめることで、これらの不安は解消、少なくとも軽減することが可能だと私は考えています。
(1)健康の不安
みなさんは「健康寿命」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。「健康上の問題によって日常生活が制限されずに、自立して暮らせる期間」のことです。
わかりやすくいえば、「介護なしで元気に暮らせる年齢」といえるでしょう。
厚生労働省が発表した2019年の最新データでは、男性の健康寿命は72.68歳、女性の健康寿命は75.38歳。平均寿命と健康寿命の差は9~12年、平均余命と比べると13~15年もの差があることがわかります。
この差が、「健康上の問題で日常生活に制限があり、自立困難な期間」です。思ったより長いと感じませんか? この数字を突きつけられると、多くの人が不安に思うのも理解できます。
この差を縮めるにはどうすればよいでしょうか。もっとも重要なのが、「老後をやめる」というマインドです。
私はこれまで、自律神経をキーワードに、健康寿命を延ばすためのさまざまなアドバイスをしてきました。食事から、運動、睡眠、リラクゼーションまで、分野は多岐にわたります。
【こちらも話題】
歩く速度が遅くなって出会えた「気づき」 失敗学の提唱者が気づいた「よい老い方」と「悪い老い方」
https://dot.asahi.com/articles/-/212366
しかしあるとき、マインドを変えなければ、私のアドバイスはすべて無意味であることに気づきました。
たとえば、「スクワットを毎日やりましょう」とおすすめしても、老後マインドにおちいっている人は、「いまさら何をやっても意味がない」とか、「どうせもうすぐ死ぬのだから」とか、「もう年だからそんなことをするのは無理」とか、言いわけをつくって取り組もうとしません。
逆に、いつまでも若い人は一生チャレンジだと思っていますから、「面白そうだからやってみよう」「今日は5回できた、明日は6回にチャレンジだ」と、みずからすすんで取り組みます。
そういう人は日中、アクティブに動いているので夜はよく眠れますし、食事もしっかりとることができる。毎日、若者のようにワクワクして生きているので、自律神経も整っています。
そういう生活をしていても、病気になったり、介護が必要になったりすることはあるでしょう。しかし少なくとも、「病気になったらどうしよう」とか、「このままでは介護が必要になる」といった不安におびえることはなくなるのです。
(2)お金の不安
2019年、金融庁が発表した「老後の30年間で約2000万円が必要」という試算が、世間で論議を巻き起こしました。いわゆる「老後2000万円問題」と呼ばれるものです。
2000万円という数字は、なかなかインパクトがあります。「そんなお金なんて持っていない」と不安をおぼえた人は多いでしょう。
【こちらも話題】
穏やかな在宅看取りを阻む人は誰? 救急車を呼んでしまう理由は「親族が納得しない」 95歳父を息子が介護
https://dot.asahi.com/articles/-/208723
お金を持っている人でも、「資産が予定より早く枯渇してしまうかもしれない」とか、「想定以上に長生きするかもしれない」といった不安を感じている人がいるようです。
こうしたお金の不安も、「老後をやめる」ことで一気に解消します。
わかりやすいのが、私の父の例です。父は家庭教師の仕事で、今も収入を得ています。年金もあるので、「老後2000万円問題」とはまったく無縁です。
金融庁の試算によれば、不足するのは「月5.5万円」とのこと。ちょっとしたアルバイトや副業くらいはできるのではないでしょうか。
実際、今は多くの人が定年後も働いています。内閣府の「高齢社会白書」によると就業率は年々上昇しており、2022年は60~64歳が73.0パーセント、65~69歳が50.8パーセント、70~74歳が33.5パーセント、75歳以上でも11.0パーセントの人が仕事をしています。
最近は少子化もあって、どこの企業も人手不足が問題になっています。そのため、以前よりも求人が豊富ですし、年齢も問わなくなってきています。また、最低賃金が引き上げられるなど、待遇もよくなっています。
また、働いていれば年金に頼らなくてすむので、年金受給を繰り下げることも視野に入ります。たとえば、70歳まで繰り下げると最大で42パーセント増額、75歳まで繰り下げれば最大で84パーセントもの増額になります。
【こちらも話題】
「もう65歳だから」と絶対口にしてはいけない…和田秀樹「実年齢より老け込んで見える人に共通する態度」
https://dot.asahi.com/articles/-/208768
貯金が少なくても、年金が少なくても、これだけ働く環境が整っているのです。老後をやめさえすれば、お金の不安を必要以上に感じることは減ります。
(3)孤独の不安
定年を迎えて、人間関係のストレスから解放されたと思ったのもつかのま、今度は孤独というストレスに襲われる。よく耳にする話です。
もともと人間は、群れで生きる動物です。自然界で群れからはぐれることは、猛獣に襲われたり、食べものを得ることができずに飢えたりなど、死に直結する非常事態でした。だからこそ、孤独は大きなストレスになるのです。
フロイトやユングとも並び称される心理学の巨人、アルフレッド・アドラーも、人間には「共同体感覚」が必要だと述べています。
共同体感覚とは、家庭、地域、職場などにおいて、人とつながっていると感じることを指します。人はこの感覚を感じられるとき、幸福を感じるとアドラーはいっています。
孤独にさいなまれる人は、会社一筋で生きてきた男性に多い傾向があります。定年を迎えたとたん人とのつながりが一気に失われてしまうため、うつ状態になったり、酒びたりになったり、引きこもりがちになったり、深刻な事態におちいることもあるようです。
たびたび例に出して恐縮ですが、私の父は孤独とは無縁の毎日を送っています。
妻には先立たれてしまいましたが、家庭教師で教えている子どもたち、その親御さん、ご近所の方々をはじめ、多くの人とつながりを持っています。ですから寂しいという感覚はないそうです。
人とのつながりがあれば、万が一のときも安心です。近年、孤独死が社会問題になっていますが、老後をやめる人が増えていけば、この問題も解決に向かうのではないでしょうか。
【こちらも話題】
「この家は悪夢そのもの」 妻は認知症、夫が心臓病の老夫婦の最期を2分割画面で描く一作
https://dot.asahi.com/articles/-/207508