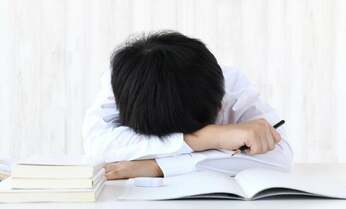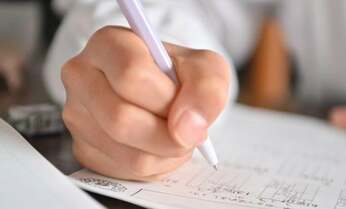検索結果1396件中
681
700 件を表示中

...問題へ 人間力や家庭の在り方も試される【中学受験2023】
中学入試問題の傾向は?(※写真はイメージです/GettyImages)
中学入試は、知識をどれだけ習得したかが合否の分かれ目になっていましたが、今、入試の問題は過去に比べて様変わりしています。社会問題を取り上げて「あなたの考え」を問うなど、知識だけでは解けない問題が増えています。
* * *
声の教育社の常務取締役・後藤和浩さんは、近年の入試問題について次のように話す。
「一問一答形式が減り、社会的な問題に対して自分の考えを述べさせる出題が増えています。以前から難関校には見られましたが、最近では中堅校にもその傾向が及んできました」
入試問題を見ると、その学校がどういう学力を大事にしているか、教育観がわかるという。その一例として取り上げたのが今年の開成と麻布の社会の問題だ。
「開成の社会は、知識問題が60%でした。あやふやな知識では太刀打ちできない、しっかりとした知識が求められています」
一方で麻布は、知識問題は20%だったという。
「たとえば累進課税制度がテーマの問題が出されたのですが、その用語を問うのが普通の問題です。麻布では、累進課税に賛成する立場として二つの意見を記述させる問題でした。累進課税は立場によって賛否分かれるのですが、自分とは異なるかもしれない意見を、あえて書かせるのはさすがだと思いました」
■学校だけでなく、家庭の在り方が問われる問題も
今年は時刻表を掲載して出題した学校が複数あった。ただし、設問が学校ごとに異なっている。たとえば東邦大東邦は、成田から最短時間で、北海道に先着している友人と待ち合わせる交通手段の問題が出題された。開智は1964年の9月と10月の二つの時刻表を並べて、走行列車の違いを問う問題を出題した。高輪は八丈島行きの大型客船、航空機、さらに八丈町営バス循環路線の時刻表3種を掲載。交通手段をXYZにして時刻表だけを示し、どれが客船、航空機、バスかを考えさせた。
なかには学校だけでなく、家庭の在り方が問われる問題も。
「渋谷教育学園幕張では、葬式や通夜の帰りに、家の中にケガレを持ち込まないようにするためにどのようなことをするか、という問題が出されました。これは知らなければ解けない問題です」
記述が増えたのも特徴で、国語や社会の文系科目だけでなく算数や理科にも及んでいる。
「算数では、答えに至るまでの考え方、途中式を書かせる学校が増えてきました。計算ミスなどで答えにたどり着けないとき、途中式もすべて消してしまう生徒がいるのですが、残しておくべき。途中のプロセスを評価して加点する学校も多いです」
■学校を選ぶときは入試問題をみてほしい
「学校の先生は、入試問題にいろいろな思いを込めて作っています。生徒にこういう力をつけてほしいという、学校のアピールでもあるんです」
その例として挙げるのが、栄東の東大特待Iの国語だ。問題文として出されたのは、杉山修一氏の『ここまでわかった自然栽培―農薬と肥料を使わなくても育つしくみ』の本文。専門的な内容で、大人でもてこずりそうだ。後藤さんが調べたところ、1ページ1063字のうち、漢字512字、その他ひらがななどが551字で、ほぼ半分が漢字だったという。
「この文章を、初見で読解できる児童はほぼいないでしょう。ただ、第1問から解き進んでいくと、徐々に理解できるような構成になっているんです。まるで授業を受けているようです」
加えて、後藤さんが最近の入試の傾向として挙げるのが「人間力」だ。たとえば慶応湘南藤沢では国語の問題で、「甘いモノは体に悪いから課税して値段を上げるべきだ」という主張に対して、反論を述べさせた。他者への理解が必要な問いだ。
これからも、こういった傾向は広がりそうだ。
「学校を選ぶときには、パンフレットやホームページを見ることが多いと思いますが、ぜひ入試問題も見てほしい。どういう生徒が欲しいのか、学校からのメッセージがわかると思います」
一方で新タイプ入試も堅調だ。実施する学校は147校と前年よりも3校減ったが、受験者数は17,067人から17,703人と逆に増えている(首都圏模試センター調べ。推定値を含む。新タイプ入試:適性検査型・総合型・思考力型・プレゼン型など含む。英語入試は除く)。選抜方法も適性検査型、自己アピール型、思考力型、総合・合科型などさまざまな方法が導入されている。最近人気なのが自己アピール型入試で、スポーツや習い事、趣味など、小学生時代に打ち込んできたことをプレゼンテーションする。ICT教育の高まりを受けて、プログラミング入試を行う学校も増えている。
首都圏模試センター取締役教育研究所長の北一成さんは、新タイプ入試について次のように話す。
「塾に3年間通わなくても自分の好きなことを続けながら、自分の得意分野で受験できる。中学入試の門戸を広げた意義は大きいと思います」
新タイプ入試は、自分の得意なことでトライできるので学校に対してポジティブな気持ちで臨み、行事やクラブ活動などに積極的に取り組む生徒が多いという。
大学が入試改革を進めていくなかで、今後中学入試はどうなっていくのか、注目していきたい。
(柿崎明子)
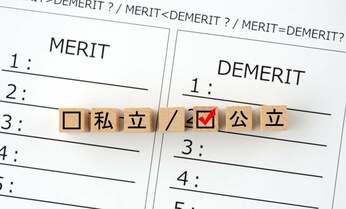
...した理由は? 東京の男女枠撤廃にも注目【中学受験2023】
公立中高一貫校の志願者は年々減少している(※写真はイメージです/GettyImages)
公立中高一貫校の倍率は、開校当初に比べて落ち着いてきましたが、それでもまだまだ高倍率です。東京では私立と併願する受検生が増え、公立と私立の垣根が低くなっています。
* * *
首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)全体の公立中高一貫校の志願者は年々減少し、倍率も下がっている。今年は首都圏すべての都県で減少した。栄光ゼミナール公立中高一貫校受検責任者の宮田篤史さんは、次のように話す。
「ここ数年、受検者は毎年1~3%減少しています。ただし易しくなったわけではありません。以前のようにお試しで受ける受検生が減ったためです。塾などでしっかりと対策をして、臨むようになってきました」
■都内では公立中高一貫校の高校募集がなくなった
東京では、白鴎(台東区)が今年から高校募集を停止した。これで都内すべての公立中高一貫校の高校募集がなくなり、内部進学のみになった。白鴎の募集定員は前年に比べて34人増え、志願者も増えたが倍率は5.0倍から4.2倍に下がった。
最難関の小石川(文京区)は志願者が712人から745人に増加した。
「全体に私立との併願は増えていますが、特に小石川は御三家クラスの難関校との併願が多い。毎年50人程度の欠席者がいますが、私立中に合格したために受検しなかったと思われます」(宮田さん)
小石川ほどではないものの、桜修館(目黒区)や白鴎、両国(墨田区)、千代田区立九段でも入試当日の欠席や入学手続きの辞退者が目立つ。一方で武蔵(武蔵野市)、立川国際(立川市)、南多摩(八王子市)などはそれほど多くない。
「地域性もあります。東エリアは難関私立が集まっているので私立を第1志望にして公立を併願校に、逆に西エリアでは公立を第1志望にする受検生が多いためと思われます」(宮田さん)
例年比較的志願者が多いのが桜修館だ。特に女子に人気で6~7倍と高い倍率で推移している。23区外では三鷹(三鷹市)が、志願者が多い。
「武蔵が高難度であることが広く浸透しており、近隣の三鷹に志願者が集まっています」(宮田さん)
立川国際は662人から494人と志願者を大きく減らした。小学校が併設されて移行期にあたることから、敬遠された模様だ。
神奈川では昨年の県立2校に引き続き、今年は横浜市立の南高附、横浜サイエンスフロンティア高附が男女枠を撤廃した。まだ入学予定者の男女比は発表されていないが、ある程度は予測可能だという。
「県立を例に取ると、男女別で募集されていたときに、倍率が高い方の人数が多くなっています。ですから、南高附なら女子、横浜サイエンスフロンティア高附なら男子が多くなるのではないでしょうか」(宮田さん)
千葉では昨年、市立稲毛(千葉市)が併設型から千葉県で初の公立中等教育学校になり校名も稲毛国際に変更した。昨年度はその期待値から、志願者が250人ほど増えて約850人になり、今年もその水準で推移している。
「千葉も全体的に志願者が減少していますが、もともと募集定員が少なく倍率が高い地域。東葛飾(柏市)の男子はほぼ10倍です。他の都県に比べると、まだまだチャレンジ層が多いと言えるでしょう」(宮田さん)
埼玉は伊奈学園で志願者が75人減少したが、その他3校の志願者数は横ばいで、3回目の入試を迎えた川口市立は男女とも約5倍である。
「他の都県に比べ私立中との併願は少なく、私立と公立で受験(検)者が分かれる傾向です」(宮田さん)
■注目は東京の男女枠撤廃
次年度以降、神奈川の市立川崎で面接が廃止されることが発表されている以外は、大きな変更は公表されておらず、受検者動向も今年を踏襲しそうだ。
「変化が起こるとすれば、世の中の状況に左右されそうです。景気が悪化すれば公立を選ぶ層が増える可能性もあります。またコロナが一段落し、どの学校もいろいろな活動を再開しているので、人気に変化が出てくるかもしれません。学校間では、東大を主とした大学進学実績で差が付いてくるでしょう」(宮田さん)
注目されているのが、東京の男女枠だ。神奈川が全校撤廃し、都立高校でも2024年度入試から男女枠を撤廃する方針を打ち出している。その影響が都立の中高一貫校にも及ぶ可能性はある。
「おおむね女子の方が合格最低点が高い傾向にあり、男女枠が撤廃されたら女子の競争は少し緩和し、逆に男子が厳しくなるかもしれませんね」(宮田さん)
今後の動きをしっかり見ておこう。
(柿崎明子)