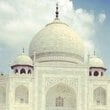コロナ禍を機に働き方が変化した。パーソル総合研究所(東京)が今年2月に実施した調査によると、テレワークを実施する従業員の80.2%が「今後も続けたい」と回答。同社が昨夏実施した調査の78.6%から微増し、好意的な受け止めが多い。
一方で、内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」の2021年4~5月の結果によると、労働時間が「大幅に増加」「増加」「やや増加」と回答した人が合計12.8%いた。「大幅に減少」「減少」「やや減少」と回答した人は33.4%で、比較すると「増えた」のは少数派ではあるものの、一定数存在していることがわかる。
「自宅で仕事をする」イコール「いつでも仕事ができる」という認識が広がり、以前ならば考えられなかった時間に働いているという人もいる。
■朝7時、夜10時に面談
大学教員をしながらキャリアカウンセラーとしても働く都内の女性(45)は、面談が午前7時や午後10時といったデイタイム以外に入ることが大幅に増えたという。以前は、対面が基本だったから、遅くとも午後9時には終わり、早朝の面談はほぼなかった。女性はこうこぼす。
「悩みを聞く仕事で、相手には『落ち着いて話せる時間にしましょう』と言っているわけだから、仕方ない。でも、名刺交換などちょっとしたアイスブレークもなく、のりしろがない状態で仕事が続いてしまうこともつらい」
著書『ルポ コロナ禍で追いつめられる女性たち』(光文社新書)の中で、テレワークの明暗を取材したノンフィクションライターの飯島裕子さんは、
「非正規雇用とテレワークは相性が悪く、正社員は自宅にいるけど、自分は出社しなければならないなど選択肢のない人たちの話を多く聞いてきた。テレワークを選べる環境にある人は、恵まれている」
とした上で、こう指摘する。
「テレワークには、落とし穴がある。長時間労働に陥っていないか、心身の不調が出ていないか。雇用されている場合は、企業側がきちんと管理する必要があるし、働きすぎる人は、この時間以降はパソコンを開かないなどのマイルールを作って自衛したほうがいい」
(編集部・古田真梨子)
※AERA 2022年5月16日号より抜粋




![AERA (アエラ) 2022年 5/16 号【表紙:ウルトラマン】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UP0ChByPL._SL500_.jpg)