パーキンソン病と、パーキンソン病に似た別の病気とは、はじめのうちはなかなか区別がつかないことがあります。そのような場合、脳MRIに加えてラジオアイソトープを用いた画像検査が役に立つこともあります。「ドパミントランスポーターシンチグラフィー」は、脳内のドパミンをつくる神経細胞が減っているかどうか画像で確認する検査です。「MIBG心筋シンチグラフィー」は、心臓の交感神経を映し出す検査で、パーキンソン病では比較的早期から異常がみつかります。
もうひとつ役に立つのは「L-ドパ製剤」の効果をみることです。「L-ドパ製剤」で明らかに症状が軽くなるのはパーキンソン病だけです。別の似た病気の場合、効果があってもごくわずかか、ほとんど症状が変わりません。そこで、診断をつけるために、薬をいったん服用し、効果があるかどうかを確認することもあります。
パーキンソン病の診断は、このように問診や診察、画像検査、治療薬の効果などから総合的におこないます。すぐに診断がつくこともありますが、ほかの病気との区別が難しいケースでは、数カ月かかること、入院して詳しく調べることもあります。
パーキンソン病は「治療法がない」など誤解の多い病気で、パーキンソン病と診断されるとショックを受け落胆する人が多いようです。なかには、意欲が低下して仕事の整理をし始めるなど、すぐに病気を受け入れられず、受容に1年、2年とかかる人もいます。
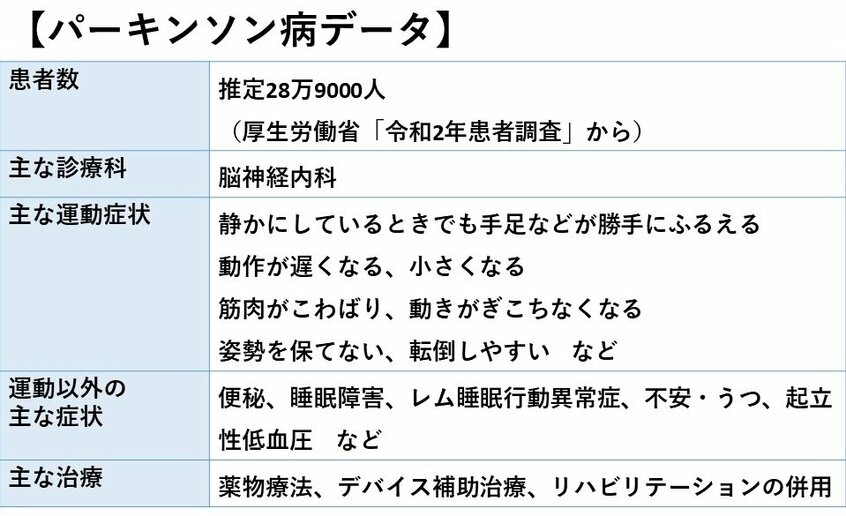
「落胆している患者さんには、高血圧や糖尿病などと同様、パーキンソン病も薬で症状をコントロールできる病気であることを丁寧に説明し、『治療を早めに開始して、仕事も趣味もできるだけ続けましょう』とお話しします。実際、治療を受けながら何年も仕事や家事を継続している患者さんがほとんどです。症状が進行するまで放置せずに、早期から治療を開始して日常しっかり体を動かしたほうがいいことがわかっていますが、それでも薬をのむことを不安に思う患者さんがいます。そういった方には、『あとに残るような副作用はまずないので試してみましょう』と励ましてみます。治療の効果を実感できると、気持ちも前向きになる方が多いようです」(大江田医師)




































