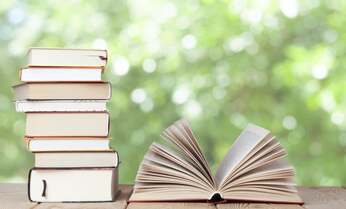熟年離婚しないためには? AV界の巨匠・代々木忠「相手を思いやる『対人的感性』が必要不可欠」
代々木忠(よよぎただし)/ 1938年、福岡県生まれ。若き華道家として将来を嘱望されるが、親友に請われて極道となる。カタギに戻ってからはピンク映画を経てビデオの世界へ。2021年に引退するまでAV監督としての作品は約600タイトル。愛称はヨヨチュー。著書に『プラトニック・アニマル』(幻冬舎アウトロー文庫)、『つながる』(新潮文庫)などがある。(撮影/写真映像部・上田泰世)
現代人の愛と性の悩みに回答する『人生を変えるセックス 愛と性の相談室』(幻冬舎新書)が話題だ。著者は伝説のAV監督・代々木忠さん。心の奥まで写し撮るドキュメンタリーの手法でAVを撮り続け、長年、性と向き合ってきた。そんな“ヨヨチュー”の回答には、老後を変えるヒントも詰まっている。そこで、中年・熟年世代の「あるある」の悩みに回答してもらった。
* * *
Q:セックスが好きじゃないのは問題ですか?
A:セックスが好きじゃない人はたくさんいます。嫌いとまでは言わないけれど、あまりしたくないという人まで含めると、セックスに興味を持てない人が多数派になろうとしている時代です。
生きる目的や意義は千差万別ですが、人はみな「快」によって生かされています。いい仕事ができたという達成感は快だし、功名心がくすぐられるのも快なら、収入が増えるのも快。人生における快は至るところに存在していて、セックスで気持ちよくなるのは、そのうちの一つです。
だからセックスなしの人生も、「今」に満足していれば、何の問題があるはずもありません。
余談ですが、人生を重ね、快を求め続けた先にあるのは「利他の心」ではないでしょうか。利他とは自分を犠牲にしてでも他人のために何かをすること。自分だけが幸せになるよりみんなが幸せになってくれたほうが嬉しい。人間とは、本来そう感じる生き物なのだろうとも思うのです。
Q:結婚生活が長すぎて愛がわからなくなります。
A:うちも結婚生活は長いですが、僕がたまにやっているのは、家族の思い出が詰まった昔の写真を見ることです。最初の子どもは生まれてすぐに死んでしまったのですが、そのあと女房と二人で行った伊豆の遊覧船に乗っている彼女のスナップ、そのあと生まれた娘が幼い笑顔で女房と笑い合うスナップなど「あぁ、こういうときがあったなぁ」と家族の歴史を思い出すような写真を見るんです。そうすると胸にじんわりとしたものを感じます。
スマホに準備した回答を読み上げながら取材に応じてくれた代々木さん(撮影/写真映像部・上田泰世)
じんわりとした、そのあたたかいものは、感情です。感情は「今」この瞬間にしか存在しません。この瞬間、瞬間の積み重ねこそが愛ではないでしょうか。いずれにしても愛は定義するものではなく、感じるものです。そして「今」に宿るものだと思います。
Q:熟年離婚しないために大切なことは?
A:僕の作品に出てくれる女性に離婚に至る原因を尋ねると、多くに共通するのは、夫が妻に、妻が夫に、本当の自分を出してこなかったということです。良いところだけでなく、弱点やコンプレックスも全部見せるなかで信頼関係が生まれます。
夫婦間に会話があればお互いにわかり合えている、というわけではありません。
かつて、サイト上で女性からの愛と性の相談に乗っていたころ、やってきた奥さんは離婚寸前という状態でした。旦那さんに何を言っても理屈で返され、それがもう耐えられないと言うのです。旦那さんからすればコミュニケーションが取れている。でも、奥さんが求めているのは論理的な解釈ではなく「心」だったわけですね。これは大きなすれ違いです。一般的な社会生活ならば、頭脳と頭脳のコミュニケーションで成り立ちますが、夫婦生活においては、お互いの心が交わるコミュニオンと、相手を思いやる「対人的感性」が必要不可欠です。
その「対人的感性」は心がイクオーガズムによって成熟します。心と心がつながる営みができれば、セックスレスはもちろん、不倫や離婚、DVや虐待まで激減するのになぁと僕は思うのです。
(構成/大道絵里子)※週刊朝日 2023年6月2日号より抜粋