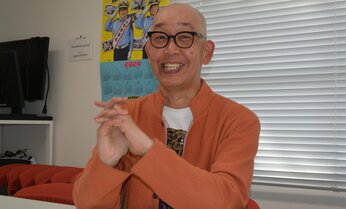【元本保証で金利0.69%】定期預金より個人向け国債「それ以外で良いお金の置き場はコレ」
(イラスト:おーるい みちひさ)
一時1ドル=161円台、金利上昇局面の日本。モノの値上げは止まらない。定額減税や夏の電気代補助では焼け石に水。節約にも限界がある。今すぐ家計の仕組みを変えよう。簡単にできてリスクもほぼ無い、お得な方法は? AERA 2024年7月15日号より。
* * *
6月28日、円は一時1ドル=161円台に乗せた。農産物や製品、エネルギーなどを輸入に頼っている日本は、円安が物価にも影響する。実際、モノの値段は上がりっぱなしで、インフレの様相を呈している。
電気代も、4月使用分から再生可能エネルギー発電促進賦課金が値上げ。ただ、8~10月は政府による電気代補助がある。「低圧電気の8月、9月は1kWh当たり4円、10月は同2.5円の補助。都市ガスの8月、9月は1立法メートルあたり17.5円、10月は同10円の補助」と発表された(6月28日、経済産業省)。だが、この程度では焼け石に水の世帯も多そう。定額減税も、生活が劇的にラクになるレベルではないだろう。
デフレ脱却していない
先ほど、インフレの「様相を呈している」と書いた。インフレとは物価が継続的に上昇する経済状態のことだが、そもそも数値的な定義はあるのだろうか。教養のため、知っておきたい。経済アナリストの森永康平さんに聞いた。
「現状をインフレと表現すること自体は間違っていないと思います。ただ、数値的な条件でいうと『日本はデフレを脱却していない』のです」
え? デフレ? 日本が?
森永さんの解説をまとめると、こうだ。日本はデフレの時代が長かった。内閣府の月例経済報告に「持続的な物価下落という意味でのデフレ状況にある」と記されたのは2001年のことだ。物価が継続的に下がっていればデフレとされる。「持続的な」の根拠として、BIS(国際決済銀行)やIMF(国際通貨基金)で「少なくとも2年間」という古い定義があり、今はデフレであるという内閣府の記述は06年半ばまで続いた。09年にも、国際機関の「2年」には満たなかったが、デフレ状況にあると記されていた。森永さんは、今の日本は政府が06年に発表したデフレ脱却の条件を厳密には満たしていないという。
AERA 2024年7月15日号より
「条件は主に四つあります。まず消費者物価指数が2%超という条件。総務省統計局によると23年の年平均(総合)が20年を100として105.6、前年比3.2%上昇で、これはクリアしています。次に、物価の変動を表す『GDPデフレーター』という指標が前年比プラス。三つ目に、国の経済全体の総需要と供給力の乖離を表す『需給ギャップ』が前年比プラス。四つ目に、1単位のモノを生産するのに必要な賃金を表す『単位労働コスト』が前年比プラス。これらの条件が確実に揃ったら、日本はインフレであると表現されるかもしれません」
勉強になった。06年に示された条件ではあるが、そのときから「正確には」デフレ脱却をしていない、と。
とはいえ「現実的には」インフレ状態にあるわけで、モノの値上がりはこれからも続くだろう。円安傾向も続くのだろうか。
金利上昇メリットは小
森永さんは「個人的観測ですが」と前置きして、こう言う。
「目先、これ以上の円安になる可能性は低いと思います。対ドル円相場は米国と日本の金利差に連動する形で動いています。金利差が縮小すれば円高に動くことが多いわけです。では金利はどうなるか。日銀が植田和男総裁になってから、金利は上昇傾向にあります」
なお森永さんは、金利を上げることに関して消極的だ。
「GDPの中身を見ると、個人消費が4四半期連続でマイナスです。これは08年のリーマン・ショック以来。皆がモノを買わなくなっているわけです。さらに実質賃金は25カ月連続マイナス。そんな中で金利が上がると、たとえば変動金利で住宅ローンを組んでいる人は将来的に返済の負担が増します。これから固定金利で組む人も、現状よりも割高な水準になってしまう。『金利が上がるといいこともある、預金も増えやすいし』という意見もありますが、現役世代で金利上昇により暮らしが潤うほど利子を受け取れる大量の預金を持っている人がそんなにいるのかと(笑)。金利上昇のメリットは、今の大半の日本人には少ない気がしています」
AERA 2024年7月15日号より
金利を上げても物価が下がるわけではない。現在の物価上昇は円安だけでなく、海外でもインフレが起きていることにも起因しているからだ。輸入の多い日本は、海外での値上がりの影響も受けている。
「植田日銀総裁が金利を上げたからといって、世界的なインフレが収まるわけではなく、そこに相関関係はありません」
では米国の金利はどうか。中央銀行や市場参加者が金利動向をどう見ているかを示すデータによると、「現時点では」秋頃に利下げをする見通しだという。日本の金利は上昇、米国は下落。金利差は多少なりとも縮小というのが森永さんの読みだ。
「1ドル=160円台半ばが天井の目安(編集部注:このコメントは24年6月末時点)。年末にかけて円高方向と予想します」
円高方向に動いても、3年前(21年)の1ドル=102円台まで行くことも考えづらい。インフレ、為替水準を踏まえてこれ以上暮らしが苦しくならないよう家計を守らねば。
家計を守りたいのは山々だが、自然に出費はかさみ、給与は上がらず、節約は限界まで来ている。そこで提案したいのは、金利上昇傾向であることを味方につけ、お金の置き場所を変えることだ。金利のある時代に、お金に働かせる。いい響き。
個人向け国債上昇
注目は個人向け国債である。16年から22年の頭まで個人向け国債の金利は地を這っていたが、上がり始めた。24年6月募集分(7月16日発行)の「変動10年」が0.69%(税引き前/以下同)、「固定5年」が0.59%、「固定3年」が0.40%だ。
たとえば0.59%の固定5年を100万円分買うと、初回(25年1月15日)に2933円。それ以降7月と1月に2950円の利子が受け取れる。5年間でもらえる利子の合計は2万9483円だ。
変動10年は、半年ごとに金利が見直され、原則として毎回変動する。金利が今後も上がっていけばもらえる利子も増え、下がれば利子も減る。
下がるといっても最低金利の0.05%は保証されている。金利上昇局面と考えるなら、変動10年にお金を入れて放置しよう。チャリンチャリンと半年に一度、利子が降ってくる。
森永康平さん(もりなが・こうへい)(39)/経済アナリスト。金融機関での株式リサーチ業務などを経て独立。近著『0からわかる!金利&為替超入門』(写真:本人提供)
この先の金利動向なんて自分で判断できず、変動10年と固定5年または3年で迷う人は?
「変動がいいか固定がいいか。住宅ローンでもよく出てくる悩みですね。どっちが得しそうかという観点で考えるから悩んでしまいます。『将来の金利を現時点で固定させたいかどうか』で決めてはどうでしょう。得がしたい人に向かってアドバイスしようとすると、将来はわからないわけですから、回答が厳しいんですよ。だから他の判断軸を持つことが大切です」
ガチガチに家計を固めたい人もいる。半年に一度、決まった額の利子が入ってくることを確定させたいなら、固定金利を。「多少増えたり減ったりするのはかまわない、金利が上がれば利子も増えてラッキー。なんとなく上がりそうだし?」とゆるく考えられる人は変動10年。
個人向け国債の基本をおさらいしておこう。利子は年2回、半年ごと。購入は1万円以上1万円単位。銀行、ゆうちょ、証券会社など898の金融機関で取り扱っている。そのうち26の金融機関はネットで買える(24年7月1日現在)。
「金」を持つ選択肢
たとえば都市銀行では三井住友銀行、りそな銀行。地方銀行では横浜銀行など10行。主要ネット証券ではSBI証券、楽天証券、マネックス証券。対面大手では野村証券、大和証券、SMBC日興証券など。
購入から1年経てば、いつでも換金できる。「100万円のうち20万円だけ」などの一部換金もOK。中途換金の場合「直前2回分の税引き前利子×0.79685」が差し引かれるが、元本割れはしない。購入金額の上限はない。対面大手証券では「1千万円の購入でもれなく現金1万4千円プレゼント」などのキャンペーンもある。
ところで森永さんは個人向け国債を買っている?
「私は個別株と現預金のバランスでリスクを調整するのが好きなので、買っていません。株式市場が危ないと思ったら預金に切り替えています。ただ、安定資金の置き場所として個人向け国債は魅力的だと思います」
個人向け国債以外で、おすすめの金融商品を聞くと「金(ゴールド)もいい」とのこと。
「元本保証はないですが、金という現物としての価値はなくなりません。金には金というモノとしての価値があるので、紙くずになる心配もない。最近では新しく発掘された金は3割ほどを各国の中央銀行が買っているため、需給面で価格が上がりやすくなっています。絶対に安全とはいいませんが、株式などに比べたらリスクは控えめです。純金積み立てや金価格に連動する投資信託を資産の一部で持っておくといいかもしれません」
(経済ジャーナリスト・向井翔太、編集部・中島晶子)
※AERA 2024年7月15日号より抜粋