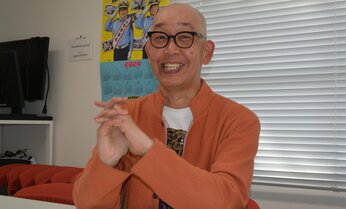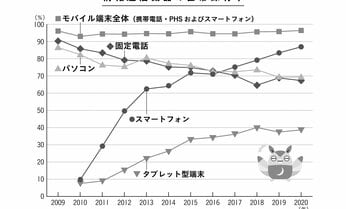「最速」よりも「数日遅い配達」選択でおトクになる仕組み 「2024年問題」で広がりの動きも
不在の際に荷物を玄関前などに置いていく「置き配」も普及したが、国土交通省の2023年の調査では、再配達となる荷物の割合はおよそ11%にのぼる(撮影/写真映像部・馬場岳人)
国連の持続可能な開発目標「SDGs」。達成に向けて、さまざまな取り組みが行われているが、今年は物流などの「2024年問題」にも直面している。持続可能な社会のために消費者一人ひとりができることは何か。AERA 2024年6月10日号より。
* * *
近年注目されているのが、持続可能な社会につながる選択をした人がトクをする仕組みだ。
LINEヤフーが運営する通販サイト「Yahoo!ショッピング」は、「最短お届け日」よりも数日遅い配達日を選択すると、1~100円相当のポイントがもらえる「おトク指定便」を昨年4月から導入している。配送日を分散し、物流業界の負担軽減に寄与するのが狙いだ。
同モール内で出店する「LOHACO」(ロハコ)で22年に試行したところ好評だったため、対象を全ストアに拡大した。ロハコの実証実験では、付与ポイントが最大30円で54%、最大20円または15円でも48%と、いずれも約半数のユーザーが利用。30~60代の女性がメインで、コスメや食品(缶詰、スープ)などの注文で多く見られた。
物流業界では「最速で届ける」ことが至上命令のように認識されているが、商品によっては「最速で受け取る」ことよりも、100円以下のおトク感を優先する利用者が少なからずいることを示している。LINEヤフーの担当者、須田琢磨さんはこう意義を強調する。
「再配達を減らすなど効率的な配送を実現できれば、CO2削減などSDGsにも貢献できると考えています」
このサービスは、再配達を避けるため、「確実に受け取れる日」に配送日を指定したい、という利用者の潜在的なニーズを掘り起こした点でも注目される。ただ、導入の可否は各ストアの判断に委ねているため、現時点で「おトク指定便」を利用できる商品は一部で、対象ストア内での利用率も約3割にとどまっているのが課題だという。
それでも2024年問題の関心の高まりを背景に、他の通販サイトでも同様のサービス導入の動きが出ている。
AERA 2024年6月10日号より
「便利だから」の見直し
ZOZOが運営する「ZOZOTOWN」は今年4月、注文翌日から4日以内に発送する「通常配送」よりも余裕のある配送日(商品注文日の5日後から10日後までに発送)を選択した場合、ポイントを受け取れる「ゆっくり配送」を試験導入した。担当者は「試験導入の結果が確認でき次第、本格導入に向けて検討したい」と意気込む。
2024年問題への対応は急務だ。とはいえ、単にトラックドライバーなどの「時間外労働の上限規制」の問題と捉え、それによって自分たちの生活にも影響が出るかもしれない、という受け止め方でいいのだろうか。これにSDGsの観点から異議を唱えるのが、環境・エネルギー問題に詳しい早稲田大学の納富信教授だ。
「大事なのは、私たちがどのような将来社会を望み、そのためには何が必要か、ということをしっかり見極めることです」
働く人の健康や人権を守ることも、持続可能な便利さや豊かさを追求することも、地球環境への負荷を軽減することも、すべてよそ事ではなく、これからの「自分」とつながっている。納富教授は企業や組織、個人それぞれが背伸びしすぎることなく、自身の持つ課題と社会課題との“つながり”を意識し、環境や社会へのインパクト(影響や負荷)を理解した上で行動を選択することが求められている、と指摘する。つまり、SDGsの目標達成に不可欠なのは、それぞれの主体性にほかならない、というわけだ。納富教授はこう強調した。
「便利だから、何かあった時のために必要だからと、多くの資源やエネルギーを消費してしまいがちな意思決定や行動スタイルは、見直すべきタイミングに来ているのではないでしょうか」
企業と消費者の双方が「サスティナブル・ファースト」の共通認識のもと、“真に必要なもの”を見極める能動的なライフスタイルへのパラダイムシフトが求められている。(編集部・渡辺豪)
※AERA 2024年6月10日号より抜粋