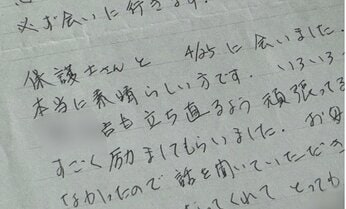トイレの「大」と「小」には大便と小便だけではない超重要な意味があった…多くの人が知らない"流し方の盲点"
3種の流すボタンがあるリモコン。「eco小」とは?(筆者撮影)
節水のために大便の際に「小」で流してもいいのか。トイレ研究家の白倉正子さんは「着眼点は悪くないのですが、忘れてはいけないのは、排泄物やトイレットペーパーがきちんと公共下水道や浄化槽まで到達するか、という点。それには『大』『小』の違いをより解像度高く理解しておくといい」という――。
トイレの流し方の不思議
みなさんはトイレの水を流す時に、節水を意識していますか?
最近のトイレの流し方は、多様化しています。例えば、レバーを押すタイプ・レバーでひねるタイプ・ボタンを押すタイプ・センサーに手をかざすタイプなど……。いろんなタイプがあり、「流し方が分からなかった」「流す部分が見つけにくくて戸惑った」なんて経験があるのではないでしょうか。
その上、流す部分をよく見てみると「大」や「小」と選べるようになっており、「eco小(エコしょう)」なんて表示があるケースがあります。これは一体どんな違いがあるのでしょうか? どうやって使い分けたら良いのでしょうか?
「大」と「小」の違いとは
例えば「大」と書いてあれば、大便(ウンチ)を流す時に使用すれば良いと思うでしょう。同様に「小」と書いてある場合は「小便(おしっこ)」を流す場合に使用すればいいと想像できます。これは正しい判断です。しかしせっかくなので、「どんな違いがあるのか」を理解すると、さらに良い使い分けができるかもしれません。
まず、洗浄水の条件の基準を定めているJIS(※)の掲載文を要約すると、「大洗浄」の条件は、「JIS P 4501に規定するトイレットペーパー(1枚重ね)を、長さ約760mmに切り、直径が約50mm?75mmの球状に緩く丸めたもの7個を、トラップを満水にした後、一度に便器内に投入し、直ちに大洗浄を行い、完全に便器外へ排出されること」と書いてあります。「小洗浄」の場合には、同様に球状の物が3つ流れるか? が基準となっています。
つまり大の洗浄の場合は、76cm×7個=532cmのトイレットペーパーが無事に流れれば良く、小の洗浄の場合には76cm×3個=228cmのトイレットペーパーが流れるのが、正常だといえます。なお、トイレットペーパー以外に、疑似汚物と呼ばれる特殊な素材で作った「ウンチの代用物」を流して性能を試すなど、メーカーごとに検査方法や基準は異なることがあります。
なお、先ほど紹介した「JIS P 4501に規定するトイレットペーパー」は、水で崩れやすいのですが、最近は温水洗浄便座用の厚手のふんわりしたトイレットペーパーが流通しています。これらは溶けるのに時間がかかるので、洗浄水を多めにしたほうが良いでしょう。
(※)参考文献:JIS A 5207:2019 衛生器具―便器・洗面器類
P.9の「8.2.1.2 排出性能試験」でのb)-3)及びd)-3)では小洗浄について述べられています。要約すると、ペーパーを丸めたものを3つが排出されることが小洗浄の基準になっています。
生理のときは要注意
しかし排泄行為は生理現象ですので、様々な状況が起こります。例えば、女性の場合、小中学生~50代ごろまで、生理(月経とも呼ぶ)が毎月のようにあります。その時に、陰部をきれいに保つために、数日間は大量の水やトイレットペーパーを使用してしまうことがあるでしょう。
こういう時は、「トイレットペーパーの長さが、228cm以上になる可能性が高まる」ので、「大洗浄」がふさわしいと言えます。無理して「小」を選んで流した場合、便器が詰まってしまい、次に洗浄をした際に汚れた水が溢れてトイレ室内を汚すことになりますし、詰まり除去業者に作業してもらわなくてはならず、他の人にも迷惑をかけてしまうからです。
間違いやすい流し方と水のトラブル
ではどうして、大量のトイレットペーパーを、「小」で洗浄した場合、詰まりやすくなるのでしょうか? それは汚物やトイレットペーパーが、便器から流される途中(専門用語では「トラップ」や「排水管」「せき」と呼びます)、または公共下水道につながっている敷地内の排水管の途中で、汚物が堆積し、流れにくい状態になってしまうからです。水溶性ではない紙(例:ポケットティッシュや箱型ティッシュ)を使ってしまった場合も、同様のトラブルが起こりえます。
トイレの流れが悪い場合には、時間をかけて数回洗浄すれば流れる場合もありますが、トイレから早く出たいがために無理やり何度も流してしまうと、汚水が便器から漏れてしまう大惨事に陥ります。
詰まりを除去する方法は、ラバーカップ(ゴム製のおわん型の詰まり除去道具)を使ったり、詰まり除去の専門業者に来ていただくのが一般的です。ですが、そうなる前に「トイレットペーパーを投入し過ぎちゃったかな?」と思ったら、ケチケチせずに「大」を選んで洗浄すれば、大きな問題にはならずに済むでしょう。
「eco小」とは何か
なお、「eco小」とは、「男性のおしっこのみを流すケース」(紙を使わない)を想定して洗浄水を少なくしています。日本のトイレは、大切な水やエネルギーを、効果的かつ効率的に使用できるよう節約機能が豊富なので、とても高性能なのですが、こうした根拠や技術があることを知ると、さらに効率的に使えるでしょう。
ただしeco小は国内最大メーカーであるTOTOだけの限定的な機能です。他のメーカー製品にはありません。最近は洗浄技術が向上したために、eco小と小の差が無くなりつつあります。そこで新製品には「eco小」のボタンがないケースがあります。
節約のために大便を小で流すのはダメなのか?
地球環境を考え、「大の時でも小洗浄で流せば、水の節約になって良いのでは?」と思うことがあるでしょう。着眼点は悪くないのですが、忘れてはいけないのは、排泄物やトイレットペーパーが、便器の内部から排出し切って、建物の中や敷地内の排水管を通り抜け、公共下水道や浄化槽まで確実に到達するか? という点です。トイレの使用者は、つい「自分の目の前の便器から、汚物が消えればOK」と思いがちですが、それだけでは「終わった」といえません。
具体的に説明すると、汚物(=ウンチやトイレットペーパー)は、便器の内部のトラップ部分(古い便器なら、横から見ると分かるでしょうが、上り坂になっている部分やカーブしている部分)を通過したあと、排水管(床や壁に埋まって見えないケースが多い)に到達し、建物の中や敷地内を通過して、道路の下部に埋められている公共下水道に到達しなければなりません。公共下水道が完備されていない地域では、庭や駐車場に埋まっている「浄化槽」まで到達しなければなりません。
高層の建物ならば、高さがあるために公共下水道までの排水経路は長くなりますし、広い敷地の場合には、排水管がくねくねと建物の形にそって設置されているため、これもまた排水管が長距離化します。その中を汚物が流れるわけですから、それを手助けする洗浄水が少ないと、勢いが少なくなってしまい、汚物が途中で止まってしまうのです。
それが次から次へと連続した場合、「汚物の行列」ができてしまいます。そうなると洗浄水を流しても、水だけが通り過ぎてしまい、本格的に詰まってしまいます。もしも汚物が壁のように立ちはだかると、逆流することもありえます。
そうなると大がかりな対処が必要となるため、せっかく節水や節約をしても、逆に水を大量に流して回復させなくてはならず、余計な出費が増えてしまいます。これでは本末転倒です。詰まる物は汚物以外に、生理用ナプキンやペンなどもよくあります。便器内に汚物以外が落ちたら、早く便器の外に出しましょう。
どうしても節水したいなら…
よって、どうしても節水をしたいのなら、節水型の便器に交換をすると良いでしょう。
それから、下水道から見て、トイレの位置より奥(上流側)にお風呂や台所があり、そこから流れ出てくる生活雑排水と一緒にトイレの汚物が流されるなら、一緒に到達するかもしれません。またマンションなどの集合住宅では、他の家庭と排水管を共用する場合もあるので、他の家庭の雑排水と一緒に流されるかもしれません。いずれにしても壁や床で見えない部分の話なので、正しく見抜けない場合が多いでしょうから、強引な判断はしないほうが良いと思われます。
なお、ロータンク(便器のそばにある、水が入っている陶器)の中に、水を入れたペットボトルを入れて節水効果を期待する人がいますが、洗浄水量をむやみに減らしてしまうだけでなく、ロータンクの中の部材にぶつかって部材を壊してしまったり、部材にひっかかり、水漏れを起こすことがあるため、お勧めできません。便器のメーカーでも禁止していますので、やめましょう。
なお蛇足ですが、公共トイレの小便器も、むやみに節水をすると、尿の汚れの塊(尿石やソフトスケールと言います)が発生してしまい、詰まりや悪臭の原因になり、大がかりな対策を数年後にしなくてはならないケースが想像されます。よってこれも安易に判断しないほうが良いでしょう。
自動洗浄は、「大・小」をどう判断しているのか
最近は、用を足した後に自動で流れる「自動洗浄機能」が付いているトイレがあります。この場合は、着座している時間の長さで大か小かを判断しています。例えば30秒以上の着座をすると「大」として洗浄され、30秒未満は「小」で流れるそうです。ということは、小便だけでも、ゆっくり座っていたら立ち上がると「大」で流れてしまうことになります。そんな時は、立つ前に自分で手元のリモコンの「小」を押せばOKです。なので、うまく使い分けを行ってください。
SDGs(持続可能な開発目標)が認知され、人々の心に地球環境を守ろうとする意識が高まっています。日常生活で頻繁に使うトイレでも、「何かできないか?」と思って行動につなげることは、素晴らしいことです。しかしその思いが、知識不足のために、新しい課題を生んでしまうケースも、残念ながらありえます。またそれぞれの環境によっても状況が異なります。トイレに関しては、取扱説明書を正しく読んで、疑問があればメーカーのお客様相談コーナーなどに相談をして、判断してください。
(白倉正子:トイレ研究家、取材協力=ニッポー設備 田中友統ほか)