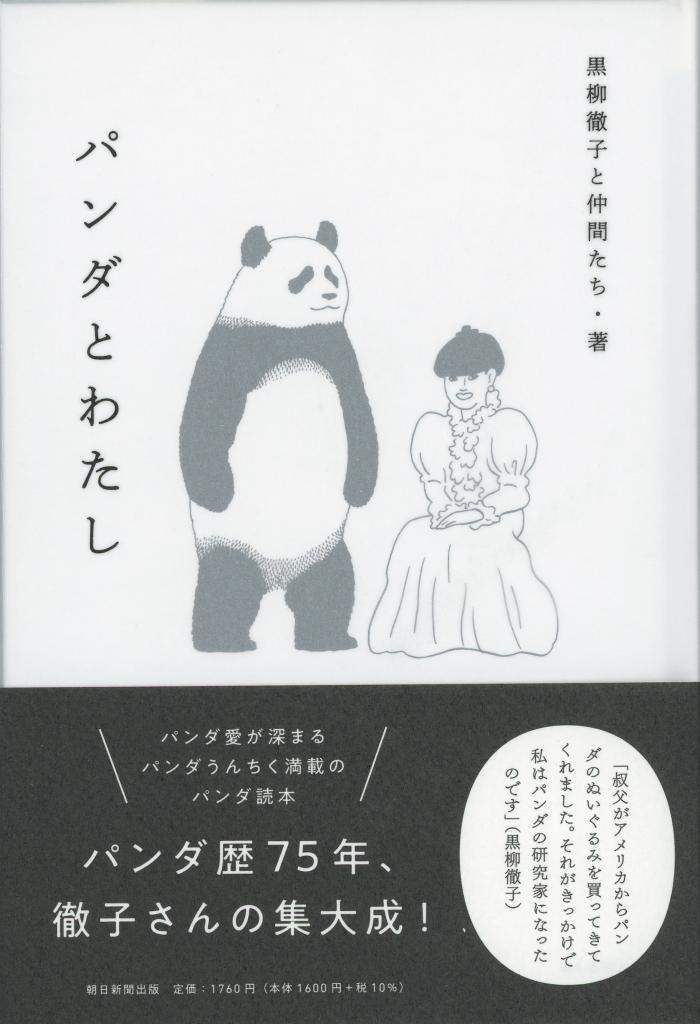
※Amazonで本の詳細を見る
さらに、羅願(らがん、1136~84年)が『爾雅翼(じがよく)』という書物を著します。この書物は、草・木・鳥・獣・虫・魚に関する語を集め、それに説明を加えた、いわば動植物専門辞典ですが、「爾雅を補佐する」というタイトル、配列方法を『爾雅』に倣うなど、『爾雅』を強く意識した後継書といってよく、『爾雅』の郭璞注も大いに利用されています。
羅願による「貘」の説明もやはり、郭璞注や『説文解字』に依っているのですが、特筆すべきは、さらに「今出建寧郡(今も建寧郡<四川省>にいる)」という説明を加えている点です。具体的にどんな動物かというと、「毛黒白臆,似熊」とあります。解釈は難しいのですが、おそらく「毛は黒いが、胸のあたりは白い」ということでしょう。これも私たちにパンダを想起させるには十分な情報です。羅願自身がパンダを見たのかどうかはわかりませんが、間接的にであれ、目撃情報を得ていたのではないかと想像させられます。
また、『説文解字』や『爾雅』の郭璞注に見える「豹」、「白豹」はたびたび「貘」の異称として説明されていますし、「●【ばく、豸へんに白】」という動物も、『文選(もんぜん)』という詩文のアンソロジーに8世紀の人がつけた注釈に「●獣、毛黒白臆,似熊……出建寧郡也(●という動物は、毛は黒いが胸のあたりは白く、熊に似ていて……建寧郡に出没する)」とあるなど、「貘」と同一視する文献があり、「●」と「貘」とは発音が同じ(近い)と記した文献も多数あります。これらも「貘」と同様パンダとつながっていると考えてよいと思います。
このころまでは「貘」と呼ばれる生き物とパンダとは結び付けてもよいのではないか、というのが私の考えです。
■パンダは銅や鉄を食べていた?
――「このころまで」というと、その後、違う生き物を指すようになるのでしょうか?
私は、宋以降、明の時代までには、「貘」は現実のパンダを指す名称としては機能しなくなっていったと考えています。



































