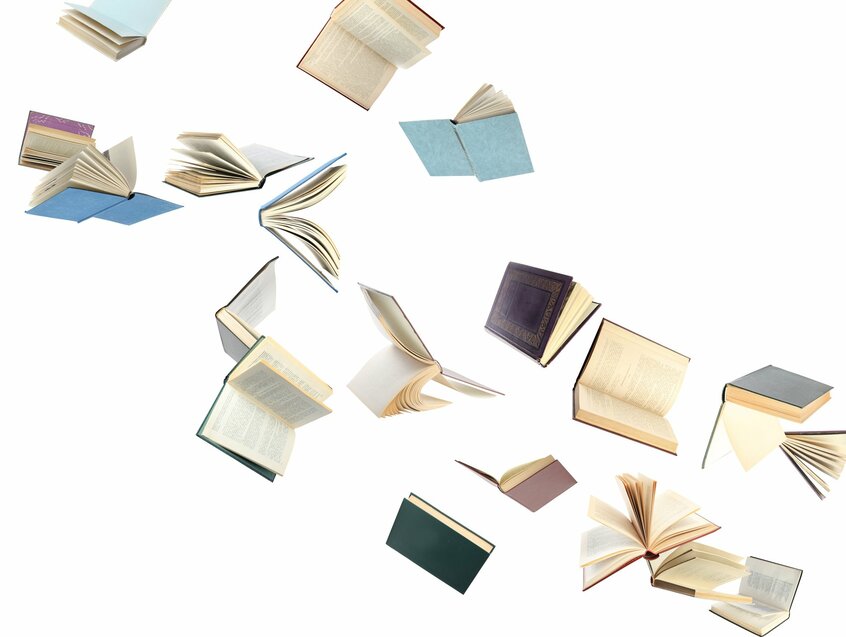
『ゲーテはすべてを言った』で芥川賞を受賞した鈴木結生さん。『一冊の本』の巻頭随筆で、自身の創作秘話を語っている。
本の中の本(book in the book)。本の中に登場する本の存在感に魅了され、物語を紡ぐことを決意した鈴木結生さんが、感銘を受けた文豪たちの「book in the book」とは?
登場人物の設定で真っ先に考えることは?
『ゲーテはすべてを言った』で最も力を入れたことは?
そして、鈴木さんの目指す理想とは?
鈴木結生さんが描く本の中の本。その秘密を覗きたい方は、ぜひご一読あれ。
* * *
本は、本の中にあるときが一番魅力的だと思う。この感覚に名前がついているのかどうか(つまり、それが私に限ったものでなく、多くの人にも共有されているのかどうか)私は知らないが、実例だったら幾らでも。
まず思い出すのは、村上春樹氏の『1Q84』だ。青豆という女性主人公が、宗教団体の教祖を暗殺した後、潜伏する部屋の中でプルーストの『失われた時を求めて』を読み進める。これを初めて読んだ時、私は小学五年生、まだプルーストのプの字も知らなかった。よって、『失われた時を求めて』が実在の本なのか、あるいは『空気さなぎ』という作中作と同様、作者が考えたものなのか、ということから既に判断がつかなかった(後々『失われた時を求めて』が有名な作品なんだと知った時も、「ああ、あの青豆が読んでたの。本当にあるんだ」と思ったくらい)。同じく村上氏による『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』では、主人公がボルヘスの『幻獣辞典』を図書館で借りる、という一節があり、私はこのボルヘスはデレク・ハートフィールドの仲間だろうと信じて疑わなかった。これはいかにも初心者的感覚だが、余りに引用が多いので、まさか実在する本からここまで拝借するはずがあるまい、と思ったのである。やがて、ボルヘスを読むようになってからは、その小説とも評論ともつかないテクストの中で並べられる、コールリッジとか、ピエール・メナールとか、ホーソーンとかといった人名が実在なのか虚構なのか、さして気にならなくなっていった。また、大江健三郎の『洪水はわが魂に及び』に、主人公・勇魚と青年のグループが、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』の英訳版とメルヴィル『白鯨』をテクストとして英語の勉強をする、というシーンがある。これを初めて読んだ時、私は既に『カラマーゾフ』も『白鯨』も読んでいたけれど、自分が読んだのより面白いバージョンをこの人たちは読んでいるんじゃないか、という気がした。




































