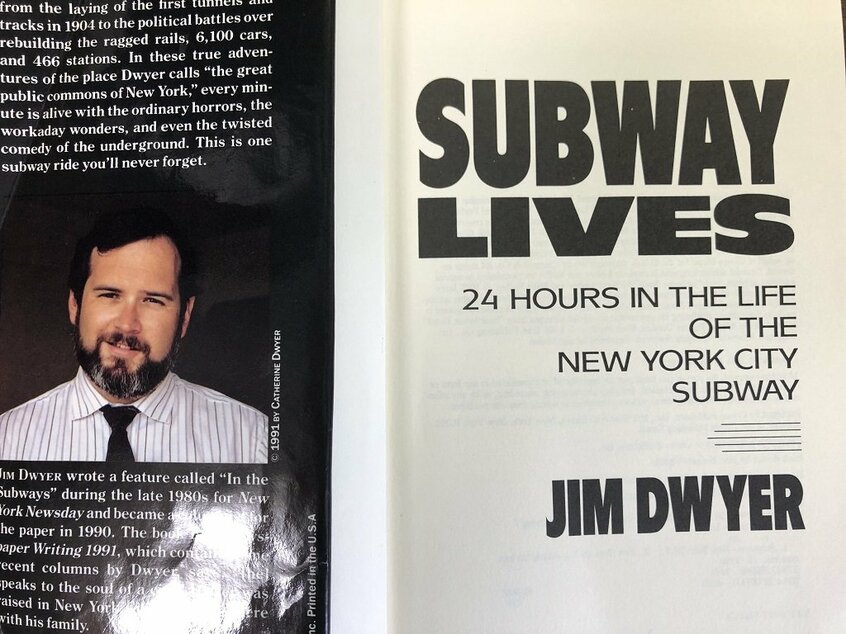
〈二〇二〇年八月に夫がいなくなってから二年を過ぎる頃まで、何を見ても彼を思い出す日々が続いた〉
という文章で始まるノンフィクション作家青木冨貴子の『アローン・アゲイン 最愛の夫ピート・ハミルをなくして』(新潮社)はそれまで硬質のノンフィクションを書いてきた青木さんの筆致とはうってかわって、柔らかく優しい筆致で最後まで読者をひっぱる。
ピート・ハミルは、短編「黄色いハンカチ(原題はGoing Home)」が山田洋次監督で映画化された(「幸福の黄色いハンカチ」)ことで、日本でも1980年代に一気に有名になった作家だ。青木さんは、来日したピート・ハミルをインタビューしたことが縁で、1987年5月にニューヨークで結婚をし、「死が二人を分かつまで」一緒だった。いや死は二人を分かつことはなかった、ということがしみじみとわかるエッセイだ。
この本に関する多くの著者インタビューや書評が夫婦二人の物語のアングルでまとめたものになるだろう。
が、私は、この本の隠れテーマについて書いてみたい。
それは、郷愁をさそうニューヨークのタブロイド紙の世界だ。
ピート・ハミルはタブロイド紙の申し子だった。ニューヨーク・ポスト紙やニューヨーク・デイリー・ニューズ紙にコラムを持ち、短期間だが、90年代に、この二紙の編集長もつとめている。そしてそもそも「黄色いハンカチ」はニューヨーク・ポスト紙に掲載された短編小説なのだ。
高校をドロップアウトしたピートが、1958年、当時のポスト紙に夜勤の記者として採用されるときの裏話。93年ポスト紙が新しいオーナーに買われて、ピートを含むほとんどのスタッフを首にすると宣言したとき、社屋を追い出されても近くのダイナーに陣取って新聞の編集発行をつづけたことや、97年にデイリー・ニューズの編集長に不動産王から請われて就任したが、8カ月で首になったこと等々。
一緒に暮らした青木さんが覗き見たタブロイド紙の世界が活写されている。
よりささやかな物語に惹かれた者たち
私がニューヨークのタブロイド紙に思い入れがあるのには理由がある。





































