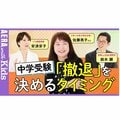「本人の気持ちと、周りからの期待にギャップがあったんだと思います」
6年生になると、体調にも異変が出始め、ほぼ皆勤だった学校も休みがちになってしまった。親子で話し合い、塾を休むことを決めた。その後は彼女の意思で、中学受験をやめて地元公立中に進んでいる。
「こちらも一緒になって受験についていろいろと手伝っていましたが、かえってそれが本人の負担になっていたのかもしれません。下の子はあまり深入りせずに、やめたかったらやめたらいいという気持ちで塾を続けさせています」
長女は体調も戻り、今は高校受験に向けて再び通塾を始めた。
この家庭のように、子どもの様子に合わせて「休む」という選択を許された子は幸せだが、中にはどうにも止められなくなり、半ば強制的に受験に向かう家庭もある。偏差値競争を戦うような中学受験に踏み入ると、通常の授業以外に特別講習なども追加され、それなりのお金もかかる。そして、成績が上がれば上がるほどもっと上を目指せるかもと、親の気持ちもはやる。
自分はここまでの人間
「時間とお金を掛けている分、引き返せない親子は多いと思います」
こう話すのは『「なんとかなる」と思えるレッスン』の著者で、ストレスマネジメントの専門家、舟木彩乃さんだ。中学受験が「沼」と呼ばれるゆえんは、親も子も一度のまれたら引き返すのが難しい所にあるのだが、受験が終わってもこの沼にハマり続けるケースもあるという。
「社会に出れば、人間の価値は成績や入った学校名だけではないと分かるのですが、子どもの世界は狭いため、いろいろな物差しがあることをまだ知りません。成績という物差しだけで考えて“自分はここまでの人間なんだ”と思い込んでしまう子もいます。そこが一番の問題で、“やってもどうせダメだから”と、その後も挑戦しない人間になってしまいます」
中学受験は早熟な子には向くが、そうでない子が偏差値競争に突入すると大人になっても拭えない傷を負う可能性がある。
今年は塾の講師による不祥事が大きく報じられることとなったが、講師からの罵声でメンタルをやられる子どももいる。学校の教員になる場合には児童心理学などの学びが必ず課されるのだが、塾講師にそれはない。
「塾は場合によっては学校よりも長い時間を過ごすこともあります。子どもに関わる職業ですから、児童心理についての知識を備える必要があると思います」
塾は成績を上げて“ナンボ”の世界。教育ではなく産業だということを、親は重々承知しておく必要がありそうだ。(フリーランス記者・宮本さおり)
※AERA 2023年12月11日号より抜粋