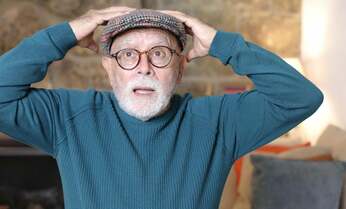
「病気」に関する記事一覧
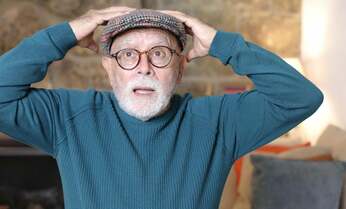



【子どもの便秘】家庭でケアは難しいことが多い。慢性化を防ぐには早期の治療が大切
腸の水分調節機能には個人差があるため、便の硬さは生まれつきの体質に左右されます。水分や食物繊維をしっかりとっても便秘になりやすい人は、たくさん汗をかく夏に、より便秘になりやすくなるもの。なかでも1~3歳の小さい子どもは便秘が「トラウマ」になりやすく、慢性化・重症化しやすいので、早い段階で大人が気づいて、きちんと治療することが重要です。パルこどもクリニック院長で「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」作成委員会委員長でもある友政剛医師のお話を、前編後編に分けてお届けします。前編に続き、後編では「子どもの便秘の治療法」を紹介します。

【子どもの便秘】排便の痛みが「トラウマ」になることも。対処法を小児科医が解説
観測史上最も早い梅雨明けとなり、猛烈な暑さが続くこの夏。小児科の友政剛医師は熱中症だけでなく、子どもの便秘の増加を危惧しています。夏は1年の中でもとくに便秘が起こりやすい季節ですが、子どもの便秘は放っておいてはいけない理由があります。とくに1~3歳の小さい子どもは便秘による排便時の肛門の痛みやかん腸が「トラウマ」になりやすく、排便を我慢するようになることで、便秘が急速に慢性化し、重症になりやすいのです。パルこどもクリニック院長で「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」作成委員会委員長でもある友政医師のお話を、前編後編に分けてお届けします。前編では「子どもの便秘の問題点と対処法」を紹介します。


食べては吐くを繰り返す「神経性過食症」や拒食症 ダイエットが発症のきっかけに【チェックシート】
かつては拒食症と呼ばれていた「神経性やせ症」やいったんのみ込んだ大量の食べ物を意図的に吐き出す「神経性過食症」などは、「摂食障害」と呼ばれる精神疾患の1つです。うつ病、統合失調症、不安症といった精神疾患を持つ人の半数は10代半ばまでに発症しており、全体の約75%が20代半ばまでに発症しています。精神科医で東京都立松沢病院院長の水野雅文医師が執筆した書籍『心の病気にかかる子どもたち』(朝日新聞出版)から、「摂食障害」についてチェックシートとともに、一部抜粋してお届けします。前編・後編の2回に分けて紹介します。





特集special feature






3分診療でも医師の力を最大限に引き出す方法とは? 患者のコミュニケーション力は治療効果に影響
体調が不安で、医師にいろいろ相談したい。そう思って病院に行ったのに、いわゆる「3分間診療」に、十分な会話もできずに帰ってきたという人も多いのではないでしょうか。診察時間を長くすることは難しくても、満足できる診療を受けることは可能であり、そのためには「コミュニケーション力」が求められます。近年は、コミュニケーションが治療の効果や患者・家族・医療者の満足度に大きな影響を与えることも明らかになってきました。短い診察時間でも医師とコミュニケーションをしっかり図るにはどうしたらいいのか。ヘルスコミュニケーション学関連学会機構副理事長の宮原哲氏(西南学院大学外国語学部教授)が患者に必要なコミュニケーション力について語ります。


























