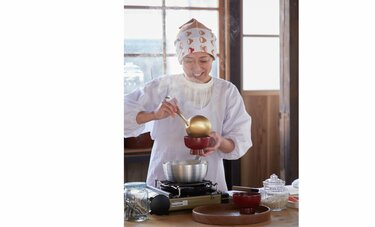■初期症状は二日酔いと酷似
高度が上がるほど気圧は下がり、呼吸で得られる酸素量は標高3000mで平地の約3分の2に、5000mでは約半分に減少する。急激に高度を上げて、こうした過酷な環境に突入すると、体は順応できず、酸素不足でさまざまな不具合を起こす。この状態が「急性高山病」だ。
主な症状は、頭痛、吐き気や嘔吐、めまい、倦怠感(けんたいかん)。「山酔い」とも呼ばれる症状で、中でも頭痛はほとんどの人に出現し、最初にあらわれることが多い。登山経験が豊富で、「健康登山塾」塾長の齋藤繁医師は、こう説明する。
「酸素不足になった脳は、酸素を取り込むために流れ込む血液を増やしてむくんでくる。その結果、頭蓋骨の内側の圧力が高くなって、脳の表面を走る痛みの神経や吐き気の中枢が刺激され、症状が出ると考えられています。同じように脳がむくんだ状態になる『二日酔い』の症状とよく似ています。また、睡眠中は起きているときに比べて酸素を取り込む能力が低下するため、山小屋に泊まった翌朝に突然症状が出てきたり、悪化したりすることも少なくありません」

山酔いが重症化し、肺に水がたまる「高地肺水腫」になって呼吸ができなくなったり、脳が腫れる「高地脳浮腫」で意識障害に陥ったりすれば、命にかかわる。山酔いの症状が見られないままいきなり高地肺水腫や高地脳浮腫を発症することもあるという。
Aさんは看護師に指導を受けながら深呼吸を繰り返したところ、なんとか動けるまで回復。医師の指示に従って友人たちとともにゆっくり下山することにした。高度を下げるにつれて症状はみるみる楽になり、5合目の登山口に到着するころにはすっかり元気を取り戻していたという。Aさんはこう話す。
「一緒に登った3人とも高山病の知識がほとんどなく、そばに救護所がなかったら本当に危なかった。高山病の症状と『低いところに移動する』という基本的な対策だけでも知っていたら、早く気づいて対処できたかもしれません」
 熊谷わこ
熊谷わこ